「ブラックアース~ホロコーストの歴史と警告」ティモシー・スナイダー著池田年穂訳 を読んで
ホロコーストについても、観光学で歴史や伝統は後から作られると説明してきたが、この本を読んでさらにその思いを強くした。別に虐殺を否定するのではなく、文脈の中で理解しないといけないということである。
著書の最後に「訳者あとがき」があり、簡明にまとめてある。
エストニアとデンマークはドイツから命じられたにもかかわらず、極端な差が出たと記述がある。エストニアでは1940年にソ連に占領され、ドイツがやってきたとき99%のユダヤ人は殺害されていた。デンマークは市民権を持つユダヤ人の99%は生き延びたとある。エストニアのイメージが一変する史実である。二年まえ日帰りでタリンを旅行したが、その時知っていればもうすこし見方が変わったかもしれない。
著者のスナイダー氏への質問と回答も紹介され、その中で
・ホロコーストは戦前のドイツの国境線の外ですべて起きているということ、
・犠牲者の97%はドイツ国外の出身のユダヤ人であった
・ユダヤ人の、現実には死の穴の縁で殺害されたものが半数で、実際に収容所の中にあったというわけではない特別なガス殺の設備で殺されている
・殺害に携わったドイツ人の多くはナチスではなかったし、そもそもドイツ人でもなかった
・国家崩壊の地域で起きた特別な種類の政治を考えないとホロコーストは理解できない出来事(政治領域を超えている)
・ホロコーストは理解できるのもであり、理解しなければいけないこと
ということが強調されている。驚きの事実である。
ソ連に占領され、そこへドイツが侵入し、国家が崩壊を重ねた結果がホロコーストなのであろう。
バルト三国、東部ポーランド、ソ連領内(ウクライナがまさにブラックアース)でのユダヤ人が殺害されたのである。
杉原千畝氏がリトアニア勤務であったことも理解ができた。
私は、外人船員に頼り切っていた海運産業行政の経験から、日本社会が外国人を受け入れないことに反対してきたが、
考えてみると日本人こそが特殊な事態になった時、エストニアやポーランドのようになりかねないかもしれないのであると、この本読み思い直した。
原発事故の際に整然としてたと日本人は評価が高いのであるが、関東大震災での朝鮮人殺害を繰り返す恐れが無きにしも非ずと思ってしまった。
特に、韓国人に対する最近の接し方を見ると、日本社会に外国人の集団を受け入れた時、とんでもないことをする日本人が出てきそうな気がしだしたのである。
なお、ホロコーストについて日本の中でも戦後すぐには問題になっておらず、中東戦争あたりから話題になってきたことにつき、ユダヤ人側からの事情として書かれたものがある。黙って死んでいったユダヤ人を当初シオニズムは評価しなかったのであるが、それが変わりだしたのが、第二次中東戦争あたりからであるといことが書かれていた。確か岩波新書であったような気がする。
関連記事
-

-
QUORAにみる歴史認識 英国はなぜ世界の覇者になれたんでしょうか?
英国はなぜ世界の覇者になれたんでしょうか? この話を解く鍵は実はイギリスにはないと
-
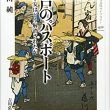
-
『江戸のパスポート』柴田純著 吉川弘文館
コロナで、宿泊業者が宿泊引き受け義務の緩和に関する政治的要望を行い、与党も法改正を行うことを検討
-

-
『不平等生成メカニズムの解明』「移民はどのようにして成功するのか」竹中歩・石田賢示・中室牧子
「移民はどのようにして成功するのか」竹中歩・石田賢示・中室牧子『不平等生成メカニズムの解明』ミネルバ
-

-
Quora6に見る歴史認識 イギリスが中国にアヘンを売ったのは有名です。あるイギリス人の言い訳が、アヘンを売り始めた頃中国には麻薬の売買を禁止する法律が無かったから問題ない。これ真実ですか?それにしても犯罪者の理屈ですよね?
アヘン戦争に対する一般的なイメージ。それは以下の様なモノです。 「大英帝国が清国を麻
-

-
QUORA 李鴻章(リー・ホンチャン=President Lee)。
学校では教えてくれない大事なことや歴史的な事実は何ですか? 李鴻章(リー・ホンチャン=Pre
-
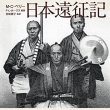
-
角川文庫『ペリー提督日本遠征記』(Narrative of the Expedition of an American Squadron to the China Seas and Japan)
https://youtu.be/Orb9x7NCz_k https:
-

-
「南洋游記」大宅壮一
都立図書館に行き、南洋遊記を検索し、[南方政策を現地に視る 南洋游記」 日本外事協会/編
-

-
『カジノの歴史と文化』佐伯英隆著
IRという言葉の曖昧さ p.198 シンガポールにしても、世界から観光客を集める手法として、
-

-
🌍🎒モンゴル観光調査の準備~社会主義が生み出した民族の英雄~
8月17日から2週間、地球環境基金の仕事でモンゴルの観光、環境調査に参加する。予備知識を得るため参考
-

-
『逆説の日本経済論』貿易決済のための為替取引量は、今や東京為替市場で見れば、その取引量の8分の1程度に落ちている。それ以外は資本取引
貿易決済のための為替取引量は、今や東京為替市場で見れば、その取引量の8分の1程度に落ちている。それ以

