2016年7月29日「ファイナンスの哲学」多摩大学特任教授堀内勉氏の講演を聞いて
資本主義の教養学公開講座が国際文化会館で開催、場所が近くなので参加してみた。
1 資本主義研究会の立ち上げ主旨が、1政策論 2経済論 3経済思想 4人間論とあったが、私は「政策」と「政策以外のもの」の違いは「公権力の行使」があるかないかだと思っているので、経済論より先に政策があるのは理解ができなかった。政策などなくても経済は存在すると思っていたからだ。
2「貨幣経済が浸透する前は多くの人が土地に縛られ、移動の自由を持たず」との認識は、農業生産が始まってからの人類のことしか考えていないからであろう。農業が始まる前の長い期間人類は移動し続けていた。そして江戸時代でも定住民以外の民が数多く存在したとも伝えられている。そもそも人類は移動を前提にDNAが形成されているのである。農奴のことを連想するが、農業が始まって人類が土地に縛られたのかはわからないが検証が必要であろう(トルコのチャタルヒユユク、ギョゲクリテペ遺跡)。
「純粋の経済人」のことにも触れているが、法律の世界も人はすべてが平等というフィクションでできている。政治の世界も一人一票で、男女の差、納税額の差はない。あるのは年齢だけであろう。代表者の割合に格差があることは憲法判断にまでなっている。
3 今回参加してためになったことに、「利子」のことがある。キリスト教もユダヤ教もイスラム教も、「同胞」のカネの貸し借りに利子をつけることが禁止されているということであった。逆説的だが、宗教で禁止なければ利子をとることは自然な出来事であったということになる。アリストテレスもポリス共同体を崩壊させる恐れがあると考えていたことを紹介していた。12世紀のキリスト教はこの「同胞」はすべての人間に当てはまるとされていたようだ。
しかし、キリスト教徒ではない者は人間扱いされていなかったと考えなければ理解ができない。人を奴隷に平然とできたのはキリスト教徒ではないからだと理解していた。そのうえで人扱いしない者は利子をとってもいいということも理解しがたいことであり、私の頭の中は混乱している。
私の個人的な見解では、損害賠償の計算において、ホフマン係数というものがあり、将来価値を現在価値に引き戻すための計算がある。法定利息5%を基に、複利計算をする時代に仕事をした。今のようにデフレだと、マイナス金利が考えられるのだが、依然としてホフマン係数はプラス金利であろう。精緻な証拠主義で審理しているにもかかわらず、最後はホフマン係数みたいな蓋然性の低いもので処理をせざるを得ない非合理性を指摘して、倉田卓司判事は、定期金賠償理論を打ち立てた。私もこれに影響を受けて、自賠責保険の定期金賠償を提案したことがある。しかしデフレまでは想定できなかったところが、時代の人間なのであろう。
4 最後に資本主義とは何かという問い。堀内氏のテーマである。
私は問題意識がなかったが、資本主義と資本主義でないもの違いが何かということを頭に置きながら聞いていたが、最後まで分からなった。民主主義はかなりのレベルで普遍的思想として認知されているとかんがえる。従って非民主的という字句が存在するのであろう。北朝鮮も民主主義を標榜している。
これに対して資本主義はどうか。
資本主義が普遍的な何かの法則なのであれば、万有引力の法則みたいに、仮定を置けばすべて正しいことになるが、どうもそうではなさそうである。佐伯氏は普遍的な定義を目指して「人間の欲望のフロンティアを開拓し拡張する自己運動」とされるようである。イギリスの産業革命を中心に考えなくてよい定義であるが、逆に何のために定義するのかわからない。産業革命もあったのかなかったのか議論があると聞いている。フェルナン・ブローテルは「市場経済と資本主義は全く別のシステム」としていることが紹介されていた。
資本主義が思想だとすると、思想なのだから、別の思想があってもよさそうだが、アンチ資本主義的な思想しか聞いたことがなく、よくわからない。
市場というものが存在し、資本、金利というものが存在することまではなんとなくわかるのだが、その先がよくわからないのである。
なお、経済学者の原田泰氏は「封建社会では人々は生まれたときからすべて決められてしまうが、資本主義社会では人々は自ら運命を開拓することができる」と指摘しているようだが、江戸時代も階層間の移動は活発であったようだから(士農工商ではなかった)、封建社会と資本主義社会を二項対立的に説明するには無理があると思う。
関連記事
-

-
『金語楼の子宝騒動』(「あきれた娘たち」縮尺版)少子高齢化を想像できなかった時代の映画
1949年新東宝映画 私の生まれた年である。嫁入り道具に風呂敷で避妊薬を包むシーンがある。優生保護
-

-
ヴィアレッジョ スーパーヨットの街
地方創生は無理をしないで伝統を発展させれば、人口6万の町でもトランプさんはヨットを注文してくるのです
-

-
伝統も歴史も後から作られる 『戦国と宗教』を読んで
横浜市立大学の観光振興論の講義ノート「観光資源論」を作成するため、大学図書館で岩波新書の「戦国と宗
-

-
『2050年のメディア』下山進
日本の新聞がこの10年で1000万部の部数を失っていることを知り、2018年4月より、慶應義塾大学
-
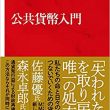
-
『公共貨幣論入門』山口薫、山口陽恵
MMT論の天敵 Amazonの書評(注 少し難解だが、言わんとするところは読み取れ
-

-
人流・観光学概論修正原稿資料
◎コロナ等危機管理関係 19世紀の貧困に直面した時、自由主義経済学者は「氷のように
-

-
QUORA ゴルビーはソ連を潰したのにも関わらず、なぜ評価されているのか?
ゴルバチョフ書記長ってソ連邦を潰した人でもありますよね。人格的に優れた人だったのかもしれませんが
-

-
2018年3月14日 CATVで クリミナル・マインド 国際捜査班 死神のささやき を見て
自画自賛のインバウンド宣伝が多い中、クリミナルマインド国際捜査班の第4話は日本がテーマ。高視聴率を誇
-

-
公研2019年2月号 記事二題 貧富の格差、言葉の発生
●「貧富の格差と世界の行方」津上俊哉 〇トーマスピケティ「21世紀の資本」
-

-
人間ってなんなの?:チンパンジーの4年戦争【 進化論 / 科学 / 人 類 】タンザニア
グドール 道具を使うチンパンジーを発見 ジェーン・グドール(Dame Jane Morris Go


