書評『我ら見しままに』万延元年遣米使節の旅路 マサオ・ミヨシ著
p.70 何人かの男たちは自分たちの訪れた妓楼に言及している。妓楼がどこよりも問題のおこしやすい場所である。故国では、そのようなところを訪れることは生活の一部として許されていた。従って使節一行の男たちが、妓楼を自分たちの工程に組み込むことは当然のことであったろう。
彼らは口をそろえて説明している。自分たちがそこを訪れる理由は、普通そのようなところを訪れる理由とは違うのだと。例えば、熟睡のためだと。
関連記事
-
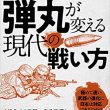
-
『弾丸が変える現代の戦い方』二見龍 照井資規 誠文堂新光社 2018年
本書は、今までほとんど語られてこなかった弾丸と弾道に焦点を当てた元陸上自衛隊幹部と軍事ジャーナリ
-
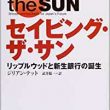
-
『セイビング・ザ・サン リップルウッドと新生銀行の誕生』ジリアン・テット 武井楊一訳
バブル期の金融問題に関する書籍は数多く出版され、高杉良が長銀をモデルに書いた『小説・ザ・外資』はハ
-
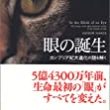
-
『眼の誕生』アンドリュー・パーカー 感覚器官の進化はおそらく脳よりも前だった。脳は処理すべき情報をもたらす感覚器より前には存在する必要がなかった
眼の発達に関して新しい役割を獲得する前には、異なった機能を持っていたはず しエダア
-

-
ウェストファリア神話
国際観光を論じる際に、文科省からしつこく、「国際」観光とは何かと問われたことを契機に、国際について
-

-
ここまで進化したのか 『ロボットの動き』動画
https://youtu.be/fn3KWM1kuAw
-

-
中山智香子『経済学の堕落を撃つ』
経済学は、なぜ人間の生から乖離し、人間の幸福にはまったく役立たなくなってしまったのか? 経済学の
-

-
QUORAにみる観光資源 なぜ、現代に、クラシックの大作曲家が輩出されないのですか?大昔の作曲家のみで、例えば1960年生まれの大作曲家なんていません。なぜでしょうか?
とっくの昔に旬を過ぎている質問と思われますが、面白そうなので回答します。 一般的に思われてい
-

-
DNAで語る日本人起源論 篠田謙一 をよんで(めも)
篠田氏は、義務教育の教科書で、人類の初期拡散の様子を重要事項として取り上げるべきとする。 私も大賛
-
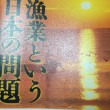
-
『漁業という日本の問題』勝川俊雄 日本人は思ったほど魚を食べてない。伝統の和食イメージも変化
マスコミによってつくられた常識は、一度は疑ってかかる必要があるということを感じていますが、「日本人は
-

-
人流・観光学概論修正原稿資料
◎コロナ等危機管理関係 19世紀の貧困に直面した時、自由主義経済学者は「氷のように
- PREV
- 書評『山形有朋』岡義武 岩波文庫
- NEXT
- 歴史認識と書評 岡部伸『消えたヤルタ密約緊急電』

