『時間は存在しない』カルロ・ロヴェッリ
公開日:
:
最終更新日:2021/08/05
出版・講義資料
『時間は存在しない』は、35か国で刊行決定の世界的ベストセラー。挫折するかもしれないので、港区図書館利用。順番待ちで一年かかった。観光資源の一つに錯覚観光があり、錯覚は人間の脳が、時間、空間を自分の都合の良いように解釈してしまうことが原因で発生することを知人の著書から学んでいた。正直「詩情あふれる筆致で時間の本質を明らかにする、独創的かつエレガントな科学エッセイ」と評されるロヴェッリの本文より、本文を読んだあとの吉田伸夫氏の日本語版解説が、素人には理解しやすかったように思う。
ロヴェッリによれば、この世界の根源にあるのは、時間・空間に先立つネットワークであり、そこには時間の流れは存在しない(「世界は”もの”でできているのではなく、”こと”ででできている。世界は相互に連結された出来事のネットである。そこに登場する変数は確率的な規則に忠実に従う。」)。しかし、人間には時間は過去から未来に流れているように感じる、その理由は何か。一般相対性理論等には過去と未来を区別するような時間の方向性はない(「量子重力の基本方程式は時間変数を含まず、変動する量の間のあり得る関係を指し示すことでこの世界を記述する。」)。時間の向きが指定できるのは、エントロピーの増大という統計的な変化を考慮に入れた場合に限られる。人間は部地理現象の根底にある微細な基礎過程を識別できず、統計的な側面だけをぼんやりとした視点で眺めるので、一方的な変化を感じることになるだ。「人間が一様で順序付けられた普遍的な時間について語る仕組みを持っているから」で、その仕組みは1)我々の持っている特殊な視点では、エントロピーの増大を頼りとして時間の流れを認識するから(時間の方向性は視点がもたらす)。2)人間の脳は過去の記憶を集め、それを使って絶えず未来を予測しようとする仕組みを持っているから。
時間が経過するという内的な感覚が、未来によらず過去だけに関わる記憶の時間的非対称性に由来することを指摘する。その上で記憶とは、脳の中における物理的なプロセスが生み出したものであり、過去の記憶だけが存在するのはこのプロスがエントロピー増大の法則にしたがうことに直接的な帰結であると論じる。Amazonの書評に「私たちが感じる時間は、宇宙に普遍の原理ではなく、人間が相互作用できる世界との間に生じさせているアフォーダンスなのだ」と記述があるが、なんとなくわかったような気にさせてくれる。なお、Amazonの別の書評では原題「The Order of Time」を引用して「この本のもっとも重要なメッセージは、「時間が存在しない」ことではなく、「もっとも基本的な方程式には含まれなかった時間が、われわれが経験し、実験し、理論と経験とを突き合わせるレベルでは、なぜ、どのようにして生じるのか」ということ。さらに続けるなら、これまでの物理学や哲学で難問だった「時間の順序、すなわち時間が流れる向き」がどのようにして生じるのか、という問題に独自の答えを与えたこと」と記述する。素人にはさらにわかりやすい説明である。
書評
時間はいつでもどこでも同じように経過するわけではなく、過去から未来へと流れるわけでもない―。“ホーキングの再来”と評される天才物理学者が、本書の前半で「物理学的に時間は存在しない」という驚くべき考察を展開する。後半では、それにもかかわらず私たちはなぜ時間が存在するように感じるのかを、哲学や脳科学などの知見を援用して論じる。詩情あふれる筆致で時間の本質を明らかにする、独創的かつエレガントな科学エッセイ。『世の中ががらりと変わって見える物理の本』(同)は世界で100万部超を売り上げ、大反響を呼んだ。『時間は存在しない』はイタリアで18万部発行、35か国で刊行決定の世界的ベストセラー。タイム誌の「ベスト10ノンフィクション(2018年)」にも選ばれている
書評1
時間についての 哲学的考察が熱い。先日の「脳と時間」に続いて、「時間は存在しない」を読む。超弦理論と並んで有力視されている量子重力理論のループ量子重力理論の第一人者カルロ・ロヴェッリ。
刺激的なタイトルに聞こえるかもしれないが、二十世紀を通して古典物理学的な「一方向に不可逆的に、一定のペースで、宇宙のどこでも共通である」ような時間の概念というものは、アインシュタインの相対性理論と量子力学によって否定されてきた。相対性理論が描くのはその名の通り速度と重力の干渉によって時間の流れは伸び縮みするゴムのような時空で、量子力学が示す宇宙においては大事なのは相互作用であって因果関係ではない。特に筆者が研究するループ量子重力理論においては、時空はスピンネットワークと呼ばれるネットワークの相互作用の結果としての生じるとされる。本書の1/3はこのような古典的・直感的な時間観の解体にあてられている。
本書が興味深いのは、それなのになぜ私たちはこれほど強く時間が流れているという感覚を持つのか、という疑問に対しての、物理学の枠を超えての考察だ。著者はその答えを、私達人間の存在と、その存在を支える宇宙の部分に求める。物理学の概念の中で、不可逆的な時間の流れを発生させるほぼ唯一の原理は、熱力学第二法則、いわゆるエントロピーの法則である。素粒子のスケールには存在しない不可逆なエントロピーの増大が、私達の知覚がとらえるマクロスケールの世界では発生する。一方で、私達の世界は地球の時点と太陽の周りの公転、月の公転による周期的なリズムによって変化している。太陽は地球にエネルギーを供給し、月は重力を変化させる。人間を含む生命は、このような世界との相互作用の中で、記憶を通じて、一定の周期でかつ一定の方向へと流れる時間を獲得してきた、というのが筆者の主張だ。
筆者は、自らの宇宙観をアリストテレスやアウグスティヌスのようなギリシャ・ローマの哲学者、またインドの古代仏教などの東洋哲学も引用しながら描き出す。実際、ループ量子重力理論の世界観は、仏教の縁起や空、諸行無常の概念と驚くほど近い。
「脳と時間」の感想にも書いた通り、僕はこの考え方が正しいと思っている。私たちが感じる時間は、宇宙に普遍の原理ではなく、人間が相互作用できる世界との間に生じさせているアフォーダンスなのだ。
僕はこれには重大な意味があると思う。二十世紀の人間はエネルギーの制御によって空間の制約を乗り越えることを可能にした。二十一世紀の人類は、エントロピーすなわち情報を制御することで、時間の制約を乗り越えることに向かっているのかもしれないと夢想させられる。
書評2
評者はこの邦訳ではなく英語版(Rovelli, The Order of Time)を読んで書評を書いた(星5つ)。それを読んでもらえばわかる通り、この本のもっとも重要なメッセージは、「時間が存在しない」ことではなく、「もっとも基本的な方程式には含まれなかった時間が、われわれが経験し、実験し、理論と経験とを突き合わせるレベルでは、なぜ、どのようにして生じるのか」ということ。さらに続けるなら、これまでの物理学や哲学で難問だった「時間の順序、すなわち時間が流れる向き」がどのようにして生じるのか、という問題に独自の答えを与えたこと。それゆえ、英語版(およびもとのイタリア語版)のタイトルは、「時間の順序」となっているのである。したがって、邦訳のタイトルは、予備知識のない読者に、最初から妙な先入見を与えてしまう恐れが大。最後まで読まなければ、ロヴェッリの答えはわからないのでご注意!
邦訳にも目を通したが、タイトルを見ただけで星3つ以上は与えられない。「時間は存在しない」というだけなら、ロヴェッリ以外にもたくさんの論者がいて、それぞれの立論を行っている。「時間が存在しないなんて当たり前」とか「しかじかの事例で時間が存在しないないて言えますか?」という、的外れな書評を書くような方々は、文字を読んでも意味を理解してない、としか言いようがない。その責任の一端は、邦訳タイトルにある!
書評④
「ループ量子重力論」を提唱するイタリア人理論物理学者カルロ・ロヴェッリの書いた啓蒙書。
「量子重力の基本方程式は時間変数を含まず、変動する量の間のあり得る関係を指し示すことでこの世界を記述する。」だから時間は存在しない。
「ループ量子重力論は、ものごとが互いに対してどう変化するか、この世界の事柄が互いの関係においてどのよう生じるかを記述する。(ニュートンの微分方程式のように)時間の進行に対してものごとが展開する様子を記述するものではない。」
「世界は”もの”でできているのではなく、”こと”ででできている。世界は相互に連結された出来事のネットである。そこに登場する変数は確率的な規則に忠実に従う。」
「空間の量子は空間的に近いという関係によって結び合わさり、スピンネットワークと呼ばれるネットになる。そしてこれらのネットは離散的なジャンプによって互いに転換し合う。」
がまず言いたいこと。
その後、その内容をもっと掘り下げた議論が展開されるかと思いきや、そうではなく、ではなぜ人間は時間を認識するのかの説明に紙幅が費やされる。
それは、「人間が一様で順序付けられた普遍的な時間について語る仕組みを持っているから」で、その仕組みは1)我々の持っている特殊な視点では、エントロピーの増大を頼りとして時間の流れを認識するから(時間の方向性は視点がもたらす)。2)人間の脳は過去の記憶を集め、それを使って絶えず未来を予測しようとする仕組みを持っているから。
だという。
要するに、ループ量子重力理論の示す世界観を人間はそのまま認識できるわけではないという事
関連記事
-

-
太平洋戦争で日本が使用した総費用がQuoraにでていた
太平洋戦争で、日本が使った総費用はいくらでしょうか?Matsuoka Daichi, 九州大学で経
-

-
ドナルド・トランプが大統領になる5つの理由を教えよう
https://www.huffingtonpost.jp/michael-moore/5-rea
-

-
井伏鱒二著『駅前旅館』
新潮文庫の『駅前旅館』を読み、映画をDVDで見た。世相はDVDの方がわかりやすいが、字句「観光」は
-
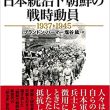
-
コロニアル・ツーリズム序説 永淵康之著『バリ島』 ブランドン・パーマー著『日本統治下朝鮮の戦時動員』
「植民地観光」というタイトルでは、歴史認識で揺れる東アジアでは冷静な論述ができないので、とりあえずコ
-

-
脳科学 ファントムペイン
四肢の切断した部分に痛みを感じる、いわゆる幻肢痛(ファントムペイン)は、脳から送った信号に失った
-
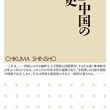
-
平野聡『「反日」中国の文明史 (ちくま新書) 』を読んで
平野聡『「反日」中国の文明史 (ちくま新書) 』に関するAmazonの紹介文は、「中国は雄大なロ
-

-
『平成経済衰退の本質』金子勝 情報、金、モノ、ヒト、自然 について、グローバリゼーションのスピードが違うことを指摘 情報と人流のずれが、過剰観光
いつも感じることであるが、自分も含め観光学研究の同業者は、研究原理を持ち合わせていないということ
-

-
デジタル化と人流・観光(1)
通信の秘密が大日本帝国憲法及び日本国憲法に規定されていることもあり、長らく電気通信事業は逓信省、運
-

-
2002年『言語の脳科学』酒井邦嘉著 東大教養学部の講義(認知脳科学概論)をもとにした本 生成文法( generative grammar)
メモ p.135「最近の言語学の入門書は、最後の一章に脳科学との関連性が解説されている」私の観光教
-
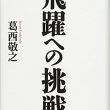
-
『飛躍への挑戦』葛西敬之著
図書館で取り寄せて読んだ。国鉄改革については、多くの公表著作物に加え、これからオーラルヒストリが世

