書評『日本社会の仕組み』小熊英二
【本書の構成】
第1章 日本社会の「3つの生き方」
第2章 日本の働き方、世界の働き方
第3章 歴史のはたらき
第4章 「日本型雇用」の起源
第5章 慣行の形成
第6章 民主化と「社員の平等」
第7章 高度成長と「学歴」
第8章 「一億総中流」から「新たな二重構造」へ
終章 「社会のしくみ」と「正義」のありか
書評1
雇用の歴史社会学から見た「日本社会のしくみ」を論じた分厚い新書本。小熊英二久々のヒット作と思う。いや、ヒット作というとちょっと褒めたりない。だが、ホームランは褒めすぎだろう。三塁打が妥当ではないかと思う。
私的感想
以下、本書が三塁打である理由を述べる。
〇本書はまず日本の生き方の類型として、「大企業型」、「地元型」、「残余型」の三類型を設定する。これは本書の大前提のようだが、なかなか分かりにくい。著者は第一章で、この三類型で日本社会の全体像を把握しようとするが、あんまり面白くない。
〇だが、第二章以後では、日本「社会のしくみ」(慣習の束)を解明するために、雇用の歴史の検証に向かう。これは面白い。ラッキーだったのは、著者が当初、雇用、教育、社会保障、政党、税制等全面展開するつもりでいた(そんなものを全面展開されては、新書読者としてはたまったものではない)のが、途中で「雇用」以外は実質的に切り捨てて、「日本型雇用慣習の歴史」に焦点を絞って、書き直したことである。たぶん、これで本書の視野はぐっとよくなり、内容も引き締まって、論理も理解しやすくなったと思う。
〇そもそも、多くの日本人にとっては、教育も、社会保障も、政党も、ちょっと離れたところにあるものだが、雇用はきわめて身近にあって、ほぼ一生つきまとい、その人の人生を決めてしまうものである。
〇第二章では、日本人の働き方(というよりは働かせ方、雇用)の特色を西洋と比較して検討する。日本ではまず人を雇い、それに職務をあてがう。西洋ではまず職務があって、それに即した人を雇う。日本式は定期人事異動や新卒一括採用と結びつく。日本では採用の基準は学歴、人格等で、専門的な職務能力は要求されない。
〇第三章では、欧米の雇用慣行の歴史を検討。欧州では産業別組合が発達し、企業を横断する人材移動が実現している。アメリカでは、職務の概念が広まり、労働運動等により、「職務の平等」の慣習が獲得された。日本の雇用慣行の特色は、企業横断的なルールのないことであり、日本の雇用慣行の歴史の特色は、長期雇用や安定した賃金を、「職務の平等」ではなく、「社員の平等」という形で実現しようとしたことにあるとする。
〇第四章以後は、いよいよ「日本型雇用」の歴史に入り、第四章、第五章は明治から戦前、第六章は戦後、第七章は高度成長までを豊富な史料を提示して論じていく。たいへんに面白いが、レビューが長くなったので、細部は略。485頁から引用「一九六〇年代に、一連の雇用の特徴が定着した。それは明治期いらいの慣行が、総力戦と民主化、労働運動と高学歴化などの作用によって、三層構造をこえて拡張することによって成立したのである」。
〇第八章は1973年の石油ショック以後の変化について論じ、終章に繋がっていく。
〇全体として、本書のよい点をあげると、一つは、脱線したり、余談に走ったりすることなく、ひたすらテーマに関連する事実とその解釈を述べていることである。もう一つは、読者に質問を投げかけたりせずに、読者への講義に専念していることである。(最後の最後に読者への質問がでるが、これは例外)。これらの結果、本書は直球勝負のスピードの心地よい本となっている。
〇終章の563頁から567頁までの「戦後日本の社会契約」はちょっと感動的である。著者は先人の努力に相当の敬意を払っている。
私的結論
書評2
わたしは元教員で退職して自営業をしている者です。よく調べて書かれた本ですが、基本が文献からの取材の形を取っています。談話もよく拾っていますが、文献に基づいた方法の限界を感じます。
世界的に教員の修士化が進み、相対的に日本では教師の学歴が下がっていると指摘してあります。それは事実です。(実は日本は1000万人以上の人口の国では世界で初めて普通教育の教員資格を学士にした国です)
しかし、日本の学校はオン・ザ・ジョブ・トレーニングの世界です。その上、日本には外国に例を見ない高度な民間研究団体の歴史があります。ただ、以前は旧文部省が民間教育団体を目の敵にしたため、日本の教育制度の表側には出てこなかったのです。関係者以外には知られなくとも、実は隠れた形で広く行われ日本の教育の背骨を支えてきました。だから、現場に強い関心を持たなければ文献主義の方法では表には出てきません。大学院に進学しなくても決して教員は自ら高いレベルのトレーニングをしていないわけではなかったのです。
教師にとって高学歴化の意味を問わずに、高学歴化だけを指標にする評価はどんなものでしょうか。現実に高学歴化した教員が民間研究団体の成果以上のものを生んでいるとも思えません。問題は学歴ではなく学ばないオトナなのです。現状での解決策は高学歴化より先に雇っている側が学ぶ余裕を与えることです。高学歴化はその中の方法の一つにすぎません。
教員の例だけでもこの通りです。現在起こっていることへの対策のための「暗黙のルールの解明」には、確かに過去のことは文献を使うしかありません。しかし、まだ、可能な分については調査(インタビュー)の積み重ねの方が解明の近道だと考えます。
書評3
1958年にアベグレンが著していた『日本の経営』の影響のもとに1972年には『OECD対日労働報告書』が発表され、日本的経営の特徴は、「終身雇用」「年功序列」「企業内組合」の3点であるとする理解が一般的となった。著者は日本的経営という言葉は使わず、「日本型雇用」を使うが、この日本型雇用がいまだに維持されているとするのが、本書の第一の主張である。そして、これが足かせになって日本の現状は変わらないのだと訴えているのだろう。
1963年、この日本の現状を変えるために出された経済審議会の報告書『経済発展における人的能力開発の課題と対策』には、職務分析で標準化された職務給の導入などで可能となる横断的労働市場の形成や、児童手当などの社会保障制度の充実が訴えられていた(p.412)。しかし、経営者や民衆は賛同を示さず(p.414)、絵にかいた餅にしかならなかった(p.579)。この歴史的事実から著者の歯切れは悪くなる。さらに、「本書は政策提言書ではない。p.572」と逃げを打たれてしまう。「日本型雇用の延命措置にすぎず、筆者としては賛成できない。p.575」とあるのだから、学者として自説をもっと明確に主張すべきだ。
そもそも日本型雇用はどのような経緯で生まれたのか、本書には隅谷三喜男先生の引用がほとんどない。長くなるが先生の説を引用したい。(『隅谷三喜男著作集』岩波書店)
隅谷は、与えられた社会的条件の中で日本社会と日本企業が生み出した、独自の歴史的対応として日本的経営を分析している。隅谷によれば、経営家族主義が姿を現すのは、明治の末、日露戦争(1904-1905)後、独占資本が形成されるようになって以後のことである。それ以前は、現場の労働力は親方によって統治されていたが、日露戦争後は、技術革新を契機に企業が直接管理する工場制企業が発展しつつあった。これは労働者の不満につながるものであったが、それでも雇主と労働者の間に立って、事実上労働者を統括した親方職人が、両者の間の潤滑油的存在であり得たかぎりは、問題は重大化しなかった。しかし、親方が廃され企業の直接管理に移行したこの時期に、労働者の不満は爆発し、全国の主要な工場・鉱山に争議暴動が発生している。呉工廠(1906年8月)や大阪砲兵工廠(1906年12月)などは憲兵・警官が出動し、足尾銅山(1907年2月)・別子銅山(1907年6月)などは全山火の海と化し、軍隊の出動に至っている。これらの流れは、企業において労使関係の安定化を緊急の課題とさせていく。つまり、経営家族主義は、労使関係の安定を目標に、共済制度を中心とする福利施設の創設を基盤として、この頃スタートしたのである。やがて年功制と終身雇用を柱とする経営家族主義は、昭和初年(1926年頃)、退職金制度の確立によって一応の完成をみる。―以上―、隅谷は経営家族主義という言葉を使うが、日本型雇用と同じと解釈した。
アメリカ労働総同盟(AFL)の会長ゴンパースの影響を強く受けて1896年(明治29年)に帰国した高野房太郎らの努力で、生活扶助つまり共済活動に力を入れた職業別組合が成立している。この共済制度は職業別組合が先に提供していたが、その後、企業も共済制度に力を入れ、年々増加させる。それは福利施設の設定拡充と、それを基盤とする労働者定着政策であった。労働組合が担う可能性があった制度を企業がとり込むことで、労働者福祉の主導権を企業が握ることになった。
コストのかかる共済制度を、なぜ企業が取り込んだのか。それほど労使関係の安定が喫緊の課題だったのだ。労使関係の一方の当事者である日経連は、2002年5月に経団連と統合して日本経済団体連合会となって消滅した。現在は、労働力はコストとなり、足かせとなったのだ。そのように労働者は処遇されても、日本型雇用を生むきっかけとなった労働者の爆発は起こりそうにもない。
本書の最後に想定問題が提示され、その回答例が3つ用意されている。ネタバレになるのでひとつだけ紹介する。
回答①
賃金は労働者の生活を支えるものである以上、年齢や家族背景を考慮すべきだ。だから、女子高校生と同じ賃金なのはおかしい。このシングルマザーのような人すべてが正社員になれる社会、年齢と家族数にみあった賃金を得られる社会にしていくべきだ。
私はこの回答①を選んだ。筆者は回答③を選んでいる(本書をご覧ください)。
賃金論からいえば、この回答は生活給であるし、年齢・年功給である。日本型雇用の長期雇用は、現実には長いといえるものではないので(p.201)、長期雇用の条件をはずすとすると、この回答は日本型雇用ということになる。
日本型雇用は正規・非正規の区別がもともとあった。しかし、この区別をなくせというのが現状の正論ではないか。そして、「カイシャp.584」という縦社会の構造を破壊することが難しいならば、あえて破壊することなく、ここから福祉を供給する。特に最大の福祉である賃金を供給する。その賃金はベーシックインカム的に政府が賃金の補助として、家族構成に見合った人数分が供給されるとしたらどうだろう。
ベーシックインカムの不安は、働かなくても生活費をもらえるなら誰も働かなくなるだろうというものだが、企業が供給するのだから、名目的には働いていることになる。おそらく、ベーシックインカムは人間の存在権に与えられるものだとする理念に反すると非難されるだろうが。日本型雇用は企業内のベーシックインカムに似ていると思いついたので、回答①を選んだ。回答①はベーシックインカムに近いといえないだろうか。
以上、本書の最後に「あなた自身にとっての、本書の結論を作っていっていただきたい。」とあるので、作ってみた。本書の内容はさほど新奇なものは見当たらないが、あらためて日本社会の現状を考えさせてくれた。
書評3
自分は木工関係の自営業者である。政治や経済、社会の仕組みには興味はあるが、専門家ではない。その自分の目からは、大いに得るところのある一冊であった。
著者もあとがきに書くように、本書は、日本社会の特質を、分野横断的、かつ歴史を追って書こうとした試みであり、そのポイントを「雇用」に絞ることで、どうにかこのボリュームに収まった、という面がある。他のレビューアのように、この本に社会を正す「回答」を求めることは、「お門違い」かと思うのである。
同時に、「日本社会の3つの生き方=大企業型・地元型・残余型」という類型にも、自営業者としてやや腑に落ちない感じがする(真っ向から否定するということではない)など、著者の問題提起が、社会をきっちり解き明かすというようなパワーを感じない、もどかしさも否めないのだ。
どなたかが書いた「三塁打」という表現に納得するものである。
本書の特長は、膨大な文献資料と他国との比較で、「新卒一括採用・長期雇用・定期人事異動・定年制」など「一流の就職先」である官公庁や大企業の雇用システムの「起源と利点と欠点」を明らかにしたことだろう。
また、「上級職員・下級職員・現場労働者の三層構造」「課ごとの大部屋システム」や「学歴社会であるがゆえに、相対的な低学歴化が進んでいる」とか「団塊ジュニアが『ロストジェネレーション』にならざるを得なかった仕組み」「社員という呼称、社員の平等が職務の平等とは相容れないこと」「学歴から賃金や社会保障までつながる二重構造」など、誰かを悪者にするのではなく、日本社会の「仕組み」が生み出したものであることを、客観的に説明しているのも素晴らしい。
政治の根源は、安全保障や外交、まして権力争いなどではなく、広義の「経済」だと思っている。世界に利便性や美しさや富を提供することで、自らもそれを享受できる、というシンプルなことを、いかに効率的に分担できるか。
ここには、行き詰まりを正すヒントがちりばめられている。
この本に書かれた程度の知識見識が中央官僚や国会議員にあれば、もっと元気な、もっと美しい、もっと世界に貢献する日本へと変わることもできようものを、と思うのである。
関連記事
-

-
Quora ヒトラーはなぜ、ホロコーストを行ったのですか?
https://jp.quora.com/%E3%83%92%E3%83%88%E3%83%A9
-
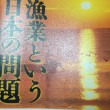
-
『漁業という日本の問題』勝川俊雄 日本人は思ったほど魚を食べてない。伝統の和食イメージも変化
マスコミによってつくられた常識は、一度は疑ってかかる必要があるということを感じていますが、「日本人は
-

-
「脳コンピューター・インターフェイスの実用化には何が必要か」要点
https://www.technologyreview.jp/s/62158/for-brain-
-
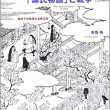
-
『「源氏物語」と戦争』有働裕 教科書に採用されたのは意外に遅く、1938年。なぜ戦争に向かうこの時期に、退廃的とも言える源氏物語が教科書に採用されたのか
アマゾン書評 源氏物語といえば、枕草子と並んで国語教科書に必ず登場する古典である。
-

-
Quora Covid-19の死亡者はアメリカが27.9万人、日本が2210人 (12/06現在) です。日本では医療崩壊の危険が差し迫っているとの報道がありますが、アメリカに比べて医療体制が貧弱なのでしょうか?
12月16日現在、アメリカでの死亡者数は約30万4千人、そして日本での死亡者数は2600名足らずで
-

-
人流・観光学概論修正原稿資料
◎コロナ等危機管理関係 19世紀の貧困に直面した時、自由主義経済学者は「氷のように
-

-
渋滞学『公研』2019年4月 メモ
渋滞学 西成活裕 渋滞とは? 結局人の動き 法則性はあるのか? 空気や水と違って人間にはそれぞれ
-
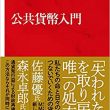
-
『公共貨幣論入門』山口薫、山口陽恵
MMT論の天敵 Amazonの書評(注 少し難解だが、言わんとするところは読み取れ

