書評『シュリューマン旅行記 清国・日本』石井和子訳
公開日:
:
最終更新日:2023/05/29
出版・講義資料
日本人の簡素な和式の生活への洞察力は、ベルツと同じ。宗教観は、シュリューマンとは逆に伊藤博文等が、西洋人は本気で神がいるとおもっていることに驚くとともに、神に代わるものとして天皇制を考えていることが面白い。
『シュリューマン旅行記 清国・日本』石井和子訳 シュリューマンは1865年世界漫遊の旅に出かけ日本に寄港している(6月1日から7月4日)。66年にパリに落ち着いて改めて考古学を学び学位を取得し、1871年にトロイ遺跡を発掘しているから、発掘前に日本に来たことになるのは驚きである。尊王攘夷、今流にいえばテロリストがうろうろしている江戸に、外交官でも軍人でもない民間人が手づるを得て来ているのである。以下訳文の抜粋と感想「上海から東洋蒸気船会社所属の北京号に乗り、日本の横浜に向かった。立った三日足らずの行程に百両も支払わなければならなかった」と相場を教えてくれている。「日本の小舟には色が塗ってない。シナ人なら忘れることのできない、船首の二つ目玉が、日本の小舟にはない」、荷揚場で「ひどい疥癬に罹っていて・・・皮膚病に冒されていない者を探したが、だれもいなかった」と観察する。「官吏二人にそれぞれ一分ずつ出した。ところがなんと彼らは自分の胸をたたいて「ニッポンムスコ」といい、これを拒んだ」と現代旅人でも悩まされる入国時の役人を描写し、感心するが、滞在後には幕府の貨幣交換政策について、通商の不利益も顧みず莫大な利益を高官に与えていると批判している。この点もどこか現代に通じる。家庭生活の観察は面白い。正座して椀と箸での食事後、瞬く間に食事の名残が消えてしまうさまを描写する。欧州で必要不可欠だとみなしていた衣装ダンス、書斎机、食器棚などちっとも必要でないことに気が付いた。欧州の親たちが日本の習慣を取りいれて子供たちの結婚準備から解放されたらと記述する。長年健康にわるい正座がなぜ日本の習慣になったのかと不思議に思っていたが、少し合点がいった。日本の政治は、騎士制度を欠いた封建体制であり、ベネチア貴族の寡頭政治である記述。民衆の生活の中に真の宗教心は浸透しておらず、また上流階級はむしろ懐疑的であると確信したとも記述する。芝居見物もしている。劇場はほぼ男女同数。男女混浴どころか、みだらな場面をあらゆる年齢層の女たちが楽しむような生活のなかに、どうしてあのような純粋で敬虔な気持ちが存在し得るのか不思議とするが、この点は、欧州でも人は変わらないのではと思い同意できない。巻末に日本文明論が展開され、日本は欧州以上に文明化されているとする。男女とも皆かなと漢字の読み書きができる。しかし、キリスト教徒が理解しているような意味は文明化されていないとする。その理由は民衆社会を抑圧する密告社会があるからだとする。外国人嫌いにするのは大名で、幕府には外国人を守る力がないから、外国人の生命財産は外国部隊にしか守れないことになる。しかし、軍隊派遣は採算が合わないと結んでいる。ビジネスマンシュリューマンの結論である。
関連記事
-

-
『ミルクと日本人』武田尚子著
「こんな強烈な匂いと味なのに、お茶に入れて飲むなんて!」牛乳を飲む英国人を見た日本人の言葉である。
-

-
『1964 東京ブラックホール』貴志謙介
前回の東京五輪の世相を描いた本書を港区図書館で借りて読む。今回のコロナと五輪の関係が薄らぼんやりと
-

-
国際観光局ができた1930年代の状勢 『戦前日本の「グローバリズム」』
大東亜共栄圏の虚構を指摘 「バダヴィアに派遣された小林一三商相」国内世論の啓発に努める小林は
-

-
Quora Covid-19の死亡者はアメリカが27.9万人、日本が2210人 (12/06現在) です。日本では医療崩壊の危険が差し迫っているとの報道がありますが、アメリカに比べて医療体制が貧弱なのでしょうか?
12月16日現在、アメリカでの死亡者数は約30万4千人、そして日本での死亡者数は2600名足らずで
-

-
2022年8月ジャパンナウ観光情報協会原稿 アフターコロナという名の観光論 原稿資料
◎ジャパンナウ原稿案 2020年冬から始まった新型感染症は日本の人流・観光業界に
-

-
QUORAにみる観光資源 なぜ、現代に、クラシックの大作曲家が輩出されないのですか?大昔の作曲家のみで、例えば1960年生まれの大作曲家なんていません。なぜでしょうか?
とっくの昔に旬を過ぎている質問と思われますが、面白そうなので回答します。 一般的に思われてい
-

-
『兵士のアイドル』押田信子著 盧溝橋事件勃発で、新聞の報道合戦開始 慰問団ブーム
陸軍恤兵(ジュッペイ)部 日清戦争時に少なくともそのたぐいの組織はできていた?
-

-
The best passports to hold in 2021 are: 1. Japan (193 destinations)
https://www.passportindex.org/comparebyPassport.p
-
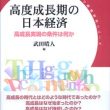
-
『高度経済成長期の日本経済』武田晴人編 有斐閣 訪日外客数の急増の分析に参考
キーワード 繰延需要の発現(家計ストック水準の回復) 家電モデル(世帯数の増加)自動車(見せびら
-
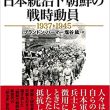
-
コロニアル・ツーリズム序説 永淵康之著『バリ島』 ブランドン・パーマー著『日本統治下朝鮮の戦時動員』
「植民地観光」というタイトルでは、歴史認識で揺れる東アジアでは冷静な論述ができないので、とりあえずコ
- PREV
- 書評『ベルツの日記』
- NEXT
- 書評『日本社会の仕組み』小熊英二


