書評 AIの言語理解について考える」川添愛 学士会報940号P.42
分類がわかりやすい
1 今のAIは人間の言葉を理解している。
理解しているようにみえることを重視する点でチューリングテストと同じ。この理屈を認めない場合には、自分以外のすべての人間の知性も認められないという独我論に陥る
2 今のAIは人間の言葉を理解していない
2-1 AIはいずれ人間の言葉を理解できるようになる
2-1-1「今の技術(機械学習)」の延長線上でAIはいずれ人間の言葉を理解できるようになる可能性がある
A AIの仕組みと人間の言語理解のメカニズムとの近さを考慮する必要はない 基本的には1と同じで、現状のAIのパフォーマンスを十分と考えるか否かの違い
B 近さを考慮する必要がある 人間の言語能力も機械学習に似たメカニズムで実現されていると考える。後天的に与えられた有限のデータから帰納的に学修されるという、いわゆる経験主義の立場
2-1-2 今の後述の延長線上では無理だが、何らかの技術革新があればAIはいずれ、人間の言葉を理解できるようになる
A 機械学習のアプローチでは、いずれAIの制度が頭打ちになると予測し、新しい技術が必要だろうと考える人たち
B 機械学習だけでは人間の言語能力には近づくことはできないと考える。チョムスキーの普遍文法が例。人間の脳に言語能力を獲得するための「先天的な作りこみ」があるとする合理主義
2-2 AIは決して人間の言葉を理解することはできない
A 言葉の理解に霊魂のようなものがかかわっていると思う人は、機械であるaiは永遠に言語は理解できなと考える(ただし機械にも霊魂が宿ると考える場合は別)
B 人間の言語能力が人体の物理的・機械的な側面によって生じると考える人が、2-2のように主張することも不可能ではない。機械の知性も内側からは観察できないから認めないとする1と同じ立場が考えられる。独我論に陥らないためには、他人に知性があるとする判断の前提を、他人が自分と同じ身体を持つことに置くという方法である。同じ体を持たない機械には知性の存在を認めないとすることは可能である。ただし、機械が人間と同じ身体を持つことを不可能と考えるか、またどのような条件が成り立てば機械が人間と同じ身体を持つといえると考えるかによってさらに立場が変わる可能性がある
関連記事
-

-
QUARA コロナ対処にあたってWHO非難の理由にWHOの渡航制限反対が挙げられていますが、これをどう思いますか?
渡航制限反対は主に「中国寄りだから」という文脈で語られています。しかし調べてみれば、今回のコロナウ
-
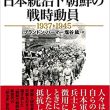
-
コロニアル・ツーリズム序説 永淵康之著『バリ島』 ブランドン・パーマー著『日本統治下朝鮮の戦時動員』
「植民地観光」というタイトルでは、歴史認識で揺れる東アジアでは冷静な論述ができないので、とりあえずコ
-

-
ネット右翼を構成する者 メディアが報じるような「若者の保守化」現象は見られない
樋口直人は『日本型排外主義』の中で、大部分は正規雇用の大卒ホワイトカラーであるとし、古谷経衡も「ネ
-

-
岩波書店の丁稚奉公ストライキ
『教科書には載っていない戦前の日本』p.222 封建的な雇用制度の改善を求めて岩波書店側に突
-
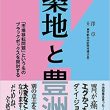
-
『築地と豊洲』澤章 都政新報社
Amazonの紹介では「平成が終わろうとしていたあの頃、東京のみならず日本中を巻き込んだ築地市場の
-

-
『逆説の日本経済論』貿易決済のための為替取引量は、今や東京為替市場で見れば、その取引量の8分の1程度に落ちている。それ以外は資本取引
貿易決済のための為替取引量は、今や東京為替市場で見れば、その取引量の8分の1程度に落ちている。それ以
-

-
MaaSに欠けている発想「災害時のロジステックスを考える」対談 西成活裕・有馬朱美 公研2019.6
公研で珍しく物流を取り上げている。p.42では「自動車メーカーは自社の車がどこを走っているかという
-

-
『庶民と旅の歴史』新城常三著
新城 常三(1911年4月21日- 1996年8月6日)は、日本の歴史学者。交通史を専門とした。1
-

-
2016年3月8日錯覚研究会
錯覚研究会におよびいただき、観光の話をさせていただいた。発表資料はHPの講演資料集に掲載してある。h
-

-
中山智香子『経済学の堕落を撃つ』
経済学は、なぜ人間の生から乖離し、人間の幸福にはまったく役立たなくなってしまったのか? 経済学の

