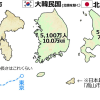『プロヴァンスの村の終焉』上・下 ジャン=ピエール・ルゴフ著 2017年10月15日
市長時代にピーターメイルの「プロヴァンスの12か月」読み、観光地づくりの参考にしたいと孫を連れて南仏旅行をしたことがある。BBCがTVドラマ化し、NHKでも放送されて話題を呼んだ、世界的ベストセラーである。1989年度イギリス紀行文学賞受賞作品でもあったからだ。
12か月は無理だが、著名な文化人12人に1か月ずつ加賀に居住してもらい「加賀の12か月」を著してもらいたいと思ったからである。結果的には市長選挙時に、その時行われた参議院選挙中に外遊していたとネガティヴキャンペンの材料に使われ、配布された文書では「観光学者が実験材料にしている」と批判されただけであったが、本書を読んであらためて今日のインバウンドの上滑りなメディアの風潮にも疑問を感じ、反省したところである。残念ながらネガティヴキャンペーンの効果通り地元の人ははやり優雅に外遊(古い言葉だが)していたと思った人の方が多かったのであった。
日本人にとってだけでなく、フランス人やヨーロッパ人にとってもプロヴァンスというと、風光明媚で、プロヴァンスイェローの壁の小さな家が点在するのんびりした「ユートピア」のようなイメージがあるらしい。その流れをプロヴァンスの12か月は作った。2000年代にはTGVが完成し、パリとエクサンプロヴァンスが3時間で結ばれた。この新たな交通様式は地価と家賃の上昇を誘発した。あまりの道路交通量に、パリとプロヴァンスを結ぶ技術の粋を凝らしたミヨー高架橋が完成したが、それがまた観光資源となっている。技術の話はナショナルジオグラッフィクでも放映されていた。瀬戸内海と瀬戸大橋のような関係になっているのであろう。プロヴァンスは3400万人の観光客を毎年受入その数は住民の8倍にも及んでいる。規模は小さいが北陸新幹線が金沢まで暫定開業し、大いに観光客で潤っている姿とダブってくる。日本中が期待している姿でもある。
さて、2012年度プロヴァンス歴史書大賞を受賞した『プロヴァンスの村の終焉』は、Amazonの広告では「プロヴァンスの伝統的な小村が直面する、現代化と共同体の危機。青い空とのんきな人々によって彩られた南仏プロヴァンスの悠久の生活芸術は、いまや生活の近代化・多様化、さまざまな人の出入りによって急激な変容を余儀なくされている。著者の30年にもわたる現地調査と、村の人々との交流を通して見えてきた「温和な太陽の楽園」の素顔と陰影を、文化、風俗、産業、建築、商業、宗教、教育などといった多種多様な視点から総合的に描き出した意欲作」と紹介されている。全総流に簡単に言えば「都市と農村の均衡ある発展」問題のフランス版である。
プロヴァンスが1970年代と80年代にどのように変貌したかを単なる風景の変貌ではなく、村人の生活を根底から揺るがす新住民との軋轢を描いている。ルゴフは一つの典型的なカドネという村に住み着き村人と親交を重ねながら、彼らの本音と建前、ゆずれない信条などをひろいあげて書き記したドキュメンタリーである。
序文で「永遠のプロヴァンス?」として、「地元の年配者は観光客や裕福な新規住民のために作られた劇場の装飾物の管理人として生きている。あるいはもっと悪いことに「消えつつある人種」として日々暮らしている」と記述している。
村落共同体に大変化を生じさせたのは、テレビ(インターネット、スマホではない)と自動車であった。このことは日本もフランスも同じである。この二つの耐久消費財の登場は当時の新時代の幕あきとなった。そしてレジャー時代が始まり、村の伝統的な社会関係は分断され、村は外部世界に大きく開かれれこととなった。テレビは家に閉じこもる生活スタイルへと変化させた。自動車はといえば、住人達の特権的な交流の場であった通りや広場を車が占領し、村そのものを征服してしまった。決定的な変化はもちろん、村のアイデンティティを形成していた伝統的な産業が終焉を迎えたことである。それとともに人口減少が加速した。
70年代以降続々と新たな人間が押し寄せて来た。しかし、更に時間を経るにつれて、田舎に暮らすだけの都会人が増加することで、もはや村落共同体は意味を成さず都会的な個人主義が当然のこととなり、田舎風の郊外都市となって行くにつれて、大多数の住民のメンタリティは、かつての籠細工師や農民のメンタリティとは似ても似つかぬ者となって行く。そして、私たちが行く知るプロヴァンスの田舎風、きれいな風景の擬似村が出来上がった。
村の教育についての著者の詳細な記述を紹介する。「都会からの新村人は都会へ働きに出るため村に子供の教育もしつけもすべて公的にすべきと考えている。その結果、学校教育では昔であれば家庭でしつけられた目上の人を敬う事、敬語を使う事すら学校教育現場に持ち込まれる。あるいは、村の公民教育として試みられた「ジュニア村議会」は熱心な指導者によって、子供たちによる選挙とジュニア村議会」の現実の運営が行なわれた。そこから出てきた色々な村の課題が、本物の村議会のものとほぼ同じであったという。しかし、このジュニア村議会の議決は程なく興味をもたれなくなった。それは村がその問題に何一つ応じなかったからだという。身につまされる問題だ。公民を教えるために、子供たち自らが村の現実にコミットしても、大人の都合でねじ曲げられる行為から、子供たちが学んだのはむしろ大人の欺瞞だろう。」
「やがてカドネの村は宅地開発の波に飲み込まれる。土地を売り大金を手にする者や、古い家を売る者、それらの土地や家をレジャー施設にする経営者が出現する。一方では貧困や仕事がないだけでなく、家庭崩壊や帰属する場所や連帯感の喪失によっていわば全てが崩れて行く「瓦解」が始まる。しかし、プロヴァンスの伝統の終焉は、その責任を「都会の人間たち」の到来のみにおわせることはできない。プロヴァンス人たちの習慣と生活様式、そして彼ら自身もまた変わってしまったのだから。」
私は大学で都市と農村について講義をするときに、学生に「農村」とは何かと問いかけることから始める。「農業は定義ができる、農地も定義ができる、では農村は?」と聞くのである。院生の論文にも無批判に農村という字句が使われるのだから、学生には無理なのであろう。未だに正解が返ってこない。日本には正解がないからである。農業を共同体として行う地域がなくなったのである。日本はすべて都市(非農村)なのである。まだ港区の商店街の方が農村社会が残っているかもしれないくらいである。
その「農村」に観光客が何を求めて来訪するのであろう。私は20世紀末に全国の鉄道、空港を回ったが、どこへ行っても同じだと思った。均衡ある発展を成し遂げたのであり、何が不満なのであろうと思った。観光は他の地域の人たちが来てくれることである。地域の誇りになるという思想で観光立国推進基本法はできている。しかし、結局、川上よりは川下、川下よりは県庁所在地、県庁所在地よりはブロック都市、ブロック都市よりは東京の方が観光客数も多いのである。
テレビ、自動車、スマホが時間空間の均一化をもたらしたとするならば、観光客は何をもたらしているのか?経済効果はきちんと測定されていないが、ルゴフは前述のとおり「地元の年配者は観光客や裕福な新規住民のために作られた劇場の装飾物の管理人として生きている」とする。京都市も沖縄県も地域住民の所得は全く増加していないのであるから、京都人・梅棹忠夫が文化と観光を一緒にするなと叫んだことの方が正しかったのかもしれない。
関連記事
-

-
国際人流・観光状況の考察と訪日旅行者急増要因の分析(1)
Ⅰ 訪日外客数の急増と福島原発事故の世界の旅行界に与えた影響 明るい話題が少ないのか、訪日外国人客
-
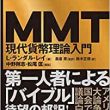
-
『MMT現代貨幣理論入門』
現代貨幣理論( Modern Monetary Theory, Modern Money The
-

-
『日本経済の歴史』第2巻第1章労働と人口 移動の自由と技能の形成 を読んで メモ
面白いと思ったところを箇条書きする p.33 「幕府が鎖国政策によって欧米列強の干渉を回避した
-

-
quora 中世、近世のヨーロッパで、10代の女性がどのような生活を送っていたのか教えてくれませんか?貴族階級/庶民とそれぞれ、何をしていたのでしょうか?
何で10代の女性限定なのかよくわかりませんが、知っている範囲で。 中世の庶民は、ほぼ
-

-
言語とは音や文字ではなく観念であるという説明
観光資源を考えると、言語とは何かに行き着くこととなる。 愛聴視して「ゆる言語学ラジオ」で例のエ
-

-
国際人流・観光状況の考察と訪日旅行者急増要因の分析(2)
1 国際「観光」客到着数 『UNWTO Tourism Highlights 2016 E
-

-
「若者の海外旅行離れ」という 業界人、研究者の思い込み
『「若者の海外旅行離れ」を読み解く:観光行動論からのアプローチ』という法律文化社から出版された書
-

-
フェリックス・マーティン著「21世紀の貨幣論」をよんで
観光を理解する上では「脳」「満足」「価値」「マネー」が不可欠であるが、なかなか理解するには骨が折れる
-

-
動画で考える人流観光学 観光資源、質量の正体は一体何なのか -質量の起源-
https://youtu.be/TTQJGcu-x3A https://
-

-
ヴィアレッジョ スーパーヨットの街
地方創生は無理をしないで伝統を発展させれば、人口6万の町でもトランプさんはヨットを注文してくるのです