『インバウンドの衝撃』牧野知弘を読んでの批判
題名にひかれて、麻布図書館で予約をして読んでみた。2015年10月発行であるから、爆買いが話題の時代であり、まだ1千万人前半の時代である。それでも副題は外国人観光客が支える日本経済となっている。
主な客が中国人とアセアンとなっているが、極東とした方が正しい。四分の三は中国本と香港に韓国及び台湾からの客であるから。
訪日外国人客がなぜ増加したかという問題意識は正しい。彼らの所得が向上したことに加えて円安効果が出ているからであるとするのは正しいが、手放しの日本の観光資源礼賛論がその後に続いているのは、本の販売政策上仕方がないのかもしれない。
レンタカーやヘリコプター等に関する記述は新聞記事の域を出ず、まったくページ数稼ぎにしか過ぎないが、私も単著を出版するときに、どうしてもこういう部分が出てしまうので、あまり人のことは言えない。
さて世界大航海時代の幕開け以下の第6章は、著者には申し訳ないが、まったくの駄文である。大航海時代的発想をする研究者がこれまでも存在した。ビッグバン等を唱えていたが、科学的分析に欠けるところがある。WTOの統計を基にインバウンドの記述するから、人の移動を、国境を超えるものにしか目を向けていない。中国の国内観光は大混雑であり、アメリカも国内観光が大規模である。国際観光統計は、一人の客が複数国を訪問すれば、複数人の数となる。また、世界最大の人口を有する中国一つとっても、統計上の国境は別である。香港、マカオ、台湾が絶えず問題となる。24時間365日ルールについても無知である。日帰り客は含まれない。しかし、世界の人流市場では、米国、カナダ、メキシコ間の日帰り客は数千万人規模であり、同じく、中国本土と香港、マカオ間も同様である。これにとどまらず、シンガポール、マレーシア間、中国本土とベトナム間の陸上移動は統計すらとっていない。ドイツの統計も宿泊機関からの報告を基にしているから、日帰り客はおよそ考えていないのである。WTOの統計では半数近くが欧州になる。当たり前のことで、欧州は国境が多く、少し動けば外国なのであるから、数字が大きくなるだけである。このことを理解すれば、「京都がパリを超えられるか」などというバカな設問は出てこないはずである。現に欧州各国の来客国は上位はアメリカを除けばすべて隣接国である。従って、日本も隣国が多いのは当たり前なのである。欧州はシェンゲン条約が結ばれており、既にインバウンド概念が希薄である。インバウンドと国内観光を同列に扱って分析を行っている。観光客がパスポートを持っているか否かにはこだわる必要がないからである。
観光大国か否かの基準を訪問外客数にのみこだわるのも後進国の発想である。数だけなら国の規模が大きければその分大きくなるだけのことである。ドイツ、中国、アメリカは送客数において大国であり、観光業界では大国として注目されている。かつての日本もそうであった。インバウンドもアウトバウンドも、国内観光も大きい国が観光大国として認識されるのであろう。そのためには、隣国が豊かにならなければならないのであり、その条件が日本でも整ってきたのである。
国際収支の観点からインバウンドを評価する向きもある。そのこと自体も間違っているわけではないが、視野が狭いと思われる。国際収支は旅行収支だけではなく、国際運輸収支もあり、貿易収支もあり、資本収支もある。アメリカは、貿易収支は大赤字で、トランプ大統領が問題にしているが、資本収支は黒字で帳尻があっている。日本は長らく貿易収支が黒字であったが、現在は海外からの配当、金利、特許料等の比重が大きい。いずれにしろ最終的にはプラマイゼロになるのが国際収支であるから、旅行収支が黒字なっても、国民所得が伸びなければ豊になったとは判断できないのであるが、地方では国際的に貧しくなっており、そのことがインバウンドの掛け声のもとにかき消されている。おかしなことである。
関連記事
-
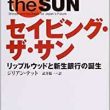
-
『セイヴィング・ザ・サン』 ジリアン・テッド
バブル期に関する書籍は数多く出版され、高杉良が長銀をモデルに書いた『小説・ザ・外資』はア
-

-
新語Skiplagging 「24時間ルール」と「運送と独占の法理」
BBCの新しい言葉skiplagging
-

-
観光資源と伝統 『大阪的』井上章一著
今年も期末試験問題の一つに伝統は新しいという事例を提示せよという問題を出す予定。井上章一氏の大阪
-

-
Quora 「汎化性能」
すべてのデータサイエンティストが知っておくべき、統計学の重要なトピックはなんでしょうか?
-

-
幸田露伴『一国の首都』明治32年 都議会議員和田宗春氏の現代語訳と岩波文庫の原書で読む。港区図書館にある。
幸田露伴は私の世代の受験生ならだれでも知っている文学者。でも理系の人でもあり、首都論を展開してい
-
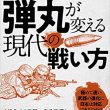
-
『弾丸が変える現代の戦い方』二見龍 照井資規 誠文堂新光社 2018年
本書は、今までほとんど語られてこなかった弾丸と弾道に焦点を当てた元陸上自衛隊幹部と軍事ジャーナリ
-

-
『素顔の孫文―国父になった大ぼら吹き』 横山宏章著 を読んで、歴史認識を観光資源する材料を考える
岩波書店にしては珍しいタイトル。著者は「後記」で、「正直な話、中国や日本で、革命の偉人として、孫文が
-

-
『金融資本市場のフロンティア 東京大学で学ぶFinTech、金融規制、資本市場』に学ぶべきMaaS
本書を読んで、アンバンドリングとリバンドリングという言葉に出会った。金融機能が、テクノロジーが導入
-

-
脳科学 ファントムペイン
四肢の切断した部分に痛みを感じる、いわゆる幻肢痛(ファントムペイン)は、脳から送った信号に失った
-

-
旅資料 安田純平『ルポ 戦場出稼ぎ労働者』集英社新書
p.254「戦火のイラクに滞在し、現地の人々の置かれた状況を考えれば自分の拘束などどういうことでも

