2002年『言語の脳科学』酒井邦嘉著 東大教養学部の講義(認知脳科学概論)をもとにした本 生成文法( generative grammar)
メモ p.135「最近の言語学の入門書は、最後の一章に脳科学との関連性が解説されている」私の観光教科書も、最終章は観光情報論で取りまとめて、脳科学への収斂としているが、脳科学そのものは他人の受け売り文章である。
観光学では、概論や辞典の最初に、観光の語源を解説することが多い。しかし、本書では「単語と意味の関係は極めて恣意的で、必然的な法則性はない。語源論を追い求めても、科学にはならない」と記述しているように、サイエンスではないであろう。
言語も自然法則にしたがっている 人間に特有の言語能力は、脳の生得的な性質に由来する 脳 心 言語の階層構造 人間は脳が進化したから言語が使えるようになった チョムスキーは自然言語には必然的な文法規則があり、これが普遍的かつ生得的な原理であることを提唱した。一方意味や概念の学習は後天的であり、単語と意味のつながりは連装に基づくもの、その連想関係は偶然的
言語サバン、クリストファーは、幼児の言語モジュールを大人になっても失わなかったところがユニーク
認知脳科学の中で言語をきりはなす努力をしているが、認知言語学は言語の独自性をなくす方向をめざしている。
p116「チョムスキーは人間である限り生得的に備わった言語能力が存在すると考えた」p.126「脳から決定される人間の行動は、心理学の経験則だけでなく、精緻な論理的予想や数理モデルによって明らかになるものと期待されるが、実際には難しい」観光行動論はそこまでいっていないのが残念である
アマゾンの照会「言語に規則があるのは、人間が言語を規則的に作ったためではなく、言語が自然法則に従っているからである―。こうしたチョムスキーの言語生得説は激しい賛否を巻き起こしてきたが、最新の脳科学は、この主張を裏付けようとしている。実験の積み重ねとMRI技術の向上によって、脳機能の分析は飛躍的な進歩を遂げた。本書は、失語症や手話の研究も交えて、言語という究極の難問に、脳科学の視点から挑むものである」
アマゾン書評
言語は心の一部なら、脳の一部である。脳の一部であるなら、科学の対象である。脳科学は医学部で言語学は文学部、という区分は全く古いのである。また、言語が科学の対象であるなら、言語には自然法則がある。そして、「言語に自然法則があるとすれば、それは普遍的でなくてはならない」(p16)。われわれは、「脳によって決められた『文法』に従っていて、人間が話す言葉の構造は、勝手気ままに変えられるわけではない」(同上)のが根拠となる。新書でありながら、引用元や参考文献が詳しく説得力がある。チョムスキー批判についても、「チョムスキーの理論は古い、という主張そのものが古いのだ」(p113)と喝破していて痛快である。ところで、「言語が何かの必要性から生まれたと考えるのは誤り」(p37)で、進化を考える上でよくある勘違いである。「鳥の翼は飛ぶために必要なものだが、飛ぶ必要性から翼が進化したわけではない。進化の遺伝的メカニズムには、今西錦司(一九〇二~九二)が唱えた進化論のような、「なるべくしてなる」という合理目的性は存在しない。鳥は、翼が進化したから飛べるようになったのである。同様にして、人間は脳が進化したから言語を使えるようになったのである」(p同上)。ちなみに、言語はコミュニケーションのために適応したのが言語の起源だとスティーブン・ピンカーが主張したことがあるらしいが、進化に合理目的性がないのだから誤りだと主張を排している(p95)。非常に勉強になった。
書評2
1章〜4章は、脳科学(脳研究全般ではなく、言語に関する脳の働きの解明を
目的とする脳科学)と生成文法の関係を説くために書かれたと思われる内容です。
ただし、著者の誤解に基づく思い込みが激しい内容で、生成文法の知識が
少し怪しい部分が垣間見えますし、言語心理学や社会言語学など、
他の言語学を不当に誹謗している書き方で、参考にはならない内容です。
5章〜10章には、本題であり、著者の専門分野である脳科学の話が書かれています。
でもその内容は、著者の研究成果ではなく、今まで過去に他の研究者によって
明らかにされて来た内容を浅く紹介する程度のものです。
著者の専門分野なので、読む前は期待していましたが、
実際は、脳科学の最初歩の内容で、他の入門書で書かれている内容と同じです。
そうしたものをすでに読んでいる方はこの本を読む必要はないと思います。
11章は手話について、12章と13章は言語獲得と脳についての内容です。
これらも他の入門書で書かれている内容と代わり映えせず、
そうしたものをすでに読んでいる方はこの本を読む必要はないと思います。
以上のように、「専門書でなく新書だからね、こんなもんでしょ」って感じの内容です。
ただし、脳科学に関する記述は問題ないのですが、1章〜4章の他分野への批判は、
あくまで著者の誤解や思い込みに基づいた不当なもので、
予備知識のない読者は、著者のこれらの言葉を真に受けてしまう危険があります。
これを理由に星2つとしました。
書評3
脳科学が言語処理に関する脳機能のどこまでを証明できているのか、当時の研究成果を解説している。言語処理における脳の機能局在、モジュール仮説、プラトンの問題など、脳科学が主要な課題としているものが分かりやすくまとめられている。
本書では、言語障害の事例分析やMRI技術を用いた実験から、言語が統語、意味、音韻のそれぞれ独立の情報処理機能の複合として成立していることが仮説として提唱されている。著者は、チョムスキアンの立場から、この仮説が、将来的にあらゆる言語を生みだす法則の証明にまでつながると考えているようだ。
しかし、本書を読んでも分かるとおり、現在の脳科学が証明できていることとは、脳の機能局在というところまでだろう。機能局在は、物理的な存在としての脳が、言語処理の際に、特定の部位が特定の機能を担うということを説明しているに過ぎない。脳が分担的に役割を果たしているということは、物理的な現象であるから「脳機能の普遍性」と呼ぶことができる。
だが、これは多様な言語表現を可能にする普遍的な言語規則の存在を証明していることにはならない。つまり、物理的な脳機能の普遍性と、多様な言語表現を統一的に情報処理する「言語規則の普遍性」との違いが不明確なまま議論が展開されていて、脳科学がチョムスキーの普遍文法のどこまでを証明できているのかがわかりにくくなってしまっている。
普遍文法の知識、すなわち、現実の言語運用の場面で多様な形式で現れている言語表現を統一的に処理している脳の仕組みは現在の脳科学ではまだ全く未知の領域ということだ。その点が解明されるまでは、脳科学からチョムスキー理論を裏付ける試みは成功したとは言えないだろう。本書に限らず、言語の脳科学に関する本を読む際は、この点を考慮しながら読むべきだと思う。
書評5
この新書版は、言語というものが物理的に脳の言語関連領域(従来左脳で分割・解析、右脳で整流・統合するといわれてきた)で生成する、
という視点に立って書かれたものです。いわば単語が文法体系に乗って脈絡をなす形で配列するもので、
モジュラー形式というのは、言語生成上その際のコアとなる単語なり概念なり(つまりキーワードやキーコンセプト)のまわりで、
コンテクストやムードあるいは文法規則なりが取り巻くように触発して、場に適応した有意な立体配座(コンホメーション)となるように、
残りの単語や概念を配位するようです。
たとえていえば、化学結合における配位的な錯体(よってケアレスミスを含む!)にあたるものでしょうか。
このときに左脳と右脳が脳梁を介して連携し、よく要素レベルにまで分析された単語なりが、
その場の状況にあうかたちで、最小限の文法規則に従って配列される、とも考えられます。
この点、コミュニケーションとはコーディングとデコーディングであり、インプットとアウトプットなのです。
本書にはいろんなキータームがでてきますが、それもこの分野がまだ新しい模索過程にあるからで、
学問分野として十分に確立されたものではないからなのです。
従来、伝統的な言語学は独自の方法論から言語にアプローチしてきましたし、心理面との連携もありましたが、
より物理学の方法を取り入れたアプローチは新しいもので、コンピューターサイエンスや工学畑からは、
ニューラルネットワークなどのアプローチがある程度理解され浸透もしていますが、
脳の構造を物理的に捉え直した上で、単語や概念要素がどう脳内に分布し、
どんな適合的状況下で、どう組み上がってゆくのかというブートストラッピング過程をもろに扱える分野は、
「唯脳論」を含めまだあまり多くはないようですね。唯脳論はそのパラダイムを与えてくれる重要な考え方だと思っています。
本書は学問としてまだ新生の物理言語学を、手話通訳や言語障害などの事例を参照しながら、
従来の言語学(音韻論/統辞論/語用論)からはみでてしまう言語現象まで含めて、総合的に扱ってゆこうという意気込みに満ちたものとして、
その基本的な考え方の一端を広く紹介した良書ですから、幅広い言語現象に関心のある方になら誰にでもおすすめできると思いました。
関連記事
-
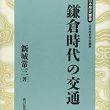
-
『鎌倉時代の交通』新城常三著 吉川弘文館
交通史の泰斗新城常三博士の著作物をはじめて読む。『社寺参詣の社会経済史的研究』が代表作であるが、既
-

-
人間ってなんなの?:チンパンジーの4年戦争【 進化論 / 科学 / 人 類 】タンザニア
グドール 道具を使うチンパンジーを発見 ジェーン・グドール(Dame Jane Morris Go
-
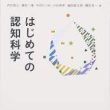
-
『はじめての認知科学』新曜社 人工知能研究(人の知性を人工的に作ろうという研究)と認知科学研究(人の心の成り立ちを探る研究)は双子
人工知能研究(人の知性を人工的に作ろうという研究)と認知科学研究(人の心の成り立ちを探る研究)は
-

-
井伏鱒二著『駅前旅館』
新潮文庫の『駅前旅館』を読み、映画をDVDで見た。世相はDVDの方がわかりやすいが、字句「観光」は
-

-
QUORA 日本の歴代総理大臣ワースト1は誰ですか?
日本の歴代総理大臣ワースト1は誰ですか? 近衛文麿でしょう。彼は首相在任中に国運を左右する二
-

-
Quora 古代日本語の発音
youtubeで、「百人一首を当時の発音で朗読」という動画を見ました。奈良・飛鳥時代の上代日本語
-

-
ウェストファリア神話
国際観光を論じる際に、文科省からしつこく、「国際」観光とは何かと問われたことを契機に、国際について
-

-
若者の課外旅行離れは本当か?観光学術学会論文の評価に疑問を呈す
「若者の海外旅行離れ」を読み解く:観光行動論からのアプローチ』という法律文化社から出版された書籍が
-

-
動画で考える人流観光学 [バリバラ] 感覚過敏の世界 ~味覚過敏・聴覚過敏編
https://youtu.be/OEMhx_pIyiM
