フェリックス・マーティン著「21世紀の貨幣論」をよんで
公開日:
:
最終更新日:2023/05/30
出版・講義資料, 路銀、為替、金融、財政、税制
観光を理解する上では「脳」「満足」「価値」「マネー」が不可欠であるが、なかなか理解するには骨が折れる。
フェリックス・マーティンの「21世紀の貨幣論」は、各書評では題名を含め評価にいろいろあるが、素人の私にはわかりやすかった。
マネーは、文字、数字、会計というメソポタミアの発見と、部族民の社会的価値はみんな等しいっていう暗黒時代のギリシャの原始的な部族の考え方が衝突して発明された」(p.399)と著者は記す。メソポタミアの「古代世界で最も進んだ経済が、文字、数の概念、会計を発明した社会が、なぜマネーを発明しなかったか」(p.68)は、「徹底した官僚制の社会ゆえ「抽象的で普遍的な経済的価値の単位」(p.89)を生み出せなかったからと記す。一方、ギリシャの原始的な社会は、成員の(平等な)「社会的価値」という概念を保持し、そこにメソポタミアの先進文化を受け入れることで(普遍的な価値の単位をも生み出す)条件がそろい、ギリシャでマネーが発明されたと説く。経済的価値という普遍的な物差しで、社会における様々な関係性を測ることのできる客観的な実態が存在したからである。
著者は物々交換経済から貨幣が生まれたとする「標準的な貨幣論」をあっさり否定する。マネーとは何かと問われた時、経済学者を含む多くの人達は物々交換からの進化で、あるモノが選択され貨幣となり、更に金・銀となり…、という標準貨幣史から生まれる学説を当たり前のように語るが、この「標準的貨幣観」実はが誤ったものだということをヤップ島のフェイ(石貨)を手始めに論じている。マネーは財のひとつなどではなく、誕生したころから「信用・決済のシステム」だったというものである。早速日比谷公園に出かけて、存在を確認してきた(アイキャッチ写真参照)。これでは持ち運びできないことは確かである。
本書では、マネーの本質を信用と譲渡性だと考えている。マネーとは(金や銀などの)モノではなく、社会的技術であり、「譲渡することが可能な信用」こそがマネーだという。
その一つの事例が、1970年アイルランドで起こった「銀行閉鎖」になる。当初、どれだけの社会的混乱を引き起こすか検討もつかなかった銀行閉鎖だが、実際には想定されたような大混乱は発生しなかった。硬貨や紙幣の流通が止まっても、国民は支払いの大部分を小切手で済ませることができた。もちろん、小切手はいっさい銀行に持ち込めない。銀行システムが閉鎖されたことで、小切手は単なる借用書でしかなくなっていた。しかし、いつ清算されるかわからない信用システムが、既存の銀行システムの代わりをした。
アイルランドの銀行閉鎖が物語るように、信用を創造して流通させるシステムは、公的に認められたものである必要はない。問題は、信用力があり、他の誰もがその信用力を受け入れてくれると、信頼されている発行体がいるかということである。企業がこの基準を満たすのはむずかしいですが、アイルランドの例が示すように、公的なマネーシステムが崩壊すると、社会は驚くべき力を発揮して、それに代わるシステムをすぐに作り上げるのも事実である。個人的な経験では、1990年代初期の混乱期のモスクワで「マルボローの赤」が一ドルの代わりをしていたことを思い出した。
著者は現代のマネーへの考え方に決定的な役割を果たしたのが、ジョン・ロックであり、彼の考え方を現代まで引きずっていることが問題だとする。17世紀のイングランドでは、完全重量銀貨が流通していたが、金属の市場価値が上がると硬貨ではなく銀として取引されてしまうために、貨幣の流通量が減少した。このため、銀の含有量を減少させる提案がなされたが、ロックはこれに反対する。結果として、硬貨の流通がなくなり、デフレに突入する。銀がなくなると今度は、ポンドを金の一定重量を表現するものとして再定義したのである。すなわち、マネーを金や銀などの実物の価値のある物と結びつけるというこのロックの貨幣観が、市場に鑑賞しないことを合理的な人間の倫理上の義務として扱う経済学に引き継がれていったと著者は言う。この考えを引きずっている経済学はマネー社会の不安定さを生む社会と政治の問題に対する答えを出すことができないでいるとしている。
一方、著者は独自の視点で著名とはいえない人物に注目する。1人は、14世紀のスコラ学派のニコル・オレーム。彼は、それまでの貨幣は君主のものという考え方を、マネーを使用する共同体全体の所有物だとした。金融政策には富と所得を再分配する力や取引を抑制したり刺激する力があることから優先するべきは君主の歳入ではなく、共同体全体の商業活動であると説いた。
また著者はあの史上最大の詐欺師とも呼ばれているジョン・ローに注目する。すなわち、初めて貨幣を一定量の貴金属との交換という裏付けを断ち切り、ペーパーマネーとした人物であるという位置づけとしてである。つまり、「すべての所得と富は生産性の高い経済から生じる。マネーが究極的に表現するのはこの所得に対する請求権だけである。ところがこの所得は不確実である。リスクをベールで覆い隠すのではなく、マネーを使うすべての人にリスクをはっきり示してそれをすべて負わせるというエクイティマネーの誕生である。」
また19世紀、金融危機下にあったシティを描いた「ロンバード街」を著したバジョットも登場させる。それは、以前の古典派の抽象的な経済学とは異なり、マネー経済の現実に合わせて理論を構築していること、金融を出発点としている経済学であるという認識である。そして、信頼を基礎として成り立っているが故に、大事件が起きれば信頼がほぼ崩れ去る懸念もある。つまり、信頼と信任という社会に内在する属性が非常に重要であり、ここにそれまでの経済学と大きく異なる視点があるとする。このため、マネーの安全性や流動性に対する信任が揺らいだときにいつでも無制限に貸し付ける用意を整えること、これが予防的な金融政策の原理原則であるとしたのである。そしてこの認識が、今回の世界金融危機の際の参考になったという。
最後に、著者の改革案である。これはフィッシャーの提言を取り入れ、マネーと金融を抜本的に改革するというものである。すなわち、ナローバンキング制とし、銀行は預金者が引き出したり支払いに使う決済預金のみを取り扱う小切手銀行として分離し、それ以外の業務については、国の支援や監視を一切受けない。約束が守られなければ投資家は救済されない。そしてもう一つ。現在のマネーをめぐる問題は、その背後にある経済学を一から作り直す必要があるともいう。加えインフレターゲティング信仰を捨てよとする独特の貨幣観を提示する。「たくさんの国で金融の不均衡が持続不可能な次元に達している。この債務の山を時間をかけて解消とするやり方は政治的に不可能だし、経済的に望ましいことではない。数年間高インフレを起こすか債務そのものを再編することがこの問題に直接対処できるようになる。」
ナローバンキングが適切かは私にはわからない。インフレターゲット論が正しいとは思えないが、安倍政権誕生時は皆がそれに期待していたことも事実であるから、移ろいやすい。経済学を一から作り直す必要があることは、その通りだと思うが、作り直せるかは素人だからわからない。結局脳のメカニズムがわからない限り課題は残るのであろう
関連記事
-

-
井伏鱒二著『駅前旅館』
新潮文庫の『駅前旅館』を読み、映画をDVDで見た。世相はDVDの方がわかりやすいが、字句「観光」は
-

-
保護中: 対面型産業の物価注視を 危機後の金融政策の枠組み
対面型産業の物価注視を 危機後の金融政策の枠組み 日本経済新聞【経済教室】2020年6月29
-

-
『日本軍閥暗闘史』田中隆吉 昭和22年 陸軍大臣と総理大臣の兼務の意味
人事局補任課長 武藤章 貿易省設置を主張 満州事変 ヤール河越境は 神田正種中佐の独断
-

-
『戦後経済史』野口悠紀雄著 説得力あり
ドッジをあやつった大蔵省 シャープ勧告も大蔵省があやつっている。選挙がある民主主義では難しいこと
-

-
『日本が好きすぎる中国人女子』桜井孝昌
内容紹介 雪解けの気配がみえない日中関係。しかし「反日」という一般的なイメージと、中国の若者
-
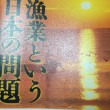
-
『漁業という日本の問題』勝川俊雄 日本人は思ったほど魚を食べてない。伝統の和食イメージも変化
マスコミによってつくられた常識は、一度は疑ってかかる必要があるということを感じていますが、「日本人は
-

-
『金融資本市場のフロンティア 東京大学で学ぶFinTech、金融規制、資本市場』に学ぶべきMaaS
本書を読んで、アンバンドリングとリバンドリングという言葉に出会った。金融機能が、テクノロジーが導入
-

-
塩野七生著『ルネサンスとは何であったのか』
後にキリスト教が一神教であることを明確にした段階で、他は邪教 犯した罪ごとに罰則を定める 一
-

-
『財務省の近現代史』倉山満著 馬場鍈一が作成した恒久的増税案は、所得税の大衆課税化を軸とする昭和15年の税制改正で正式に恒久化されます・・・・・通行税、遊興飲食税、入場税等が制定されたのもこの時であり、戦費調達が理由となっていた 「日本人が汗水流して生み出した富は、中国大陸に消えてゆきました」と表現
p.98 「中国大陸での戦争に最も強く反対したのは、陸軍参謀本部 p.104 馬場

