『江戸の旅と出版文化』原淳一郎
公開日:
:
最終更新日:2021/08/05
出版・講義資料
中世宗教史と異なり近世宗教史の大きな特徴に寺社参詣の大衆化がある。新城常三の「社寺参詣の社会経済史的研究」の上梓以降、研究が飛躍的に進展し、多くの庶民が旅に出ていたことが具体的にわかってきた。
p16 旅が広まる要因の一つに、寛永8年以降の建立された寺院は檀家を持つことが許されなかったことがあり、派手な宣伝活動を行い他地域からの参詣客を増やすことに専念した。
「膝栗毛」爆発的にヒットし、参詣を誘発したと安易に書かれることが多い。一般的に、出版物が読むものから使う物へと変化したといわれる。だが、本当にこれを実証した人がいるのであろうかとする。
寛政6年から享和3年にかけて、参詣型往来物は、それまでの地理学習用手習い本から、徐々に実用性を高めていった。その背景には江戸周辺の社寺の案内記としての受容の高まりがあり、地域を認識する段階から地域の個性を発見する段階への転換点でもあった。黒部アルペンルートの開発者佐伯宗義は観光は地域の個性の発揮といったが、近世において始まっていたのである。
18世紀後半において、社寺参詣の大衆化に対応できる出版物は江戸、鎌倉、日光を除き皆無であった。元禄後期から享保期に関東の社寺が広い範囲から参詣客を獲得してゆき、参詣客の講が形成されてゆくのが宝暦期である。参詣地の複合化が起きるのが明和・安政期。これを境に各地へ単一的に営まれていた参詣形態が変容し、互いに参詣者が流入しあって等質化し、それまでの道中記のような各街道を主とした出版物では飽き足らなくなった。こうした時期の登場したのが名所図会と参詣型往来物である。
文化期頃から、三都の書肆による出版から次第に各地域において在地出版のよる参詣型往来物が登場した。一方、旅の実用性だけではなく、教育という視点も同様に重要である。例えば幼児教育のために一地域の往来物を作成する者が現れた。この郷土意識の高まりを排他的な国学の影響とするのは性急とする。教育基本法と国、地域の誇りを強調する観光立国推進基本法の関係を思い出してしまう。
名所とは、しょせん人間の頭の中の産物に過ぎないとする(脳科学)。字句名所の成立は、和歌に詠まれる「ナドコロ」である。和歌の世界だけで再生産されるから多分に観念的な要素を持っている。その一方「名所」は和歌の世界を軽く飛び越えてゆき、広範な概念となった。上杉和央氏は「俗名所」として読んでいる。
近世の紀行文は、それまで土佐日記が生まれて以来詠嘆をはっきりとさせてきたのに対し、知性を重んじ文章は簡潔、地誌的でさえある。読まれることを想定して旅の実像を伝えようとする意志があった。その点奥の細道は中世紀行文の系譜を受け継ぐもの。
近世の人々は、程度の差こそあれ、先行する紀行文によって自分が学んできた知識を名所ごとに予習して再構築し、情報を十分に得てから自律的に取捨選択して旅にのぞんでいた。観念の世界から実際に目で確かめられる名所へと変化した。といっても、依然として「書物を介して継承されている世界」にとどまっていた。この点は現在も同じ。書物に、映画やネットが加わっただけである
女人禁制 危険な場所から女性を遠ざけるという、長年の人々の知恵があった。
関連記事
-
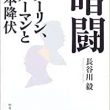
-
歴史認識と書評『暗闘 スターリン、トルーマンと日本降伏 』長谷川毅
日本降服までの3ヶ月間を焦点に、米ソ間の日本及び極東地域での主導権争いを克明に検証した本。
-

-
「第3章 流入する他所者と飯盛女」武林弘恵著『旅と交流に見る近世社会』清文堂
旅と交流にみる近世社会 高橋陽一 編著
-

-
ヒマラヤ登山とアクサイチン
〇ヒマラヤ登山 機内で読んだ中国の新聞記事。14日に、両足義足の、私と同年六十九歳の中国人登山
-

-
ハーディ・ラマヌジャンのタクシー数
特殊な数学的能力を保有する者が存在する。サヴァンと呼ばれる人たちだが、どうしてそのような能力が備わ
-

-
『知られざるキューバ』渡邉優著 2018年
4年前のキューバ旅行のときにこの本が出版されていれば、また違った認識ができたとの思う。 カリ
-

-
世界人流観光施策風土記 ネットで見つけたチベット論議
立場によってチベットの評価が大きく違うのは仕方がないので、いろいろ読み漁ってみた。 〇 200
-

-
GetTaxi Via (company) YANDEX
Gett, previously known as GetTaxi, is a global on-
-
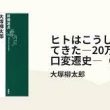
-
『ヒトはこうして増えてきた』大塚龍太郎 新潮社
p.85 定住と農耕 1万2千年前 500万人 祭祀に農耕が始まった西アジアの発掘調査で明らかにさ
-
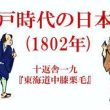
-
『日本語スタンダードの歴史』野村剛士は、「日本の話しことばについて」『現代国語三』所収 木下順二著1963年を否定
私の自説に、日常と非日常が相対化しており、観光資源もあいまいになってきているというアイデアがある
- PREV
- 『近世社寺参詣の研究』原淳一郎
- NEXT
- 『鎌倉時代の交通』新城常三著 吉川弘文館

