『鎌倉時代の交通』新城常三著 吉川弘文館
公開日:
:
最終更新日:2021/08/05
出版・講義資料
交通史の泰斗新城常三博士の著作物をはじめて読む。『社寺参詣の社会経済史的研究』が代表作であるが、既にその後に続く研究者の著作物に目を通しているので、私の関心事である、観光概念の発生等について、鎌倉時代は観光概念が存在しなかったことを確認のため、港区図書館で借りだして読ませていただいた。
古代律令制下においては、交通・運輸の根幹的主体は官吏であり、国家献納物であったが、平安中ごろから荘園的交通が凌駕する。荘園的交通とは、荘園を巡る荘園年貢物の輸送と荘官等荘園関係者の往来を指す。荘園的交通においては物資輸送が主で、人の交通は従であったが、陸上の場合は、当時の輸送技術の極端な低さから、相当量の人員がこれに関与するのが常であって、人の移動の荘園的交通に占める比重は軽視されるべきではないとする。
農民の行旅に関しては、相対的に自給自足的生活の濃厚な鎌倉時代の農民の大半は、自ら好んで郷土を一歩越える必要性や刺激は、一般的にほとんどなかったとする。郷土外への他出といえば、近傍の定期市場への出入りや、近傍の社寺参詣などが、強いてあげられるにとどまり、それ以上、彼らを遠隔交通へ誘発する要因は、ほとんどなかった。
中世欧州では一般に領主の直接経営地の投入される農耕労働力が基幹的な不役である。これに対し我が国にあっては、領主の直営地が相対的に狭隘な点から、むしろ非農業的夫役に優越するようであるとする。しかも我が国の非農耕的夫役の内容は雑多にわたるが、そのうち何らか交通に関連する夫役が、特に顕著である。
東海道と宿に関し、橋及び渡船の不備、年中行事のような増水氾濫を加えるならば、自然状態を放置する場合、河川による東海道の交通上の困難と障碍の重みは、予想をはるかに超えるものである。 東海道は概ね道路は平坦で温暖であり、その上風勝にも富んである。東海道の致命的な交通障碍である河川の渡河も、その後の技術向上により次第に克服されてゆく。こうして東海道は東山道に対する交通上の優位性を徐々に勝ちえる。東海道の交通量は時を追って漸増するのであった。 特に中世に入り、鎌倉幕府の成立以来、京都・鎌倉間の交通量が急激に上昇し、東海道の道路・宿泊機関の整備が進むと、東海道の吸引力はますます大となり、東山道は裏街道としていよいよ顧みられることが少なくなった。
東海道の交通量の発展につれて、旅人相手の宿屋や遊女の発生するのもまた自然の成り行きであったとする。古代末、東海道の各所に宿(しゅく)と呼ばれる聚落が現れた。宿とは営業的旅宿を中心として成立した交通聚落である。遊女と交通とのつながりの堅いことは、遊女の相手が主として旅人・船客である点からも疑いないとする。
平安末には東海道の所所に交通聚落が発達し、人々はそれまでの野宿等の宿泊の不安から解放されつつあった。宿及び遊女等が交通不便の緩和剤となり、その後の交通上昇の促進剤となった。交通聚落は、旅人が滞留・宿泊を迫られるような地点に発生しやすい。河川の渡渉地点、山麓等、街道と街道の合流地である。
宿は、遊女を媒介として地方文化の中央紹介に一役を担ったが、逆に遊女が中央文化の東国伝播に果たした役割はより重視されるべきとする(猿楽等)。このあたりの理解は、遊女をメディアと置き換えれば、現代と変わらない。文化の地方伝播における宿の重要性は、庶民性が濃厚な新興仏教の伝道において、やや具体的に表現される。庶民性に焦点を当てれば、新興宗教概念と観光概念の共通点が見いだせるから面白い。
宿が単純なる交通集落にすぎず、宿の住民が、その生活の大半を外来者である旅客に依存する限りは、宿は地方社会と遊離した存在で、その聚落基盤も脆弱である。
駅制に関しては、中世駅制は全く幕府存立のための交通制度であった。駅の負担が御家人の個人負担を超えて荘園及び民衆の負担化されたが、それとともにその被害は旅人にまで及んだ。鎌倉幕府の駅制が一般交通の発展に無縁のみならず、むしろそれを阻害する否定的存在を無くしていたことは注意されなければならないとする。
鎌倉時代における交通界の特徴的な現象に交通圏の拡大があるとする。国家権力の行政権の拡大に伴い必然の結果である。
鎌倉幕府の崩壊により、京都が再び交通上唯一の中心として古代の栄光を回復。しかし、在地領主制の発展により、中央への輸送量を漸減させた。それのも拘わらず京を中心として中央都市の発展は、従来以上に多量の物資移入を必要とする。輸送界は荘園年貢輸送より商品輸送へと転換した。陸運より水運で一層明確である。
荘園的輸送からは、中央物資の地方流通は生まれがたく、年貢輸送の担夫、馬匹、船舶は空荷でもどる。しかし、地方からの商品は中央にて売却され一旦貨幣化され、多くの場合他の都市的商品となって、再び地方に還元される。こうして荘園的輸送から商品輸送への転化は、物資の求心的片荷輸送から、相互往還輸送への展開を将来し、地方経済を促進したとする。現代の物流論と共通する問題意識である。
関連記事
-

-
『「日本の伝統」の正体』
現在、「伝統」と呼ばれている習慣の多くが明治時代以降に定着したと聞いたら驚く人も多いかもしれない
-

-
幸田露伴『一国の首都』明治32年 都議会議員和田宗春氏の現代語訳と岩波文庫の原書で読む。港区図書館にある。
幸田露伴は私の世代の受験生ならだれでも知っている文学者。でも理系の人でもあり、首都論を展開してい
-

-
政治制度から考える国会のあるべき姿 大山礼子 公研2019年1月号
必要なのは与党のチェック機能 どこの国でも野党に政策決定をひっくり返す力はない 民主主義は多数決だ
-

-
QUORA 李鴻章(リー・ホンチャン=President Lee)。
学校では教えてくれない大事なことや歴史的な事実は何ですか? 李鴻章(リー・ホンチャン=Pre
-

-
保護中: 書評『脳は空より広いか』エーデルマン著 冬樹純子訳 草思社
エデルマンは、Bright Air、Brilliant Fire、Wider than the
-
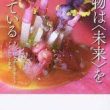
-
保護中: 『植物は未来を知っている』ステファノ・マンクーゾ 、動物が必要な栄養を見つけるために「移動」することを選択。他方、植物は動かないことを選び、生存に必要なエネルギーを太陽から手に入れるこにしました。それでは、動かない植物のその適応力を少しピックアップ
『植物は<未来>を知っている――9つの能力から芽生えるテクノロジー革命』(ステファノ・マンクーゾ著、
-

-
観光資源評価の論理に使える面白い回答 「なぜ中国料理は油濃いのか」に対して、「日本人は油濃いのが好きなのですね」という答え
中華料理や台湾料理には、油を大量に使用した料理が非常に多いですが、そうなった理由はあるのでしょうか
-

-
『芸術を創る脳』酒井邦嘉著
メモ P29 言葉よりも指揮棒を振ることがより直接的 P36 レナードバースタイン 母校ハー
-

-
ニクァラグア手話 聴覚障害の子どもたちが手話を作り出すまで
https://youtu.be/qG2HjmG0JGk https://www.bbc

