『近世旅行史の研究』高橋陽一 清文堂出版 宮城女子学院大学
公開日:
:
最終更新日:2025/05/18
出版・講義資料
本書の存在を知り港区図書館の検索を探したが存在せず都立図書館で読むことにした。期待通りの内容で、この著作を読んでいれば、私がkindleで電子出版した『人流・観光学概論』でも大いに参考にできたのにと残念であった。早速著者にメールをし、丁寧な返信をいただいた。
前書きに、旅行史を冠する本邦初の研究書とある。海外はともかく日本では観光史といわれる研究書は存在しなかったのかもしれない。その上で、高橋氏は旅行史研究の体系化に意欲を見せている。
旅が現代のように庶民文化の一つとして社会に定着した近世に、夥しい数の人々が旅に繰り出したことは、中世に比して圧倒的な残存数を誇る旅の記録(道中日記と紀行文)が物語っていると著者は記述する。ジョン・アーリ―等による『観光のまなざし』によれば、欧州では19世紀以前は、上流階級以外が労働や仕事と関係のない理由でどこかへ何かを見に行こうとするはまずなかった。従って、17-19世紀の旅の大衆化は、日本特有の現象と言えると記述する。
この理由を新城常三は、民衆の上昇、交通環境の好転、参詣の遊楽化、乞食参詣の横行、御師・宿坊の発達、講の発展、封建的規制の7点を挙げている。これに対して高橋氏は、平和な時代の到来(統一政権)、交通環境の整備(街道、宿駅、往来手形等)、経済の安定(貨幣経済等)、村落共同体の成立、宗教秩序の確立、文字社会の発展、の6点に整理している。
1970年代以降近世の旅の評価が、苦行性から遊楽性の強調へと変化している。新城常三の影響を受けてか、観光諸学においても参詣の観光化といった見方が一般化(伊勢参り、大明神へもちょっとより)してきたが、高橋氏は「信仰は建前で本音は観光」という理解に疑問を呈する。 「近世の旅イコール観光」は一部の要素(遊女、芝居見物等)を誇大化した見方であり、旅行者の記録から検証して判断しなければならないとし、道中日記に焦点を当てている。従来の研究が観光とは何かを定義することなく進められてきたゆえに、旅行者の精緻な記録の分析が置き去りにされたまま、研究者の判断で旅の表層が剥離され観光のレッテルが張られてきたとする。そこには旅が平和的なものと考えすぎる今日的風潮があるように思えると主張する。
高橋氏は、信仰か物見遊山かの二元論ではなく、近世参詣が、無意識的達成である身体的自己解放(信仰性重視)と、意識的達成である「精神的自己解放」(行楽性重視)が繰り返される過程であるとの原淳一郎の『近世社寺参詣の研究』における主張を評価しつつも、社寺参詣に偏らない更なる広範囲な論議が必要と主張する。地道な調査により収集された紀行文、道中日記の量が飛躍的に増加しており、様々な階層の旅の行動分析が可能となるだろうし、 信仰と観光の関係を極力あいまいにせず、観光を定義したうえで旅行者の記録を数多く、体系的に分析する必要があるとする。これが高橋氏の基本スタンスである。私が教科書で主張したこととも一致する。
第4章「道中日記の見える庶民の観光」での記述。日本では、南北朝を境にそれまでの話し言葉のカタカナ使用から書き言葉の漢字仮名交じり文普及への本格的シフトが見られた。文書主義の到来である。江戸幕府の統治は当初から町村に読み書きができる者がいることを前提としていた。(逆に明治になっても話し言葉で異なる地域の者の意思疎通は困難であったことが井上ひさしの戯曲でも紹介されている)。道中日記はなぜ記されるのかという問いには、後年の旅の参考となるためとする。では何故旅行者の主観的述懐が稀なのであろうか。道中日記では「言語に述しがたし」と、主観表現まで定型化されている。旅行者は感想を記述するに、特に印象的な場面に遭遇し、だれもが経験するような心理的境地に陥った場合、それを常套句で表現するとする。この現象は、欧州のグランドツアーでも見られることであるとする。近代マスメディアが発達する前の人間社会において自然の成り行きと高橋氏はするのである。この、庶民が常套句で表現した感動体験こそ「観光」と把握できるものとする。逆に、専門的まなざしから得られる、紀行文の著者らが体験する知的充足感は観光のたのしみではないとする。本物の探究が観光の形成の根底にあるというというような議論は正しくなく、多数の他者を必要とする大衆的ともいえるまなざしこそ、庶民のまなざしであるとする。観光と文化を一緒にしてもらっては困るという梅棹忠夫の言説を思い出してしまう表現である。
字句「観光」と字句「遊山」に関し、これまで、両者の関係に踏み込んで論じられていなかった。おそらくは同義とし、前近代の観光を遊山としたのであろうとする。高橋氏によれば、近世を通じて庶民の旅行の主目的は「信仰」にあり、その過程に「観光」がプラスされたのである。道中日記の記述には観光体験が現れている。芝居見物、遊所は旅の一部を形成するものに過ぎず、近世の旅の大部分は日々の旅程における町村の街並みや自然景観との対面である。数多くの旅行者の記録を読み込んだうえでの綿密な検証を経て、旅の性格は論議されなければならないと高橋氏は主張する。このことは、安易に観光の定義を論じる観光研究者への警告でもある。
「旅の対象と地域の視点」は私の教科書では観光資源論の範疇になるものである。青柳周一の「観光地化」の定義を紹介している。その定義は「大量の旅行者たちを恒常的に受け入れることを通じて再生産を維持し、併せてその内部の社会的秩序をも保ちえる能力を有するようになること」である。富士山麓の信仰登山集落を対象に、フリー客用宿泊斡旋の順回り留制度や女人登山近世の緩和等を分析している。旅行産業の村への一元管理である産業の自由化を制限する道理は「村の存立維持」に求められるが、その流れが緩められ、旅行者の誘致活動が近世的な秩序から離脱し、独立的事業として公的に容認される過程をたどり、観光地化の過程を考察している。旅行者の消費によって地域住民の多くが生計を維持しつつも観光産業が村の多くの制約を課せられていることを、観光政策論的に分析している。
関連記事
-

-
世界の運営を米国でなく中露に任せる 2023年6月7日 田中 宇
https://tanakanews.com/230607armenia.htm 5月25日、
-

-
【ゆっくり解説】【総集編】ガチで眠れなくなる「生物進化」の謎6選を解説/ミッシ ングリンク、収斂進化、系統樹、生命起源【作業用】【睡眠用】
https://youtu.be/ACEmkF1-g88
-

-
ソ連の北方四島占領作戦は、米国の援助のもとで実施されたという「発見」 『さらば!検索サイト』太田昌国著 現代書館
また私の頭の中で「歴史は新しく作られる」という例が増加した。表記のpp.77~79に記述されている
-

-
『インバウンドの衝撃』牧野知弘を読んでの批判
題名にひかれて、麻布図書館で予約をして読んでみた。2015年10月発行であるから、爆買いが話題の時代
-
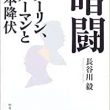
-
歴史認識と書評『暗闘 スターリン、トルーマンと日本降伏 』長谷川毅
日本降服までの3ヶ月間を焦点に、米ソ間の日本及び極東地域での主導権争いを克明に検証した本。
-

-
動画で考える人流観光学 観光資源、質量の正体は一体何なのか -質量の起源-
https://youtu.be/TTQJGcu-x3A https://
-
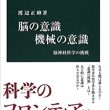
-
『脳の意識 機械の意識』渡辺正峰著 人間は右脳と左脳の2つを持ち,その一方のみでも意識をもつことは確かなので,意識を持っていることが確実である自分自身の一方の脳を機械で作った脳に置き換えて,両脳がある場合と同じように統一された意識が再生されれば,機械は意識を持ちうると結論できる.
Amazon 物質と電気的・化学的反応の集合体にすぎない脳から、なぜ意識は生まれるのか―。多くの
-

-
ふるまいよしこ氏の尖閣報道と観光
ふるまいよしこさんの記事は長年読ませていただいている。 大手メディアの配信する記事より、信頼できる
-

-
保護中: 蓮池透『拉致被害者たちを見殺しにした安倍晋三と冷血な面々』
アマゾン書評 本書を読むに連れ安倍晋三とその取巻き政治家・官僚の身勝手さと自分たちの利権・宣伝
-

-
書評『人口の中国史』上田信
中国人口史通史の新書本。入門書でもある。概要〇序章 人口史に何を聴くのかマルサスの人口論著者の「合
- PREV
- 『諳厄利亜大成』に見る、観光関連字句
- NEXT
- 『富嶽旅百景』青柳周一 観光地域史の試み

