観光資源の評価に係る例 米国の有名美術館に偏り、収蔵作品は「白人男性」に集中
芸術の本質が何であるかは、重要な哲学的問題のひとつである。これについて誰もが納得する答えはほぼ見つからないだろう。しかし、明らかなことがある。芸術は、それを育んだ社会の映し鏡になるということだ。
美術館の収蔵品は、その美術館が属する社会をどれほど反映するものだろうか?妥当な出発点は、収蔵品の作者の人口統計的多様性を調べることだ。しかしこれまで、そのような研究は実施されていなかった。
マサチューセッツ州にあるウィリアムズ大学のチャド・トパーズ教授らは、データマイニングとクラウドソーシングを使った研究で、米国全土の美術館収蔵品の人口統計的多様性を初めて浮き彫りにした。その研究結果は、襟を正させるものであった。
トパーズ教授らはまず、米国で最も権威ある18の美術館の収蔵品を調査した。対象となった美術館の多くは世界的にも屈指の規模と権威を持つもので、ワシントンDCのナショナル・ギャラリー・オブ・アート、ニューヨーク近代美術館、サンフランシスコ近代美術館などが含まれる。
最初に、各美術館のオンラインカタログをダウンロードした。それからデータマイニングで、各作品に携わったアーティスト、およびそのジェンダーや民族といった関連情報を収集した。
しかし、こうした情報は手に入らない場合が多い。たとえば多くの作品は作者が不明であり、その場合調査は手詰まりになってしまう。だがデータマイニングの結果、1万1000人を超えるアーティストの名前を突き止められた。データベースに同一のアーティストの名前が複数回現れた例があったため、個人を特定可能なアーティストの総数は最終的に1万108人となった。研究チームはこのデータを足がかりに、研究の次の段階、すなわちクラウドソーシングを使った調査へと移行した。
トパーズ教授らはアマゾン・メカニカル・タークを活用し、人間のクラウドワーカーに対して各アーティストのバックグラウンドの調査と、ジェンダー、民族、出身国、生年月日といったアーティストにまつわる10の質問への回答を依頼した。
各ワーカーにはアーティストの名前と、その情報のダウンロード先である美術館のWebサイトのリンクが提供されたほか、グーグルとウィキペディアを使ってさらなる情報を収集した。さらに研究チームは、標準データチェック手順を設定した。たとえば、結果が一致するように同じ調査タスクを少なくとも3人のワーカーに依頼するといったものだ。
研究の結果、米国の美術館に作品が収蔵されているアーティストには明らかな偏りがあることが示された。「アーティストの85%が白人で、87%が男性であることを突き止めました」とトパーズ教授は述べている。
一部の美術館は他と比べて多様性が著しく低かった。たとえばワシントン・ナショナル・ギャラリーだ。この美術館は1930年代にアメリカの銀行家アンドリュー・メロンが設立した。彼は自分のコレクションを収蔵品として同美術館に寄贈した。これには節税の意味もあったが、それ以来様々な人が作品を寄贈し、現在では北米で最大規模の美術館に数えられる。
しかし美術館の収蔵品が多様であるとは言えない。収蔵品の作者は白人が97%を超え、男性が90%を占めている。そして黒人あるいはアフリカ系米国人のアーティストの作品は皆無である。
モダンアート専門の美術館でも多様性はそれほど高くない。たとえばニューヨーク近代美術館では、収蔵品の作者の中で女性はわずか11%、アジア人は10%、黒人あるいはアフリカ系米国人は2%という割合だ。サンフランシスコ近代美術館の場合、女性は18%、アジア人は7%、黒人あるいはアフリカ系米国人は2%だった。
「ジェンダーについて言えば、全美術館のアーティスト全体の母数に占める女性の割合は12.6%でした」とトパーズ教授らはいう。「18の美術館全体で見た場合、ジェンダーと民族の上位4グループは、白人男性(75.7%)、白人女性(10.8%)、アジア人男性(7.5%)、ヒスパニック/ラテン系男性(2.6%)でした」。他のグループの割合はどれも1%未満だった。
とはいえ、このデータには注意すべき点がいくつかある。多くの美術館にはおびただしい数の作者不明の作品が収蔵されているが、こうした作品については作者の多様性を評価はできない。さらに特定可能なアーティストについても、その大部分は推測に頼ってデータを埋めざるを得なかった。当然ながら、アーティスト本人から情報を得られれば、より正確なデータが得られただろうが。
それでもこの研究は、美術館が収蔵品を拡大するうえでの重要な基準を提供している。
美術館の多様性がなぜこれほど低いのかは、興味深い問題だ。この問題が複雑であることは明らかだ。作品制作当時の社会問題、収蔵品に追加された時期、収蔵品の経時的変化が関連してくる。こうした問題はトパーズ教授らの研究範囲を超えている。
しかし同教授らは、各美術館の多様性と使命の間にある関係性を調査することで、その問題についていくつかの洞察を導き出している。「クラスタリングの結果、収蔵品の使命と多様性の間にある相関関係は非常に弱いことがわかりました。ここから考えられる可能性は、収蔵品の多様性を高めようとしている美術館は、使命の地理的・時間的な重視点を変えないまま取り組みを進めているのかもしれないということです」と、非常に言葉を選んだ言い方ではあるが。
見方を変えれば、こうした結果はより広いスケールでの多様性の欠如を反映しているに過ぎない。たとえば、美術館スタッフの多様性に関する最近の研究では、美術館スタッフに占める女性の割合が60%である一方、館長となれば女性の割合は43%にとどまることが示されている。似たようなバイアスは他の業界にも、そして社会一般にも現に存在する。
トパーズ教授らのアプローチが興味深いのは、こうした問題をさらに深く掘り下げる方法となるからだ。「私たちの使った方法論は、他の分野での多様性を広範かつ効率的に評価する方法としても使えます」と同教授らは述べている。
しかし差し当たって、この研究が美術館の世界に提示している含意は明らかである。すなわち、こと多様性に関しては大幅に改善の余地があるということだ。
(参照:arxiv.org/abs/1812.03899 : Diversity of Artists in Major U.S. Museum:アメリカの主要な美術館におけるアーティストの多様性)
関連記事
-

-
デジタル化と人流・観光(1)
通信の秘密が大日本帝国憲法及び日本国憲法に規定されていることもあり、長らく電気通信事業は逓信省、運
-

-
保護中: 学士会報No.946 全卓樹「シミュレーション仮説と無限連鎖世界」
海外旅行に行けないものだから、ヴァーチャル旅行を楽しんでいる。リアルとヴァーチャルの違いは分かっ
-

-
『休校は感染を抑えたか』朝日新聞記事
https://www.asahi.com/articles/ASP6J51TNP6CULEI0
-
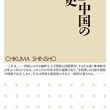
-
平野聡『「反日」中国の文明史 (ちくま新書) 』を読んで
平野聡『「反日」中国の文明史 (ちくま新書) 』に関するAmazonの紹介文は、「中国は雄大なロ
-

-
非言語情報の「痛み」
言語を持たない赤ん坊でも痛みを感じ、母親はその訴えを聞き分けられる。Pain-o-Meter Sc
-

-
『「日本の伝統」の正体』
現在、「伝統」と呼ばれている習慣の多くが明治時代以降に定着したと聞いたら驚く人も多いかもしれない
-
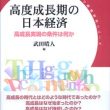
-
『高度経済成長期の日本経済』武田晴人編 有斐閣 訪日外客数の急増の分析に参考
キーワード 繰延需要の発現(家計ストック水準の回復) 家電モデル(世帯数の増加)自動車(見せびら
-

-
田岡俊二さんの記事 陸軍は「海軍の方から対米戦争に勝ち目はない、と言ってもらえまいか」と内閣書記官長(今の官房長官)を通じて事前に働きかけた。だが、海軍は「長年、対米戦準備のためとして予算をいただいて来たのに、今さらそんなことは言えません」と断り、日本は勝算のない戦争に突入した。
昔、国際船舶制度の件でお世話になった田岡俊二さんの記事が出ていたので、面白かったところを抜き書き
-
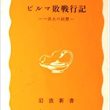
-
動画で考える人流観光学 『ビルマ敗戦行記』(岩波新書)2022年8月27日
明日2022年8月28日から9月12日までインド・パキスタン旅行を計画。ムンバイ、アウランガバード
-

-
山泰幸『江戸の思想闘争』
社会の発見 社会現象は自然現象と未分離であるとする朱子学に対し、伊藤仁斎は自然現象
- PREV
- 聴覚 十二音技法
- NEXT
- Quora 日本が西洋諸国の植民地にならなかったのは何故だと思いますか?
