『財務省の近現代史』倉山満著 馬場鍈一が作成した恒久的増税案は、所得税の大衆課税化を軸とする昭和15年の税制改正で正式に恒久化されます・・・・・通行税、遊興飲食税、入場税等が制定されたのもこの時であり、戦費調達が理由となっていた 「日本人が汗水流して生み出した富は、中国大陸に消えてゆきました」と表現
公開日:
:
最終更新日:2023/05/29
出版・講義資料, 路銀、為替、金融、財政、税制
p.98 「中国大陸での戦争に最も強く反対したのは、陸軍参謀本部
p.104 馬場鍈一が作成した恒久的増税案は、所得税の大衆課税化を軸とする昭和15年の税制改正で正式に恒久化されます・・・・・通行税、遊興飲食税、入場税等が制定されたのもこの時であり、戦費調達が理由となっていた 「日本人が汗水流して生み出した富は、中国大陸に消えてゆきました」と表現
馬場財政の混乱とその後
1936年(昭和11年)に広田内閣が発足すると馬場は満を持して蔵相として入閣。前任者の高橋是清蔵相が掲げていた公債漸減主義を放棄し、国防の充実と地方振興のためには増税と公債増発をもいとわない財政声明を出した(馬場財政)。またその政策遂行のために省内の人事刷新にも着手、長沼弘毅を蔵相秘書官にして新たな人事を練らせた。まず津島寿一次官を退任させ、軍部と強硬に渡り合ってきた賀屋興宣主計局長を理財局長に異動させたほか、石渡荘太郎主税局長を内閣調査局調査官へ、青木一男理財局長を対満事務局次長へと、それぞれ省外へ放出した[3]。
こうして馬場が初めて主導権を握って作成した昭和十二度一般会計予算案の概要は次の通りだった。
| 十二度予算案 | 前年度比 | |
|---|---|---|
| 歳出 | 30億3850万円 | 7億6650万円増(↑33.7%) |
| うち軍事費 | 14億0800万円 | 3億4900万円増(↑33.0%) |
| 公債発行額 | 9億5700万円 | 2億7700万円増(↑40.7%) |
| 増税額 | 4億1750万円 | — |
| 増収額 | 1億5480万円 | — |
増税はタバコの値上げなどで賄うことにした。こうして昭和十二度予算案が明らかになると、軍需資材の需要増を見込んだ商社が一斉に輸入注文を出し、輸入為替が殺到して円が下落、輸入物資の高騰を招く混乱を招いた。
特筆すべきは、日本が泥沼の支那事変・大東亜戦争に突入するのに必要な国家体制が出来上がった要因は、広田弘毅内閣の馬場鍈一蔵相にあるという趣旨のことを、大蔵省が公式の史書に記していることではないでしょうか。馬場鍈一は二・二六事件(1936)で暗殺された高橋是清に代わって蔵相に就任した人物ですが、彼は自由主義閣僚の排撃と軍拡路線を軸として広田内閣組閣を仕切り、蔵相就任後は統制経済と大増税・大軍拡を推進したのです。この路線を次の林内閣では、大蔵省・日銀・財界が一体となって修正しようとしましたが、結局軍事予算はほとんど削ることができませんでした。林内閣の次の第一次近衛内閣が成立してすぐに支那事変が発生、近衛は人気取りのために強硬に軍事介入を主張、そして大日本帝国は泥沼の戦争に沈んでいきました。
敗戦後の大蔵省は、占領前半期には占領軍や社会党内閣の社会主義者を巧みに排撃して大蔵省の組織を守り、占領後半期以降はアメリカの占領政策の転換によって大蔵省の伝統とする健全財政・自由主義経済を進めることが可能になるのですが、田中角栄以降その健全財政は崩れ、そして現在の1000兆円の負債という悲惨な財政状況に至ります。まさに「軍事と福祉は無限大の金食い虫」です。
恥ずかしながら僕はこの本を読むまで「竹下院政」をほとんど知りませんでした。外見から、田中角栄のほうが凄そうなイメージがありますが、実は竹下登のほうがかなり強固な体制を築いていたのですね。
「1976年成立の福田内閣以降、すべての内閣が田中角栄・竹下登という親中政治家の影響力下にあったので、小泉政権の誕生というのは、25年ぶりの親米政権が誕生したことを意味しています。」(p.236)
書評2
財務省の歴史を復習しようと思って買ったら、リフレ派のトンデモ本だった。
ありがちな陰謀論で纏められた本。
リフレ派の人以外は買わないほうがいいかな。
特に、若者は考えが偏るのでもうすこしマトモなものを読んだ方がいい。
書評3
良く分かっていない。勉強が足りない。それに尽きる。現役財務官僚より
関連記事
-

-
田岡俊二さんの記事 陸軍は「海軍の方から対米戦争に勝ち目はない、と言ってもらえまいか」と内閣書記官長(今の官房長官)を通じて事前に働きかけた。だが、海軍は「長年、対米戦準備のためとして予算をいただいて来たのに、今さらそんなことは言えません」と断り、日本は勝算のない戦争に突入した。
昔、国際船舶制度の件でお世話になった田岡俊二さんの記事が出ていたので、面白かったところを抜き書き
-

-
伝統も歴史も後から作られる 『戦国と宗教』を読んで
横浜市立大学の観光振興論の講義ノート「観光資源論」を作成するため、大学図書館で岩波新書の「戦国と宗
-
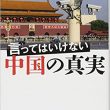
-
『言ってはいけない中国の真実』橘玲2018年 新潮文庫
コロナ禍で海外旅行に行けないので、ブログにヴァーチャルを書いている。その一つである中国旅行記を
-

-
脳科学 ファントムペイン
四肢の切断した部分に痛みを感じる、いわゆる幻肢痛(ファントムペイン)は、脳から送った信号に失った
-

-
『カジノの歴史と文化』佐伯英隆著
IRという言葉の曖昧さ p.198 シンガポールにしても、世界から観光客を集める手法として、
-

-
須田寛「国鉄改革を顧る」(くらしのリサーチセンター)メモと国の交通施策への感想
敬愛する須田寛氏の対談メモ。内容は既に知られていることではあるが、当事者が語ったものとしては数少ない
-

-
『官僚制としての日本陸軍』北岡伸一著 筑摩書房 を読んで、歴史認識と観光を考える
○ 政治と軍 「軍が政治に不関与」とは竹橋事件を契機に明治政府が作ったことである。そもそも明治国家
-

-
観光資源の評価に係る例 米国の有名美術館に偏り、収蔵作品は「白人男性」に集中
https://www.technologyreview.jp/s/117648/more-th
-

-
歴史は繰り返す遊興飲食・宿泊税とDMO論議
デスティネーションを含んだDMOなる言葉が独り歩きしている。私がカタカナ用語のデスティネーションを
-

-
シャマニズム ~モンゴル、韓国の宗教事情~プラス『易経』
シャーマン的呪術は筮竹による数字と占いのテキストを使った方法にかわった。このことにより特殊能力者でな

