『生成文法』書評
公開日:
:
出版・講義資料
「人間の言語習得は知性の獲得を証明するものではなく、単に種の進化の延長であるーー。」
はじめてこの考え方に触れたとき、正直なところ拒絶の感情を抱いた。
言語の獲得。これこそ人類が手に入れた最も価値ある道具であり、およそ人間が産み出したあらゆる文化・技術の成立の基盤にあって、いまや現代社会を支える最たるもの。私の言語観とはこのようなものだった。
しかしチョムスキーの主張は違った。言語はあくまで進化の過程で生まれ出でた産物にすぎぬという。言語の獲得は人類の不断の努力によってもたらされた成果などでは決してなく、そもそも新人に遍くプログラミングされた潜在的なものであるらしい。いわゆる普遍文法と呼ばれる概念である。
生成文法の面白さは、全人類に共通の言語能力が脳内に存在し(普遍文法)、個別の言語の獲得に際しては個別言語の言語構造に対応しながら脳内の言語能力が生成されたもの(生成文法)、という考え方をするところにあろう
言語と数学に共通して存在する「離散無限性」から、生成文法は数学的に啓発された理論であることは理解できるが、それと同時に、『純粋理性批判』の項831「数学での成功による理性の錯覚」や834「哲学と数学の違いー形式の違い」が思い起こされる。数学と言語を御大がどれほど同列に考えているかはわからなかったが、それでも「我々はひたすら間違った方向へと進んでいて、遅かれ早かれそのことが表面化して来るかも知れないという可能性は心に留めて置かなければならないと思う」という言葉からも、御大自身も生成文法に一抹の不安を抱えているのんだなと知った。
本書の内容は(私にとっては)決して平易ではないが、時間をかけて噛みしめるように読むと、読むたびにきっと何か大きなヒントが得られるように思う。私にとって初めて御大の思想に触れることができた本なので、感動が大きい。やはり御大は偉大だ。ものすごく。
4.説明的妥当性(P78)
無意識的な言語知識を説明するには母語話者の内観、直感によらざる得ません。つまり母語話者が違和感を感じるか否かということです(記述的妥当性とか言っているやつです)。日本語の「私は彼に本をくれません」が変で、「彼は私に本をくれません」はいいと感じるみたいにです。チョムスキー自身、話者の直感に頼ることの科学的根拠はないと認めています(P65)。本人が認めていないなら、私だって認めないよ(笑)
子どもは非文も含む一次言語データから正しい文を選択します。その上で重要なのは子どもは一次言語データの中の何が正しい文なのか知っている必要があります。生得的に。普遍的に。生成文法と言われる。これがいわゆる「説明的妥当性」というやつです。その拠り所は母語話者の直感です(P79)。しかしチョムスキーはこれに期待するのは現段階では非現実的だとも言っています(P79)。なんじゃ、それは。。。生成文法は根拠のない仮説であり、その論拠は結局は直感です。直感に頼っていては科学なんて言えません。
関連記事
-
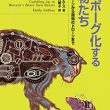
-
『サイボーグ化する動物たち 生命の操作は人類に何をもたらすか』作者:エミリー・アンテス 翻訳:西田美緒子 白揚社
DNAの塩基配列が読破されても、その配列の持つ意味が分からなければ解読したことにはならない。本書の冒
-

-
「米中関係の行方と日本に及ぼす影響」高原明生 学士會会報No.939 pp26-37
金日成も金正日も金正恩も「朝鮮半島統一後も在韓米軍はいてもよい」と述べたこと 中国支配を恐れてい
-

-
『ミルクと日本人』武田尚子著
「こんな強烈な匂いと味なのに、お茶に入れて飲むなんて!」牛乳を飲む英国人を見た日本人の言葉である。
-

-
戦陣訓 世間が曲解して使用し、それが覆せないほど行き渡ってしまった例
世間が曲解して使用し、それが覆せないほど行き渡ってしまった例である。「もはや戦後ではない」は私の
-

-
観光立国から経済立国へ Recommendations with Respect to U.S.Policy toward Japan(NSC13/2)
この翻訳テキストは、細谷千博他『日米関係資料集1945~97』(東京大学出版会,1999)<当館
-

-
「元号と伝統」横田耕一 学士會会報No.937pp15-19
元号の法制化に求めた人々に共通する声は元号は「日本文化の伝統である」というものだった。 一世
-

-
『知られざるキューバ』渡邉優著 2018年
4年前のキューバ旅行のときにこの本が出版されていれば、また違った認識ができたとの思う。 カリ
-

-
国際収支の理解 インバウンド好調の原因
それでも円高にならないのはなぜか?「売った円が戻ってこなくなった」理由 https://www.
-

-
Quora ヒトラーはなぜ、ホロコーストを行ったのですか?
https://jp.quora.com/%E3%83%92%E3%83%88%E3%83%A9

