「世界最終戦論」石原莞爾
公開日:
:
最終更新日:2023/05/28
出版・講義資料
石原莞爾の『世界最終戦論』が含まれている『戦略論体系⑩石原莞爾』を港区図書館で借りて読んだ。同書の存在は多くの人が知っていると思うが、実際に読んだ人は多くないのであろう。コロナで時間もあり、読んでみることにしたが、正直言って宗教的な部分も多く、また論文と言えるものでもなく、内容よりもはやり石原莞爾という人物の著作であるということが同書を有名にしているのであろう。しかし、AMAZONのカスタマー書評の投稿はゼロであるからほとんど読者はいなくなっているのであろう。戦争史が大観されている記述は、素人の私には新鮮であったが、おそらく専門家には極めて教科書的なものなのであろう。例えば、フランス革命では兵器の進歩はなく、傭兵から徴兵という社会の変化が、持久戦から決戦戦争になったこと、ナポレオンの軍事的才能は年とともに発達したが、相手もそれを覚えてしまったことが記述されているが、その分野では当時から常識だったのであろう。1940年のドイツの快進撃である「第二次欧州大戦」に関する記述を読んでいると、その名称を含め他人事のように書かれており、石原莞爾クラスの意識でもまだ日本が本格的に巻き込まれていないことが実感できる。その決戦スタイルが今日の戦争の本質ではないという結論を述べているが、そのこともほぼ常識であったと思われるが、それだけになぜ真珠湾攻撃をしたのか理解に苦しむのである。戦闘群の指揮単位が時代を追い、大隊、中隊、小隊、分隊と次第に小さくなり、最後は個人、即ち国民と記述する。従って総力戦になるとする。石原莞爾は成層圏での決戦までは予測し、その先は4次元でわからないとするが、現代は個人を超えて、ロボットとヴァーチャルに近くなっている。極限まで行くと、戦争はなくなるが、闘争心はなくならないので、国家単位の対立がなくなるという。すなわち、世界最終決戦戦争のあと人口は半減するものの、持てる国と持たざる国が一つになるという。戦争の発達の極限が戦争を不可能にするというのは、キューバ危機を経験した現代人には理解しやすい。戦国時代を統一したのは兵器の進歩の結果だとする点もわかりやすい。兵器が使えないから、はなはだ迂遠な方法であるが言論戦で選挙を戦っているともいう。この点は現代の国際社会を考えると、米国軍事力が不十分で、言論戦ではないということが理解できる。石原は核兵器的なものを予想していたようであるが、その破壊力や放射能被害を創造する段階までには至っていない。当然でもあり、米国はビキニ環礁で島民に死の灰を降らせたわけである。明治維新後民族国家を形成するため他民族を軽視する傾向が強かったと記述し、シナ事変に否定的であるが、満州事変がシナ事変の引き金になっていることを思えば、素直に同意もしにくい。最終決戦は、ロシア、ドイツ、アメリカ、日本とするが、現代の常識では、アメリカと中国、あるいはインドが参加するということなのであろう。石原は、最終決戦がいつ来るかは、占いのようなものというものの、30年を想定している。決戦のため、日本は昭和維新を断行し、そのための国策の重要課題は東亜連盟結成と生産力の大拡充とする。東亜連盟は、明治維新の廃藩置県のように、民族協和であり、満州国建国の精神とする。日本国は盟主ではないが、天皇は盟主であると記述する。天皇否定をすることができないであろうから、このような記述になったのかもしれないが、英国植民地の独立後、英連邦の各国が元首にエリザベス女王にいただいたことを思うと、先見の明があったのかもしれない。産業大革命については、あらゆるものが容易に生産できる第二次産業革命が起きているとする。当時でもその感覚があったのであるから、今日から将来を想定すると、モノの生産は問題ではなくなるのかもしれない。石原はこの後、宗教論を展開するが、私の理解を超えており、割愛した。
関連記事
-

-
太平洋戦争で日本が使用した総費用がQuoraにでていた
太平洋戦争で、日本が使った総費用はいくらでしょうか?Matsuoka Daichi, 九州大学で経
-
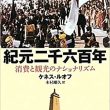
-
消費と観光のナショナリズム 『紀元二千六百年』ケネスルオフ著
今観光ブームでアトキンス氏がもてはやされている。しかし、観光学者なら「紀元二千六百年」を評価すべ
-

-
Quora 物語などによくあるように、中世ヨーロッパの貴族たちは国民から搾取してすごく贅沢な暮らしをしていたのですか?
中世に今日と同じ意味での「国民」はまだ存在しません。領主が農民を支配し、領主同士に主従関係
-

-
2023/7/18 【未来予測】地球の課題を解決するのは「人流ビッグデータ」だ ジオテクノロジーズ | NewsPicks Studios
https://newspicks.com/news/8641407/body/ 若い人達も人
-

-
『インバウンドの衝撃』牧野知弘を読んでの批判
題名にひかれて、麻布図書館で予約をして読んでみた。2015年10月発行であるから、爆買いが話題の時代
-

-
『結婚のない国を歩く』モソ人の母系社会 金龍哲著
https://honz.jp/articles/-/4147 書によれば、「民族」という単
-

-
ヨーロッパを見る視角 阿部謹也 岩波 1996 日本にキリスト教が普及しなかった理由の解説もある。
キリスト教の信仰では現世の富を以て暮らす死後の世界はあ
-
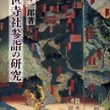
-
『近世社寺参詣の研究』原淳一郎
facebook投稿文章 「原淳一郎教授の博士論文「近世社寺参詣の研究」を港区図書館で借りて
-

-
『ざっくりとわかる宇宙論』竹内薫
物理学的に宇宙を考察すればするほど、この宇宙がいかに特殊で奇妙なものかが明らかになる。マルチバー
-

-
Transatlantic Sins お爺さんは奴隷商人だった ナイジェリア人小説家の話
https://www.bbc.co.uk/programmes/w3cswg9n BBCの
- PREV
- 『2050年のメディア』下山進
- NEXT
- 『1964 東京ブラックホール』貴志謙介

