『2050年のメディア』下山進
公開日:
:
最終更新日:2021/08/05
出版・講義資料
日本の新聞がこの10年で1000万部の部数を失っていることを知り、2018年4月より、慶應義塾大学総合政策学部特別招聘教授として、講座『2050年のメディア』を立ち上げた下山進氏による。Amazonの書評には「タイトルで気になって買いましたが、お世辞にも良い本とは言えません。まったく2050年が語られておらず、釣りタイトルとも言えるかもしれません。過去の歴史を辿っているだけで発見はほぼありませんでした」と厳しいものもあるが、その歴史も、読売を中心に、ヤフーが対立軸で、日経が補足的に登場している点で、朝日が出てこないところが面白い。私なりにメモする。まず読売の渡邉恒雄氏の大学合同説明会での「朝日を読むなら赤旗を読め」という言葉を紹介しているところで、学生どころか私まで驚かされてしまった。次に北区の新聞販売店主が学校の現場に入って日本の民主主義を支えてきた新聞を手に取ってもらうための活動をすると、「新聞の切り抜きの授業はできません」と2008年に言われたエピソードが出てくる。運輸省の広報室勤務時代、職員が毎朝、新聞の切り抜きを作っていたことを思い出し、どうなっているのかと思わされた。以下、読売、ヤフー、日経のデジタル化と人事の話を、エピソードを交えながら時代順に期日されている。デジタル販売と紙販売のウェイトの置き方がテーマになるが、ヤマトが三越の百貨店貨物輸送を切り捨てて宅急便に乗り出したことを思い出した。後から振り返れば当然の判断であっても、その時点でのステークホールだーの意向を抑えて乗り出すには、相当のリーダーシップがいる。読売新聞の拡販の武器はジャイアンツ戦の切符であったが、アメリカの銀行のそれはトースターであることも記述され、面白かった。アメリカの新聞の危機は日本より10年早く訪れていた。ニューヨークタイムズのことが紹介されているが、Uberの調査に行ったさいに、同社を訪問したことを思い出す。すでにデジタル化にかじを切った後であったが。デジタル部門で働く人の将来のキャリアパスがないということが最大の不満であり、問題であった。この問題点を「タイムズ・イノベーションレポート」で指摘され、機構改革が行われている。下山氏の作成したグラフをみれば、2011年を境に広告料収入より購読料収入が増加している。ページヴューにとらわれないで購読者数を増加させたのである。バズフィード等無料広告モデルは、FacebookやGoogleに負けてしまうのである。私が広報室勤務の時代は、朝刊の締め切り時間が朝の2時。ギリギリまで記者さんは取材をしていたから、家庭崩壊も珍しくなかった。朝日出身の細川総理はそれを狙って夜中に会見を行っっていた。コメの開放もその一例である。しかし、電子版が普及し、順次ネットに掲載されるようになると、新聞社も夜には人がいなくなっているようだ。デジタル化とグローバル化。ヤフージャパンは米国ヤフーとの関係でグローバル化ができなかったが、そのくびきが解かれたと最後に記述。しかし、メディアのグローバル化は、英語、中国語の世界もあり、私には想像もつかない。
関連記事
-

-
『兵士のアイドル』押田信子著 盧溝橋事件勃発で、新聞の報道合戦開始 慰問団ブーム
陸軍恤兵(ジュッペイ)部 日清戦争時に少なくともそのたぐいの組織はできていた?
-

-
『コロナ危機が浮き彫りにした日本の統治機構とその弱点』読書メモ 竹中治堅・手塚洋輔 公研no.695 2021.7
首相の権限は強くない例 安倍首相2020年4月6日にコロナ患者用の病床を5万床にすると発言、しかし
-

-
橋本健二 『格差と階級の戦後史』
この社会はどのようにして、現在のようなかたちになったのか?敗戦、ヤミ市、復興、高度成長、「一億総
-

-
QUORA 日本の歴代総理大臣ワースト1は誰ですか?
日本の歴代総理大臣ワースト1は誰ですか? 近衛文麿でしょう。彼は首相在任中に国運を左右する二
-

-
QUORA 北方四島問題でソ連は日ソ不可侵条約が有るも拘わらず、終戦直後参戦し北方四島を強奪しましたが、国と国の条約は形式だけで何の意味も持たないのですか?
https://qr.ae/py4JmS 北方領土問題の発端は、大東亜戦争(太
-

-
『「日本の伝統」の正体』
現在、「伝統」と呼ばれている習慣の多くが明治時代以降に定着したと聞いたら驚く人も多いかもしれない
-
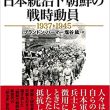
-
コロニアル・ツーリズム序説 永淵康之著『バリ島』 ブランドン・パーマー著『日本統治下朝鮮の戦時動員』
「植民地観光」というタイトルでは、歴史認識で揺れる東アジアでは冷静な論述ができないので、とりあえずコ
-
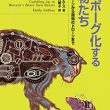
-
『サイボーグ化する動物たち 生命の操作は人類に何をもたらすか』作者:エミリー・アンテス 翻訳:西田美緒子 白揚社
DNAの塩基配列が読破されても、その配列の持つ意味が分からなければ解読したことにはならない。本書の冒
-

-
「元号と伝統」横田耕一 学士會会報No.937pp15-19
元号の法制化に求めた人々に共通する声は元号は「日本文化の伝統である」というものだった。 一世
-

-
『動物の解放』ピーターシンガー著、戸田清訳
工場式畜産 と殺工場 https://www.nicovideo.jp/watch

