観光立国から経済立国へ Recommendations with Respect to U.S.Policy toward Japan(NSC13/2)
この翻訳テキストは、細谷千博他『日米関係資料集1945~97』(東京大学出版会,1999)<当館請求記号A99-ZU-G54>pp.55~58からの転載であり、書式等の点で展示史料と一致しない部分があります。
米国家安全保障会議文書第13号の2
「アメリカの対日政策に関する勧告」(1948年10月7日)
NSC 13/2,”Recommendations with Respect to United States Policy toward Japan”(10/7/1948)
講和条約
1.時期および手続き
対日講和条約の手続き,および内容をめぐり明らかになった関係諸国間の見解の相違,ならびにソ連による侵略的共産主義勢力の膨張政策によって引き起こされた深刻な国際情勢に照らして,アメリカ政府は現時点では講和条約を推進するべきではない.もし連合国の間で一般的に受容された投票手続きに関する合意がみられるのであるならば,政府はそのような投票手続きのもとでの交渉を進める準備を行うべきである.われわれは,講和会議に実際に参加する前に,外交チャンネルをとおして,講和条約に望む主要点について参加諸国の多数の同意を得るように努めるべきである.この間,われわれは最終的な占領統治の解消に対する日本側の準備に関心を集中するべきである.
2.講和条約の性質
最終的に取り決められる条約は,できる限り簡潔で,一般的で,非懲罰的なものとすることをわれわれの目的とするべきである.このために,われわれは,条約締結までの間に解決しなければ,平和条約に含まれると予想される問題をできる限り多く解決するように努めるべきである.われわれの目的は講和条約で取り扱われる問題の数をできる限り少なくすることである.これはとりわけ財産権,賠償等といった問題に該当する.今後われわれの政策はこのことに特に留意して形成されるべきである.
安全保障問題
3.講和条約前の体制
この政策文書で示されている占領任務のしかるべき履行,および軍事的な安全保障と士気に合致するあらゆる努力が,日本国民に対する占領軍のプレゼンスの心理的影響を最小のものとするために支払われるべきである.戦術部隊と非戦術部隊の,とりわけ後者の兵力数は最少とするべきである.講和条約前における占領軍の配置と使用,日本経済からの補給を決定する上で,上記の点に充分な配慮が与えられるべきである.
4.講和条約後の体制
アメリカの戦術部隊は講和条約の発効まで日本において保持されるべきである.条約後の日本の軍事的な安全保障体制に対するアメリカの最終的立場は,講和交渉が始まるまで,明確に決められるべきではない.それは,その時点での支配的な国際情勢と日本において達成された国内的安定の程度に照らして,明確に決められるべきである.
5.琉球諸島
(この問題に関する勧告は別に提出される.)
6.海軍基地
アメリカ海軍は横須賀基地に関する政策を,現在享受している便益を講和条約後商業ベースでできる限り多く維持するに好ましいように形成するべきである.一方,沖縄については,われわれがそこを長期的に管理すると前提し,海軍基地としての沖縄の可能性を発展させるべきである.この政策は,もし講和条約後の日本の軍事的な安全保障体制に対するアメリカの立場の最終化の時点で,支配的な国際情勢がそのような行動を望ましいものとし,かつアメリカの政治目的に合致するのであるならば,横須賀といった海軍基地の保持を損なうものではない.
7.日本の警察機構
沿岸警備隊を含む日本の警察機構は現有の警察力の増員と再装備,そして現在の中央集権的な警察組織を拡充することで,強化されるべきである.
管理体制
8.連合国最高司令官
アメリカ政府は現時点で,管理体制の重要な変更を提案したり,それに同意するべきではない.したがってSCAPは形式的には既存のすべての権利と権力を維持するべきである.しかしながら責任は逐次日本政府の手に委譲するべきである.このために,アメリカ政府はSCAPに対して,その業務の範囲は可能な限り縮減され,それに伴って人員が削減されること,その結果SCAPの任務は大部分が,日本政府の活動に対する一般的な監督と幅広い政府の政策の問題をめぐる日本政府の高級レベルでの接触からなること,との見解を伝えるべきである.
9.極東委員会
(この問題に関する勧告は別に提出される.)
10.対日理事会
対日理事会はその機能を変更することなく,存続されるべきである.
占領政策
11.日本政府との関係
(前記8項を参照.)
12.国内の政治的・経済的変革
今後は日本国民が改革計画に同化することに重点が付与されるべきである.このためSCAPは日本側によって率先される改革措置が全体の占領目的に合致するのであれば,それを妨害するべきではないが,アメリカ政府はSCAPに対して,日本政府にこれ以上の改革立法を強いることのないように勧告すべきである.日本当局によって既に取られている,あるいは準備過程にある改革措置については,SCAPは日本政府への圧力を着実かつ控え目に緩和するように勧告されるべきであり,日本当局が自らの方法で改革を履行し,調整する上で,改革の基本を無効化,もしくは損なう時にのみ,介入すべきである.SCAPはもし日本側が非常に重大な意味を持つ行動に訴えた場合,緊迫した事情が許すのであれば,介入の前にアメリカ政府と協議を行うべきである.ある特定の改革については,上記の原則を具体化し,許容される調整の性質と程度に関するアメリカ政府の見解を示す明確な背景原則がSCAPに与えられるべきである.
13.追放
追放の目的は大部分が達成されたので,アメリカ政府はいまやSCAPに対して,日本政府にこれ以上の追放は考慮されていないこと,追放は次のような方針に沿って修正されるべきことを非公式に伝えるように勧告するべきである.
(1)比較的無害な地位を占めていたために追放,もしくは追放の対象となっている人物は政府,実業界,ならびに公的なメディアの地位へ復帰可能とするべきこと.
(2)在職した地位を基準に公的な生活から排除,もしくは排除の対象になっているそのほかの人物は個々の行動の基準によってのみ再審査を許容されるべきこと.
(3)最低の年齢制限を設定し,この年齢以下では公職に適する審査を必要とするべきではないこと.
14.占領コスト
日本政府の負担する占領コストは本文書で示されている,講和条約前の政策目標に合致するように最大限削減され続けるべきである.
15.経済復興
アメリカの安全保障上の利益を除いては,経済復興が今後のアメリカの対日政策の主要目標とされるべきである.この目標は規模は漸減しながらも数年にわたる物資供与とクレジットを想定するアメリカの援助計画をとおし,さらには商船隊の復活規定と並んで日本の対外貿易を再興するために既存の障害を除去し、日本の輸出の回復と発展を容易にするために、アメリカ政府のすべての関係する機関,省庁の活発な協力によって,達成されるべきである.日本の内外の貿易と産業を発展させる上で,私企業が奨励されるべきである.上記の点の履行に関する勧告は,他の極東諸国に対する日本の経済的関係を考慮して明確化されるべきであるが,アメリカ政府の関係機関と省庁の協議を経て,国務省と陸運省の間で決定されるべきである.われわれは日本政府に対して,復興計画の成功の大部分が,生産を拡大し,厳しい労働,最少の労働停止,国内の耐乏措置,そしてできる限り早急に均衡財政を達成する努力を含むインフレ傾向に対する断固たる戦いをとおして高い輸出水準を維持する日本側の努力にかかっていることを,明確にするべきである.
16.財産問題
SCAPは,連合国およびその国民の財産の回復,あるいは最終処理について,その過程を1949年7月1日までに実質的に終了するように促進することが勧告されるべきである.すべての財産問題はできる限り早期に,そして確実に講和条約締結の前に解決し,講和交渉を妨げないようにすることをアメリカの目標とすべきである.
17.情報および教育
a.検閲
日本に輸入される出版物の検閲はできる限り早く実施し,日本の出版物に対する事前検閲は停止するべきである.しかしながら,これはSCAPによる広範な事後検閲的な監督,および対諜報活動を目的とする郵便物検査の履行を妨げるべきではない.
b.ラジオ
アメリカ政府は適当な地点で,おそらくは沖縄に設置される送信局から日本に対する中波・長波放送の定時番組を放送するべきである.これらの番組はアメリカ側の考えに対する理解と評価を得る,と同時にできる限り広範な日本のラジオ聴取者を維持する目的で,注意深く準備されるべきである.
c.人的交流
日米の学者,教員,研究者,科学者,技術者の交流を強力に奨励するべきである.SCAPは承認を受けた日本人の文化・経済目的の海外渡航を許可する政策を継続するべきである.
18.戦争犯罪裁判
A級戦犯容疑者の裁判は終了しており,彼らは裁判の判決を待っているところである.全B級・C級戦犯容疑者については,われわれは訴追する意向のない者を釈放する目的で審査を継続し,早期に終了するように努めるべきである.他の者の裁判はできる限り早い時期に開始し,終了させるべきである.
19.日本の経済的な戦争能力の管理
真の平和目的の財と経済サーヴィスの日本国内での生産,日本への輸入,使用は次の場合を除いて制限なく許されるべきである.
a.日本の経済的な戦争能力は指定された戦略的原料の備蓄の許容量に制限を課すことで管理されるべきである.
b.日本の工業的非軍事化は戦争武器と民間航空機の製造の禁止,およびアメリカが工業戦争能力の削減に関して既に行った公約に照らして主張し得る工業生産に対する最小限の暫定的制限に限定されるべきである.
20.日本の賠償
(この問題に関する勧告は別に提出される.)
●賠償案が事実上無賠償に
ポーレー案(1946年11月最終案)は「産業施設9.9億円+軍事施設17.8億円」とかなり厳しい内容でした。
次に発表されたストライク案(1948年3月最終案)では「産業施設1.7億円+軍事施設14.8億円」と、産業施設に関してかなり緩和されています。
NCS13/2以降に発表されたジョンストン案(ドレイパー案;1949年3月最終案)では「産業施設1.0億円+軍事施設5.6億円」となって全体的に大きく削減されました。そして、この賠償案は最終的に破棄され、無賠償になります。
●集排法による分割実施会社の大幅削減
集排法(過度経済力集中排除法)は、財閥をはじめとする巨大独占企業を分割するための手続を定めた法律です。制定されたのは、NSC13/2の前である1947年12月です。
制定当時、この法律にしたがって財閥は解体されましたが、財閥以外に分割指定にあったは企業は当初325社にも及びました。
しかし、NSC13/2による対日政策の大転換があったため、実際に分割されたのは12社にすぎませんでした***。民間活力を大きく削ぐ政策は事実上大きく後退したのです。
このわずか6頁のNSC13/2によって、戦後日本経済の復興が「経済立国」へと大転換した点は、従来あまり明確には取り上がられていませんでした。この時期の歴史記述は政治史的にごちゃごやと描かれるのが普通なので。
しかし、アジアでの冷戦構造の大きな変化がなければ、このNSC13/2も登場せず、戦後日本経済の飛躍的な発展はなく、経済大国としての日本もなかった
関連記事
-
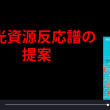
-
AIに聞く、甘利俊一博士の「脳・心・人工知能」を参考にした、『観光資源反応譜』の提案
人流・観光に関する学生用の教科書として、amazonのkindleで『人流・観光学概論』を出版してい
-

-
「若者の海外旅行離れ」という 業界人、研究者の思い込み
『「若者の海外旅行離れ」を読み解く:観光行動論からのアプローチ』という法律文化社から出版された書
-

-
『動物の解放』ピーターシンガー著、戸田清訳
工場式畜産 と殺工場 https://www.nicovideo.jp/watch
-

-
英国のドライな対外投資姿勢 ~田中宇の国際ニュース解説より~
私の愛読しているメール配信記事に田中甲氏の田中宇の国際ニュース解説 無料版 2015年3月22日 h
-

-
『元寇』という言葉は江戸時代になって使われ始めた
Wikiでは、「「元寇」という呼称は江戸時代に徳川光圀が編纂を開始した『大日本史』が最初の用例で
-

-
ジョン・アーリ『モビリィティーズ』吉原直樹・伊藤嘉高訳 作品社
コロナ禍で、自動車の負の側面をとらえ、会うことの重要性を唱えているが、いずれ改訂版を出さざるを得な
-
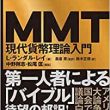
-
『MMT現代貨幣理論入門』
現代貨幣理論( Modern Monetary Theory, Modern Money The
-

-
錯聴(auditory illusion) 柏野牧夫
マスキング可能性の法則 連続聴効果 視覚と同様に、錯聴(auditory illu
-

-
「元号と伝統」横田耕一 学士會会報No.937pp15-19
元号の法制化に求めた人々に共通する声は元号は「日本文化の伝統である」というものだった。 一世


