🗾🎒三重県一身田 父親の納骨と道中の読書 『マヤ文明』『英国人記者からみた連合国先勝史観の虚妄』 2016年10月19日、20日
公開日:
:
最終更新日:2023/06/15
シニアバックパッカーの旅, 国内観光, 歴史認識
父親の遺骨を浄土真宗高田派の総本山専修寺(せんじゅじ)に納骨をするため、山代の妹のところに行き、一晩厄介になり、翌日一緒に車で三重の一身田まで向かった。往復の道中に読む本を図書館で借りた。いつも新書版を借りているが、今回は、ヘンリーSストークス『英国人記者からみた連合国先勝史観の虚妄』2013年祥伝社と青山和夫『マヤ文明』岩波新書2012年にした。後者は来月ガテマラ、メキシコ等に行く予定であるからだ。
伊勢の専修寺の通りの写真はなかなか風情がある。

納骨のお参りは、親鸞聖人の遺歯が納められている塚の前に建てられたお堂でまずお経をあげていただいた。
納骨が終了し、お寺の前で食事。
目方で値段をつけている面白い食堂であった。

さて、『英国人記者からみた連合国先勝史観の虚妄』である。
前者の著者は1938年英国生まれ1961年オックスフォード大学卒のかたで、日本人と結婚している。その著書の中に、ファイナンシャルタイムズ東京支局長で赴任してきた際、外務省報道課長が銀座のバーに案内をしてくれて、店の女の子をテイクアウトするように盛んにすすめられたこと、ホテルオークラの部屋に帰ったら、見たこともない女性が待っていたことを記述している(p.80)。オリンピックあたりからこの習慣もなくなったと記述している。買春防止法が制定されたからとあるが、同法制定は昭和31年であるから、少し混乱しているのであろう。
その延長上で、従軍慰安婦問題について、日本だけではないという視点で話を展開している。もちろん日本だけではなく、韓国での経験も紹介してバランスを取り、米軍もいかに兵士の性処理に心を砕いていたかを記述している。この話は、従軍慰安婦に代表される戦争と性の問題は、日本だけの問題ではないということで、韓国に反論することは、英国人であればできるところが面白い。日本軍がインドネシアでオランダ女性を従軍慰安婦にした問題もあり、全体としてこの話を日本人が否定をすると、火に油となってしまうのであろう。
南京大虐殺については、中国国民党の欧米マスコミへの広報戦略が大成功した面を取り上げて、ほぼ完全否定している。日本国粋主義者が涙を流して喜びそうな話である。戦時においての兵士の行為は、平時の感覚で論じることはできないと思っている。日本軍のほうが規律が良かったのかは、比較のしようがなく、国民党兵士の評判の悪さも、台湾では語り継がれている。東京裁判の公式評価にもつながってしまう問題であり、歴史問題ではなく、政治問題である。父親の手記にも日本軍の虐殺のことは記述されているから、戦地において虐殺行為が全くなかったわけではないであろう。今だってシリアで米軍が誤爆をして死亡者が出ているくらいである。勝者が敗者を裁く点について、勝者の立場から反対してくれるのは、東京裁判否定論者からするとありがたい話であろう。著者の原体験に、英国での米軍兵士のことがこの本に書かれているから、手放しでアメリカを評価していないことは推察できる。東京裁判は天皇責任を否定した点で私などは日本の国粋主義者は足を向けて寝てはいけないと思うのであるが、昭和天皇にシニカルな見方をする一部の人物(具体的には服部時計店の服部一郎氏)との会話を記述し、軍部の言いなりなるのは小学校教師程度の知性であったという同氏の発言を紹介する。幼児教育の重要性がわかっていない点で問題があるある発言であるが、それよりも昭和天皇の評価が低いのは、チャーチルが天皇の戦争責任を主張していたことと関係があるのかもしれない。
ユダヤ人を救った杉浦千畝氏のことに関連して、2万人のユダヤ人難民を旧満州国が受け入れるか否かの判断のさい、ハルピン特務機関長樋口少佐が入国の許可を関東軍参謀長の東条英機に求め了解を得ていることから、東条英機も評価すべきと記述している。ユダヤ人難民救済は、杉浦千畝氏以外にも多くの日本人が救済に寄与しているのであるが、その一方で多くの中国人を巻き込んであることも忘れてはいけないであろう。
次に『マヤ文明』である。
まず、マヤ文明とはスペイン人がつけた名前であり、まとまった「マヤ」というものはなかったようだ。次に、四大文明を紹介している。四大文明は、鉄器、半乾燥地帯の大河流域、大規模灌漑農業、大型家畜、統一王朝が特色とされる。これを四大文明史観とするが、1952年の高校の教科書で採用されて以来のものなのだそうである。ここにも歴史は後から作られるという事例が出てくる。マヤ文明は、鉄器は存在せず、石器である。農耕革命もおこらずして、定住革命が発生した。安定した食料供給ができれば定住化は可能であり、大規模河川も農業も不要なのである。観光学は定住社会を前提に組み立てられるから、ここにも新たな知識が得られることになった。ゼロの発見はインドより先であったから、高度の文明であった。現在でも800万人の「マヤ」諸語族が存在し増加しているそうだ。立派な現役の文化なのである。青山氏は、デズニーシーの「クリスタルスカルの魔宮」https://www.youtube.com/watch?v=INI0Z5t9CRE が誤ったマヤ文明観を与えてしまっていると嘆いている。この点になると、観光資源としてのマヤ文明は、真実かどうかよりも、興味をひくことができるかどうかで価値が決まるから、難しい問題である。なお、デズニーランドの歌のなかにデイビークロケットが出てくるが、デイビークロケットはメキシコ人からすれば大悪党なのであり、選挙民構成が変化すればそのうちに削除をされるかもしれない。日本と韓国もその程度のことと割り切って人物評価をすれば、観光資源にできるのであるが。
関連記事
-

-
シニアバックパッカー フィリピン(国連加盟国3か国目) 1977年(大阪陸運局時代)、2005年(パナウェイ棚田)、2017年(ライドシェア、スラム観光)2023年セブ
1977年4月鉄道監督局から大阪陸運局総務部企画課長に赴任した。鉄道監督局時代は、国鉄全線乗車券、当
-

-
🗾👜 🚖2018年1月22日23日 チームネクスト 沖縄タクシー・観光事情調査
午前中の大学の授業を終えて、羽田に直行。ぎりぎりのスケジュールでJALに搭乗。午後からは大雪の予報。
-

-
『カシュガール』滞在記 マカートニ夫人著 金子民雄訳
とかく甘いムードの漂うシルクロードの世界しか知らない人には、こうした動乱の世界は全く想像を超えるも
-

-
🌍👜シニアバックパッカーの旅 2018年5月19日 ヤムドク湖、チベット民家訪問
19日 https://photos.google.com/photo/AF1QipNpG1SIO
-

-
🗾🚖 2017年7月22日 チームネクスト 柳川 北原白秋は文化勲章を受けていない
2017年7月22日柳川を初めて訪れた。水郷柳川として、西鉄が大牟田線の旅客誘致に力をいれてきたとこ
-
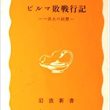
-
動画で考える人流観光学 『ビルマ敗戦行記』(岩波新書)2022年8月27日
明日2022年8月28日から9月12日までインド・パキスタン旅行を計画。ムンバイ、アウランガバード
-
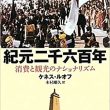
-
消費と観光のナショナリズム 『紀元二千六百年』ケネスルオフ著
今観光ブームでアトキンス氏がもてはやされている。しかし、観光学者なら「紀元二千六百年」を評価すべ
-

-
🌍🎒シニアバックパッカーの旅 グアテマラからマイアミ経由メキシコへ 2016年11月13日
13日はグアテマラのホテルを6時に出発。ランチボックスを準備してくれたが、制限区域内にはジュースがあ
-

-
🌍🎒シニアバックパッカーの旅 2020年2月2日~3日 パナマ経由で 五輪8🏳🌈㉛蘭領アルバ
Googlephoto 2020年2月2日~3日 アルバ https://photos.goo
- PREV
- 「北朝鮮の話」 平岩俊二 21世紀を考える会 10月13日 での講演
- NEXT
- 伊勢観光御師の会









