山泰幸『江戸の思想闘争』
社会の発見
社会現象は自然現象と未分離であるとする朱子学に対し、伊藤仁斎は自然現象から社会現象を分離し、独自の現象ととらえた。さらに社会現象を人為的に改変可能なものととらえたのが荻生徂徠である。丸山真夫は徂徠の思想に近代思想の萌芽を読み込もうとした。 社会学の基本的な問いに、社会秩序はいかにして可能なのか
アマゾン紹介
死んだらどうなるのか。「鬼神(霊魂)」は存在するのか、しないのか。「社会秩序」はいかにして生まれるのか。「道」をめぐる、儒家と国学者による「国儒論争」とは何だったのか。伊藤仁斎、荻生徂徠、太宰春台、賀茂真淵、本居宣長、平田篤胤ほか、近代社会の根本問題に果敢に挑んだ思想家たちの闘争を考察。「死」と「贈与」の言説への、思想史と社会学のアプローチによって江戸の思想を展望する、挑戦的な試み。
アマゾン書評1
「18世紀江戸期における新たな社会の胎動のなかで、儒家のなかに、『古学』という新たな立場を主張する者たちが登場します。まず伊藤仁斎の『古義学』として形成され、さらに仁斎に激しく対抗するかたちで、荻生徂徠の『古文辞学』が登場します。仁斎や徂徠によって、『道』という概念が重視され、深い思想的な意味を帯びた概念として、語り出されることになります。・・・徂徠は、『道』を『先王の道』とするのです。『先王』とは『聖人』のことであり、徂徠にとっては、『聖人=先王』とは『道』を制作し、これを人間にもたらした制作者のことです。これによって人間は文化を獲得し、人間として社会生活を営むようになったのです。つまり、『道』は『聖人=先王』によって、『与えられたもの』なのです。・・・徂徠は、鬼神(祖霊、霊魂)祭祀もまた、『聖人=先王』が制作したといいます。・・・『鬼神』もまた『鬼神祭祀』とうかたちで、『聖人=先王』が制作して人間に『与えたもの』、『贈与』なのです」。
「荻生徂徠の登場以前と以後で、江戸時代の学問の世界は一変したといわれています。徂徠は、日本思想史上、最も波紋を呼び起こした思想家の一人といっていいでしょう」。
「江戸期の思想において、社会現象は自然法則と未分離であるとする朱子学に対して、自然法則から社会現象を分離し、独自の現象として捉えたのが仁斎であり、さらに社会現象を人為的に改変可能なものとして捉えたのが、徂徠なのです」。
「徂徠の弟子の太宰春台は、徂徠が説き始めた『道』の学説を受け継いで、さらに徹底化を図った儒家といえます。春台は『弁道書』という道を説いた書物の中で、日本には元来『道』というものはなく、中国から聖人の教えが伝わって、はじめて日本に『道』というものができたと述べています。つまり、日本は本来、自然状態にあったが、中国から聖人の教えがもたらされた結果、はじめて文化をもったのだ、と主張するのです」。
「古代の日本が『自然状態』であり、『聖人の道』によって、古代の日本は『自然状態』から脱して、『文化』を獲得したという考え方を、快く思わない人たちが出てくることになります。国学者たちです。これに強く反発したのが、賀茂真淵です」。徂徠や春台らの「道」の言説に対する反発から、それとの差異化を通じて、国学的言語が形成され、多くの儒家や国学者を巻き込んだ、いわゆる「国儒論争」が展開されていきます。
真淵の弟子であり、篤胤の師匠に当たる本居宣長は、「中国では『道』という言葉をわざわざ言葉に出していうのは、それだけ乱れていたので、道についてしつこくいう必要があったというのです。・・・宣長における『道』は、人々の行為を外から規制するために為政者が後から作為的に設けたものではなく、『皇国(日本)』においては、最初からすでに実現されているものなのです。この点で、真淵の『道』の捉え方とも通じるところがあります。・・・宣長は、まず異国が昔から乱れていたといいます。そして、狡賢くて、人をうまく手懐けて騙して、人の国を奪い取り、また人に奪われないことばかりを考えて、人々を政治的にうまく支配しようとする者を、中国では、『聖人』というと述べるのです。宣長は、聖人をはっきりと否定的に捉えていることがわかります。宣長は、自己の利益のために人々を騙して支配する作為と欺瞞に満ちた人物として聖人を捉えているのです」。徂徠の「聖人」と宣長の「聖人」とは、正反対の捉え方をされているのです。そして、宣長の日本中心主義的な発想を極端なまでに推し進めたのが篤胤と言えるでしょう。本書のおかげで、江戸時代に展開された激烈な論争の全体像を俯瞰することができました。
アマゾン書評2
漢文訓読を導入してほぼ確立した超優秀な学者貴族官僚・吉備真備の話は大いに役立ったが、その他の話題は、あまりに思索的すぎて、お勧めできない。
なお、著者は、若干の偏りはあるが優秀な国学者であり、かつ、あの、どおしようもない超国粋主義者の本居宣長を正しく評価しているものの、その欠点を極限までもっていってしまった平田篤胤をなぜここまで評価するのか、全く理解できないところである。著者は、あまり論議をこね回しすぎて、混乱しているのではないかと危惧する次第である。
関連記事
-

-
『日本が好きすぎる中国人女子』桜井孝昌
内容紹介 雪解けの気配がみえない日中関係。しかし「反日」という一般的なイメージと、中国の若者
-

-
Quoraに見る歴史認識 太平洋戦争(大東亜戦争)は侵略戦争だったのでしょうか?
侵略には外交用語として明確な定義があります。計画に基づいて軍事作戦を先制発動することです。
-
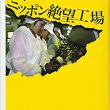
-
『ルポ ニッポン絶望工場』井出康博著
日本で働く外国人労働者の質は、年を追うごとに劣化している。 すべては、日本という国の魅力が根本のと
-
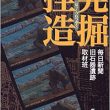
-
『発掘捏造』毎日新聞旧石器遺跡取材班
もう20年も前の事であるが、毎日新聞取材班の熱意により旧石器遺跡の捏造事件が発覚した。その結果、
-

-
国際観光局ができたころ 満州某重大事件(張作霖爆死)と満州事変
排日運動が激しくなってきていた。当時は関東軍は知らず、河本大佐数人で実行。満州の出先機関はバラバラ
-
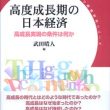
-
『高度経済成長期の日本経済』武田晴人編 有斐閣 訪日外客数の急増の分析に参考
キーワード 繰延需要の発現(家計ストック水準の回復) 家電モデル(世帯数の増加)自動車(見せびら
-

-
園田、石原も認識していた尖閣問題棚上げ論 川島真『21世紀の「中華」』を読んで
気になったところを抜き書きする。 外国人犯罪者の数で中国人の数が多いが、在留率が30%と多い
-

-
Quoraに見る歴史認識 終戦後に当時のソ連は、どうして北海道に侵攻しなかったのですか?
終戦後に当時のソ連は、どうして北海道に侵攻しなかったのですか? 回答を先に書けば、米国との間
-

-
Quoraにみる歴史認識 日露戦争で日本は英米に膨大な借金をしてますがどうやって返済したのでしょうか?
ご質問文に「英米」とありますが、高橋是清の求めに応じて日本の戦時国債を購入して支えたジェイコブ・ヘ
-

-
学士会報926号特集 「混迷の中東・欧州をトルコから読み解く」「EUはどこに向かうのか」読後メモ
「混迷の中東」内藤正典 化学兵器の使用はアサド政権の犯行。フセインと違い一切証拠を残さないが、イス
- PREV
- 宇田川幸大「考証 東京裁判」メモ
- NEXT
- 『創られた伝統』


