QUORAにみる観光資源 なぜ、現代に、クラシックの大作曲家が輩出されないのですか?大昔の作曲家のみで、例えば1960年生まれの大作曲家なんていません。なぜでしょうか?
とっくの昔に旬を過ぎている質問と思われますが、面白そうなので回答します。
一般的に思われている「クラシック」とは、ヨーロッパの市民階級を対象とした芸術音楽です。古典派の時代くらいから市民階級を対象とした「コンサート」が行われるようになり、レパートリーとして交響曲をはじめとする器楽曲が数多く書かれ、19世紀を通じて隆盛を極めました。はじめは存命の作曲家の作品ばかりが演奏されていたようですが、コンサートの数が増えるにつれ、曲が足りなくなり、「すぐれた作品であれば、故人のものでも演奏しよう」ということになります。数々の音楽雑誌が創刊され、音楽に関する言論が盛り上がります。シューマンが創刊した「新音楽時報」が代表格で、これは現在も刊行されています。音楽雑誌の主要な関心は、「未来に遺すべき優れた音楽作品の選定」でした。現在コンサートのプログラムを飾る数々のクラシックのレパートリーは、こうした中で選ばれてきたものです。バロック時代の作品はいわば「前史」として、後に発掘されたものです。メンデルスゾーンがバッハを発掘した例はあまりにも有名です。
作曲家たちは、こうした中で勝ち残りつつ、世俗的な成功をおさめようとしのぎを削っていました。みんな「世界で自分にしか書けない、鮮やかな個性」を目指していた、といっていいと思います。が、19世紀後半に爆発的な数の作曲家が出て、個性を追求しようにも、もはや音の組み合わせが尽きつつあるのではないか…その問題から逃れようがなくなっていきました。そもそもオクターブに12音しかないものを、多くの作曲家が競争して曲を書いて行ったら、可能性を汲みつくしてしまうのではないか…そういう種類の問題です。
その問題の処し方は、ヴァーグナーが切り開いた半音階和声の道や、国民楽派が切り開いた民族性追求の道、フランス人たちが切り開いた旋法や非機能的和声の活用の道でした。
20世紀に入っても、少なくとも第一次世界大戦まではこの延長上で数々の作曲がなされていました。民族性追求はジャズやガムランなど非ヨーロッパ音楽への関心を生み、そのよって立つ民族を広げながら続いていきます。フランス人たちの切り開いた道も、それはそれで継承されていきます。
が、半音階和声の追求の中からシェーンベルクが無調の道を開き、一般の聴衆と決別する傾向が出て来ます。複調を多用した作品でスキャンダルとなったストラヴィンスキーの春の祭典も、同じように言えるかもしれません。新しい作曲技法の追求は、第1次世界大戦前の段階で、「クラシック」の前提であった「市民階級を対象とした芸術音楽」から外れ始めたのです。簡単に言えば、「最新の技法で曲を書くと、市民に聞いてもらえない」「市民を置き去りにしないと、最新の技法を試せない」という状態に陥ったのです。
第1次世界大戦以降、ロマン的な感覚が毛嫌いされ(民族主義を盛り上げる=ナショナリズムに訴える=戦争に結果的に協力する部分があったのは否定できません)、クラシック界は新古典主義の時代となります。シェーンベルクは十二音技法を開拓しますが、これも言ったら無調のシステム化であり、理性的です。中には新古典主義の語法を適度に取り入れつつもロマン的な曲を書いた人もいますし(バーバーとか)、ルネサンス期の舞曲や民謡を編曲した懐古的な作品も見られますが、例外的です。
ただ、この新古典主義ですが、形式への回帰とロマン的な感情表現の否定、下手をするとオリジナリティの否定(民謡と現代的な作曲技法を結びつけたりしています)ですので、大物は出て来にくいです。最大の大物はラヴェルとバルトークだと思いますが、フランス6人組といっても一般的には知られていないでしょうし、コダーイやカゼッラやマリピエロも通常は知らないでしょう。
何より、第1次世界大戦が、それまでの「未来に遺すべき優れた音楽作品の選定を行う市民階級の共同体」に物理的・経済的に深刻なダメージを与えたことは間違いないでしょうし、それまでのようにナイーブに共同体の共同主観を信じることも難しくなったでしょう。ナイーブに自国の素晴らしさと誇りを信じた結果、破局的な大戦に至り、ドイツ・ロシア・オーストリア・オスマンの4帝国は解体となりました。フランスは人口構成が変わるほどの大ダメージです。ロマン派音楽の前提だった「世界で自分にしか書けない、鮮やかな個性」という理想自体が、技術的にも理念的にも疑わしくなったと言えるのではないでしょうか。
悪いことは続くもので、ソ連では社会主義リアリズムが叫ばれるようになり、音楽は大衆に奉仕するものとして、人為的に古めかしい様式で書くことを強制されるようになりました。ナチスは実験的な音楽とユダヤ人の音楽を抑圧しつつ東方に勢力を広げました。ここでもロマン派音楽の前提だった「世界で自分にしか書けない、鮮やかな個性」を試みるための自由が奪われたわけです。結局、そうした自由が残っているのは実質アメリカだけのような状態になりました。ガーシュウィンやグローフェやコープランドやバーバーやケージなど、アメリカだけがかなり元気に見えるのは、絶対に偶然ではないでしょう。
要するに、戦間期の段階で、すでに「クラシック」を生み出してきた種々の条件が大幅に崩れています。オリジナリティの余地は狭まり、オリジナリティ自体の正当性が疑われ、クラシックを支えてきた市民階級の共同体は物理的・経済的・精神的に力を失い、やがては全体主義国家による抑圧も行われるようになった、ということです。こうした時代に、ベートーヴェンのような素朴な市民共同体の信奉者や、ショパンのような詩人や、ヴァーグナーのような誇大妄想狂が伸び伸びと作曲できたでしょうか。
さらに、凄惨な独ソ戦はドイツ以東を滅亡の淵に突き落とします。一応戦勝国のはずのフランスも、ドイツに率先して協力した者を糾弾するなどで戦後は内輪もめです。クラシックを支えてきた市民階級の(ある意味のんきな)共同体など、大陸諸国では崩壊したものと思われます。おまけに戦後は鉄のカーテンで、東欧は全てソ連の影響下となり、抑圧体制となります。社会主義リアリズムは粛清を伴う形になり、自由な創作は生命の危険を伴う状態にすらなりました。社会主義リアリズムとは「強制されたロマン主義音楽や民族主義音楽」と言えると思います(ショスタコーヴィチやハチャトゥリアンを聞けばわかります)。ソ連の音楽界は、西側諸国から離れ、ガラパゴス的な世界となりました。
対抗上、西側諸国では、いわゆる前衛音楽が各国政府によってバックアップされ、自由のアピールとされました(ロマン主義・民族主義・新古典主義のどれをやっても、社会主義リアリズムと被ってしまいます)。前衛音楽は新しくていいのですが、一般市民にアピールする力はありません(ヨーロッパの音楽愛好者が、「前衛音楽は、風変わりな音が古い城の大広間などで演奏される様が最初は非常に新鮮で面白かったが、すぐに飽きた」などと書いています。一番好意的な反応でこのくらい、と考えられます)。受け取り手の共同体が崩壊し、作品をつくる側が市民階級から背を向けていたとしたら、巨匠が出てくる余地があるわけがないではありませんか。
一応、メシアンだのブーレーズだのケージだのライヒだのと、主要な作曲家を挙げることはできますが、おそらく一番影響力があって楽壇をリードしていたブーレーズが、ある時期からほとんど作曲をしなくなり、指揮ばかりするようになってしまったのが象徴的です。要するに、「クラシック」を生み出してきた種々の条件が完全に崩れてしまったのです。質問に対する直接のお答えは、これです。
戦後に起きた大きな変化としては、世界の中心がヨーロッパからアメリカに移ったこと、旧体制(ナショナリズム的な国家体制)が若者世代から各国で猛反発を食らい無視できなくなったこと、貴族主義やエリート主義の崩壊(といって悪ければ地下化)などがあるでしょうが、これもすべてクラシックの首を絞めています。代わりに台頭した音楽が、アメリカ起源のロックで若者対象の音楽であることが象徴的です。
それでもクラシックに関心のある層は、クラシックの新作ではなく、指揮の巨匠によるレコードの演奏の違いに関心を寄せるようになりました。が、徐々に生演奏のハッタリ要素は自粛され、レコードにしても傷のない演奏をコンサートで行うのが当たり前になり、クラシックは新作という意味でも、演奏という意味でも、活力を削がれる形になっていきます。1960年代くらいのライブ録音など聴くと、相当にロマン的な無茶をやっていて楽しいですし、各国のオーケストラにもまだ明確にエスニシティがありますが、70年代以降どんどんそれは消え失せていきます。演奏に全く傷のない録音とそれとそん色ない生演奏の極北は、シャルル・デュトワとモントリオール交響楽団だと思いますが、あれはあれで尖った個性だったと思います。しかし、もはやその路線もありません。クラシックのCDは、どれをとっても似たような穏健な解釈とそこそこ傷のない演奏により、聴く人の「既存の曲のイメージ」をほぼ再確認するだけのものになっているように思います。おまけに値崩れも甚だしく、昔の巨匠と世界的オーケストラの録音が、500円くらいで投げ売りされていたりします。
それでも、宮廷料理に起源のある高級料理が滅びないのと同様、クラシック音楽が絶えることは一応ないでしょうし、また映画音楽などのネタ元として、クラシック音楽は活用され続けるでしょう。もしかしたら、一応西欧文明の影響下にある国々に普遍的に流行する音楽も書かれる余地はあるかもしれません(クラシックではありませんが、Let it goが世界43か国語に訳されて歌われたのはなかなかエポックメイキングだと思います)。が、その時に使われる作曲技法は絶対に最新の前衛的な技法などではなく、多くの人にわかりやすいロマン的あるいは民族的あるいは新古典的な様式でしょう。
クラシック的(あくまで「的」ですよ)な作曲法で大流行した例としては、パーシー・フェイスとか、ヘンリー・マンシーニとか、ポール・モーリアとかが挙げられるでしょう。映画音楽は後期ロマン的な様式で書くというルールがハリウッドで確立されており、ジョン・ウィリアムスはその巨匠です。日本だと久石譲ですね。こうした音楽は、おそらく今後も書かれ続け、一定程度の人気を得る曲も出てくると思われます。
が、クラシックの系譜に直接つながる音楽=ヨーロッパの市民階級を対象とした芸術音楽で、作曲家が世界で自分にしか書けない鮮やかな個性を目指して最新の技法で書き、多くの人に受け入れられた上、歴史の審判を経て残る音楽=はもはや、存在しえないと思います。
関連記事
-

-
三谷太一郎『日本の近代とは何であったか』なぜ日本に資本主義が形成されたか
ちしまのおくも、おきなわも、やしまのそとのまもりなり
-

-
ピアーズ・ブレンドン『トマス・クック物語』石井昭夫訳
p.117 観光tourismとは、よく知っているものの発見 旅行travelとはよく知られていな
-

-
現代では観光資源の戦艦大和は戦前は知られていなかった? 歴史は後から作られる例
『太平洋戦争の大誤解』p.183 日本人も戦前はほとんど知らなかった。戦後アメリカの報道統制
-
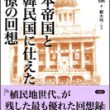
-
任文桓『日本帝国と大韓民国に仕えた官僚の回想』を読んで
まず、親日派排斥の韓国のイメージが日本で蔓延しているが、本書を読む限り、建前としての親日派排除はなく
-

-
『庶民と旅の歴史』新城常三著
新城 常三(1911年4月21日- 1996年8月6日)は、日本の歴史学者。交通史を専門とした。1
-
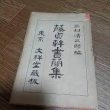
-
中国文明受入以前は、藤貞幹は日本に韓風文化があったとする。賀茂真淵は自然状態、本居宣長は日本文化があったとする。
中国文明受入以前は自然状態であったとする賀茂真淵、日本文化があったとする本居宣長に対して、藤貞幹
-
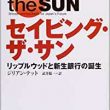
-
『セイビング・ザ・サン リップルウッドと新生銀行の誕生』ジリアン・テット 武井楊一訳
バブル期の金融問題に関する書籍は数多く出版され、高杉良が長銀をモデルに書いた『小説・ザ・外資』はハ
-

-
『近世旅行史の研究』高橋陽一 清文堂出版 宮城女子学院大学
本書の存在を知り港区図書館の検索を探したが存在せず都立図書館で読むことにした。期待通りの内容で、
-
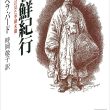
-
イサベラバードを通して日韓関係を考える
Facebook投稿文(2023年5月21日) 徳川時代を悪く評価する「薩


