『パッケージツアーの文化史』吉田春夫 草思社
港区図書館の新刊本コーナーにあり、さっそく借り出して読んだ。JTBでの実務経験が豊富な筆者であり、材料も多く読み応えのある内容である。「あとがき」にもあるように、パッケージツアーを正確に伝えるためには旅行あっせん業法が何故1971年に旅行業法へと全面改正されたかを踏み込んで記述する必要があるとなっている点で、私と問題意識を共通する部分が多い。主催旅行等の専門用語も詳しく取り上げる必要があるとの認識を示している。旅行代理店というマスコミ用語へのクレームも同じ問題意識である。
しかし、私の問題意識と大きく異なるところは、旅行業法だけではなく、鉄道事業法、国際観光ホテル整備法等の実サービス法との関係を総合的に理解する必要があるという点で、本書ではほとんど記述がなされていないところである。同世代であるので、国鉄の商品を取り扱っていたことがうかがえるが、その当時は国鉄運賃は国有鉄道運賃法により法定されており、器用に旅行業者が取り扱えるようにはなっていなかった。しかも運送契約内容は、現在でも、鉄道営業法で規定されているから、本書を読んでいても、その点への問題意識のずれがあると感じてしまうのである。
日本の旅行業法の特徴に、いわゆる単品パックといわれるものがある。欧米では、パック旅行は航空制度から始まっており、複数のサービスの組み合わせと出発から帰宅までの時間間隔が24時間を超えるというルールがある。これは現在の日本の国内航空会社でも生きているルールである。従って単品パックは、国鉄制度が生み出したものであり、わが国特有のものである。この点への言及がなされていない点で、物足りなさを感じてしまう。
さらに、踏み込んでいえば、本書では条文に即して解説しており、条文に即するとすれば、日本の旅行業法は、利用運送、利用宿泊について規定している。しかしながら、実体としてもその商品は存在せず、標準約款も準備されていない。この点が利用運送が主体の物流界と大きく異なる点である。ポストコロナの商品としては避けて通るべきではないであろう
なお、戦後、大事なお客である米国人に対する悪徳業者の取り締まりは、米軍のにらみが聞いており日本の法律は必要がなかったのであるが、1952年施政権返還に伴い貴重な外貨獲得政策のため、インバウンド向けの、旅行あっせん業法が制定されたのである。1971年に旅行業法に全面改正されたのは、同年にインバウンドの数はアウトバウンドの数を上回り、日本人海外旅行者の保護が重要な政策になったからである。
関連記事
-

-
人流・観光学概論修正原稿資料
◎コロナ等危機管理関係 19世紀の貧困に直面した時、自由主義経済学者は「氷のように
-

-
戦陣訓 世間が曲解して使用し、それが覆せないほど行き渡ってしまった例
世間が曲解して使用し、それが覆せないほど行き渡ってしまった例である。「もはや戦後ではない」は私の
-
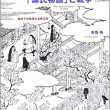
-
『「源氏物語」と戦争』有働裕 教科書に採用されたのは意外に遅く、1938年。なぜ戦争に向かうこの時期に、退廃的とも言える源氏物語が教科書に採用されたのか
アマゾン書評 源氏物語といえば、枕草子と並んで国語教科書に必ず登場する古典である。
-

-
新語Skiplagging 「24時間ルール」と「運送と独占の法理」
BBCの新しい言葉skiplagging
-

-
旅資料 安田純平『ルポ 戦場出稼ぎ労働者』集英社新書
p.254「戦火のイラクに滞在し、現地の人々の置かれた状況を考えれば自分の拘束などどういうことでも
-

-
韓国・済州島から中国人観光客が激減。次期大統領選の結果次第では回復の兆しも 2017.04.10
https://hbol.jp/136104 韓国報道によれば、THAAD(高高度防衛ミサイル
-
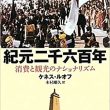
-
消費と観光のナショナリズム 『紀元二千六百年』ケネスルオフ著
今観光ブームでアトキンス氏がもてはやされている。しかし、観光学者なら「紀元二千六百年」を評価すべ
-
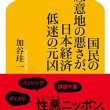
-
『国民の底意地の悪さが、日本経済低迷の元凶』 (幻冬舎新書) 加谷 珪一
題名にひかれて、三田図書館で借りて読む。表題は営業用に編集者がつけたのであろう。先進国が消費拡大
-
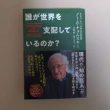
-
ノーム・チョムスキー著『誰が世界を支配しているのか』
アマゾンの書評で「太平洋戦争前に米国は自らの勝利を確信すると共に、欧州ではドイツが勝利すると予測
-

-
「太平洋戦争末期の娯楽政策 興行取締りの緩和を中心に」 史学雑誌/125 巻 (2016) 12 号 金子 龍司
本稿は、太平洋戦争末期の娯楽政策について考察する。具体的にはサイパンが陥落した一九四四年七月に発
