南米「棄民」政策の実像 遠藤十亜希著 岩波現代全書 最も南米移民を排出したのが最貧困地帯たる東北ではなく北部九州~山陽ラインだったのは何故か?
公開日:
:
最終更新日:2023/05/29
出版・講義資料
19世紀末から20世紀半ばまで、約31万人の日本人が、新天地を求めて未知の地ラテンアメリカに移住した。その多くは、日本政府が奨励・支援した「国策移民」だった。従来人口増加や貧困への対策とされてきた日本の移民政策が、「不要な人々」を国内から排除し、海外で利用するためのものであったことを明らかにする。
書評1
在米日本人研究家の長期にわたる研究の成果。膨大な資料を掘り起こして南米国策移民の歴史からニッポンの矛盾をあぶりだす、この本で最も興味深く、スリリングだったのが、最も南米移民を排出したのが最貧困地帯たる東北ではなく北部九州~山陽ラインだったのは何故か?を考察する章である。『大正時代』は実は『革命前夜』だった?それが本当に実像に沿っているのか判らない。著者は興奮のあまり筆をすべらせた感がある。60年安保について触れた部分の書きぶりにいささか針小棒大の気があるし、キム・ジョンミが指摘したように水平社の運動には限界があった。とはいえ、労働者・農民・部落民さらには沖縄や朝鮮からの移民たちが連帯し、軍隊の鎮圧に対し武力で抵抗することも厭わない運動体が、このニッポンにも存在していた時代があった、という物語には何かそそられるものがある。それが過大評価であったとしても。近代日本に対してそのようなイメージを描くことが難しいのは何故なのか?を問わなければならない。
関連記事
-

-
ふるまいよしこ氏の尖閣報道と観光
ふるまいよしこさんの記事は長年読ませていただいている。 大手メディアの配信する記事より、信頼できる
-

-
『鉄道が変えた社寺参詣』初詣は鉄道とともに生まれ育った 平山昇著 交通新聞社
初詣が新しいことは大学の講義でも取り上げておいた。アマゾンの書評が参考になるので載せておく。なお、
-

-
Quoraなぜ、当時の大日本帝国は国際連盟を脱退してしまったのですか?なぜ、満州国について話し合ってる中で軍事演習をしてしまったのか、なぜ、当初の目的である権益のほとんどを認められているのに堂々退場したのか。
日本の国際連盟脱退は、満州事変に対するリットン調査団の報告書を受け入れられないと判断して席を蹴った
-
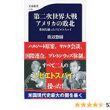
-
渡辺惣樹著『第二次世界大戦 アメリカの敗北』
対独戦争をあくまで回避するべきと主張したチェンバレンら英国保守層 対独戦争は膨大な国力を消費し、アメ
-

-
QUORA ゴルビーはソ連を潰したのにも関わらず、なぜ評価されているのか?
ゴルバチョフ書記長ってソ連邦を潰した人でもありますよね。人格的に優れた人だったのかもしれませんが
-

-
『国債の歴史』(富田俊基著2006年東洋経済新報社)を読んで
標記図書を読み、あとがきが要領よくまとめられていた。財政に素人の私には、非常に参考になる。 要約す
-

-
Quora ヒトラーはなぜ、ホロコーストを行ったのですか?
https://jp.quora.com/%E3%83%92%E3%83%88%E3%83%A9
-

-
書評 AIの言語理解について考える」川添愛 学士会報940号P.42
分類がわかりやすい 1 今のAIは人間の言葉を理解している。 理解
-

-
動画で考える人流観光学 観光資源、質量の正体は一体何なのか -質量の起源-
https://youtu.be/TTQJGcu-x3A https://
-

-
『AI言論』西垣通 神の支配と人間の自由
人間を超越する知性 宇宙的英知を持つ機械など人間に作れるか 人間は20万年くらい前に生物進

