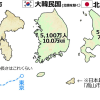『サカナとヤクザ』鈴木智彦著 食と観光、フードツーリズム研究者に求められる視点
築地市場から密漁団まで、決死の潜入ルポ!
アワビもウナギもカニも、日本人の口にしている大多数が実は密漁品であり、その密漁ビジネスは、暴力団の巨大な資金源となっている。その実態を突き止めるため、築地市場への潜入労働をはじめ、北海道から九州、台湾、香港まで、著者は突撃取材を敢行する。豊洲市場がスタートするいま、日本の食品業界最大のタブーに迫る衝撃のルポである。
〈密漁を求めて全国を、時に海外を回り、結果、2013年から丸5年取材することになってしまった。公然の秘密とされながら、これまでその詳細が報道されたことはほとんどなく、取材はまるでアドベンチャー・ツアーだった。
ライター仕事の醍醐味は人外魔境に突っ込み、目の前に広がる光景を切り取ってくることにある。そんな場所が生活のごく身近に、ほぼ手つかずの状態で残っていたのだ。加えて我々は毎日、そこから送られてくる海の幸を食べて暮らしている。暴力団はマスコミがいうほど闇ではないが、暴力団と我々の懸隔を架橋するものが海産物だとは思わなかった。
ようこそ、21世紀の日本に残る最後の秘境へ――。〉(「はじめに」より)
書評1
北海道の項で感じたのは、ヤのつく人々もK察も海保も同類。
机上で鉛筆舐めながら規程を作ってる役人には絶対わからない、現場の重さを感じた。
個人的には1980年頃の「北方領土の日」設定はこういうことなんだなあ、とフムフムと感じた。
本の内容とは直接関係ないが、
家人が一時、野菜・果物を大田市場に配送する仕事をしていた。
彼に言わせると「市場ってそんなもんよ、前歴を根掘り葉掘り聞いちゃいけないひとがいっぱいいる」と。
普通の人が動いていない時間帯の仕事っていうのは、えてして自由な人を受け入れる土壌になっている。
書評2
著者渾身の一冊だろう。
言葉の中身がいちいち濃密である。しかし、読むものを惹きつける何より「事実」の積み重ねが、どんどん「読ませる」構成になっている。
暴力団が悪い、密漁者が悪い、それを野放しにしている漁業者が悪い、ひいては政府が悪い、消費者が悪い・・・という誰かが悪い、というステレオタイプな二元論にいきがちなこの手の話題であっても、決してそう導かないところにこの作者のフリーライターとしての真骨頂が見て取れる。
それを知らずして、食と観光などといっている観光研究者も視点を広げてほしい
書評3
アワビ、ナマコ、カニ、ウニ、ウナギ。これらの海の高級食材は密漁ルートで市場にでまわっているものがわたしたちの想像をはるかにこえた量存在する。年間どれだけの密漁水産物をわたしたちは食べているのだろう。ついこのまえふるさと納税のお礼品で宮崎からやってきたウナギを食べながら、複雑な思いになる。本書によればウナギのシラス業界は「闇屋が跋扈し、国際的なシラス・ブローカーが暗躍し、暴力団の影も見え隠れする。全国で暴力団排除条例が施工され、企業コンプライアンスの重要性が認知された現在、ここまで不正が常態化し、不透明な業界も珍しい」とのことだ。宮崎県はウナギ取引の透明化に動いた最初の自治体だが、県の許可した最大漁獲量の10倍ものシラス(稚魚)が流通し、その9割が公定価格よりも高く売られているという。ウナギ業界の闇の深さがわかろうというものだ。“稀少”なウナギのシラスの産地台湾が日本向けの出荷を禁止したあと、迂回して香港から何ごともなかったかのごとく入ってきている。そういえば一時期ウナギが食べられなくなるかもしれないと騒がれたが、スーパーに行けば年間をとおしてウナギを売っている。ファストフードチェーンでも食べられる。不思議なことではないか。
三陸、築地、銚子、台湾、北海道…と密漁団を追い、その懐に入り込んで取材したディープなルポである。ヤクザ専門誌出身のジャーナリストの面目躍如だ。なかでも面白かったのが「東西冷戦に翻弄されたカニの戦後史」の第5章。本書のなかでも最大のページ数を割いている。太平洋戦争末期にソ連が千島列島に進軍、多くの島民たちは根室に逃れた。戦後、北方四島周辺がソ連領海となり、漁場を奪われた根室の漁師たちが見出した「活路」が“赤い御朱印船”とよばれた、スパイ行為と引き換えの操業許可だった。情報(レポ)をあげる見返りにソ連領海内での拿捕を免れていた通称レポ船主のなかには「北海道の大統領」「オホーツクの帝王」などと呼ばれた大立者がいた。実際はダブルスパイが多かったそうだ。しかし北の海で荒稼ぎしていたレポ船も、ソ連が崩壊し、ロシアになってからは存在意義を失い、姿を消す。それと前後して出てきたのが、船外機で補強した「特攻船」でロシアの巡視船を強引に振り切って大量のウニやカニを持ち帰ってくるという新手の密漁だ。しかし特攻船はソ連の実弾を使った本気の取り締まりによって壊滅。その後、根室の元暴力団がロシアからカニを輸入するような時代を経て、日ロ間で違法漁業防止の協定が結ばれたあとは、カニ貿易については正規ルートが主流になる。しかし日ロの港に入れない密漁船が保税区域を経て原産地ロンダリングをされて世界中に輸出される。日本に逆輸入されることも少なくないと言う。読むほどに「漁業の不正はどうやっても根絶できないのかもしれない」という著者の言葉が腑に落ちてくる。本書には出ていなかったが越前ガニとかはどうなんだろう。
日本の漁業と反社会的勢力との関係の深さには、日本特有の事情も関連しているらしい。本書で初めて知ったが、「漁業権」というのは日本でしかない独自の法律なのだそうだ。村の前にある海はその村の住民のもの、という考え方である。諸外国では、そうした概念はなく、操業許可を与えられた漁船は決められた海域内で海産物を獲る。明治維新後、漁師町の慣習や掟を明文化する形で漁業の法整備が行われ、戦後は漁業権を漁業協同組合が引き継ぐかたちでシステムは温存された。この組合を手なずけて銚子を「暴力の港」とした「東洋のアル・カポネ」高橋寅松(高寅)の話にもまるまる一章が割かれている。
わたしたちが日常的に口にしているものが、ここまで違法や脱法にまみれているとは想像もしていなかった。数々のヤクザ関連取材をしてきた著者でさえ「取材はまるでアドベンチャー・ツアーだった」「暴力団と我々の懸隔を架橋するものが海産物だとは思わなかった」と驚きを隠さない。密漁は、完全に日本の漁業のエコシステムの一部になっている。だからこそ、徹底的に取り締まることができない。さらにいえば乱獲、産地偽装を「やめる」インセンティブが業界には存在していない。消費者も共犯だ。あまりに根が深すぎ、複雑すぎる問題。AIも、VRも、ドローンも、ビッグデータも、何の役にも立たない「秘境」は、きっと漁業のほかにもまだあるのだろう。
関連記事
-

-
学士会報926号特集 「混迷の中東・欧州をトルコから読み解く」「EUはどこに向かうのか」読後メモ
「混迷の中東」内藤正典 化学兵器の使用はアサド政権の犯行。フセインと違い一切証拠を残さないが、イス
-
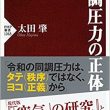
-
地域観光が個性を失う理由ー太田肇著『同調圧力の正体』を読んでわかったこと
本書で、社会学者G・ジンメルの言説を知った。「集団は小さければ小さいほど個性的になるが、その集団
-

-
ここまで進化したのか 『ロボットの動き』動画
https://youtu.be/fn3KWM1kuAw
-

-
『AI言論』西垣通 神の支配と人間の自由
人間を超越する知性 宇宙的英知を持つ機械など人間に作れるか 人間は20万年くらい前に生物進
-

-
ヒマラヤ登山とアクサイチン
〇ヒマラヤ登山 機内で読んだ中国の新聞記事。14日に、両足義足の、私と同年六十九歳の中国人登山
-

-
御手洗大輔「示威の自由に関する日中比較と日本人の課題」
『横浜市立大学論叢』第68巻社会科学系列2号 御手洗大輔「示威の自由に関する日中比較と日本人の課題」
-
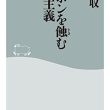
-
『ニッポンを蝕む全体主義』適菜収
本書は、安倍元総理殺害の前に出版されているから、その分、財界の下請け、属国化をおねだりした日本、
-

-
ジャパンナウ2019年9月号原稿「森光子記念館」
著名人の顕彰施設は著名である限りは存続する。問題は経年変化により著名人でなくなった場合である。文化