『「食糧危機」をあおってはいけない』2009年 川島博之著 文芸春秋社 穀物価格の高騰は金融現象
公開日:
:
最終更新日:2021/08/05
出版・講義資料
コロナで飲食店が苦境に陥っているが、平時には、財政措置を引き出すためもあり、時折食糧危機論が繰り返される。元農水省職員・東大教授による本書は「何かの時に食料が輸入できなくなるかもしれない」という間違った思い込みに基づいた政策をやめるべきとし、食料安全保障は世界の穀物市場をよく見ている商社に任せておけばよい、と主張する。アフリカなどで暴動まで発生した2008年の食糧価格の高騰は、生産量不足から来るものではなく、商品市場に投資資金が流入したことによるとする。このことは、江戸時代の飢饉が商品経済の浸透により、大阪にコメが集積されたことが主たる原因であったことと同じである。 人口の急速な増加を問題視した1972年『成長の限界』、途上国が肉を食いだし穀物が不足すると警告した1995年の『だれが中国を養うのか』等により、繰り返された食糧危機説は間違いであった。食糧危機説の中で在庫率の低下の根拠として言及されるが、90年代以降世界の穀物在庫率が低下したのは、IT技術の革新により、世界の穀物ロジスティックスに飛躍的進歩が起きた結果であるとする。人流もIT技術の革新により必須ではない動きや宿泊が減少することは、コロナで図らずも証明された。 観光資源論の調査記述の際分かったことであるが、「伝統」という言葉自体が戦前に陸軍が生み出したものであり、従って伝統といわれるものの大半は古くはない。本書も、近年の日本人の魚離れに関して、魚の消費が増加したのは大正年間からであると記述している。疑似エコ意識に彩られたフードマイレージのいかがわしさも指摘するが、エコツーリズム論にも当てはまる指摘である。
関連記事
-
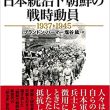
-
コロニアル・ツーリズム序説 永淵康之著『バリ島』 ブランドン・パーマー著『日本統治下朝鮮の戦時動員』
「植民地観光」というタイトルでは、歴史認識で揺れる東アジアでは冷静な論述ができないので、とりあえずコ
-

-
ここまで進化したのか 『ロボットの動き』動画
https://youtu.be/fn3KWM1kuAw
-

-
『一人暮らしの戦後史』 岩波新書 を読んで
港図書館で『一人暮らしの戦後史』を借りて読んでみた。最近の本かと思いきや1975年発行であった。
-

-
保護中: 学士会報No.946 全卓樹「シミュレーション仮説と無限連鎖世界」
海外旅行に行けないものだから、ヴァーチャル旅行を楽しんでいる。リアルとヴァーチャルの違いは分かっ
-

-
21世紀を考える会「仮想通貨の現状」岩下直之京都大教授の話を聞く 2018年4月20日
Bitcoinの発掘の仕組み 256ビットの最初の30個は零が続かなければらないという約束。ハッシュ
-
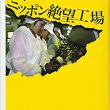
-
『ルポ ニッポン絶望工場』井出康博著
日本で働く外国人労働者の質は、年を追うごとに劣化している。 すべては、日本という国の魅力が根本のと
-
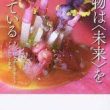
-
保護中: 『植物は未来を知っている』ステファノ・マンクーゾ 、動物が必要な栄養を見つけるために「移動」することを選択。他方、植物は動かないことを選び、生存に必要なエネルギーを太陽から手に入れるこにしました。それでは、動かない植物のその適応力を少しピックアップ
『植物は<未来>を知っている――9つの能力から芽生えるテクノロジー革命』(ステファノ・マンクーゾ著、
-

-
錯聴(auditory illusion) 柏野牧夫
マスキング可能性の法則 連続聴効果 視覚と同様に、錯聴(auditory illu
-

-
書評『法とフィクション』来栖三郎 東大出版会
観光の定義においても、自由意思を前提とするが、法律、特に刑法では自由意思が大前提。しかし、フィク

