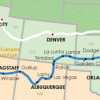「太平洋戦争末期の娯楽政策 興行取締りの緩和を中心に」 史学雑誌/125 巻 (2016) 12 号 金子 龍司
本稿は、太平洋戦争末期の娯楽政策について考察する。具体的にはサイパンが陥落した一九四四年七月に発足した小磯国昭内閣期以降終戦までの政策に注目する。 小磯内閣期の思想・文化統制については、先行研究により、東條内閣期の言論弾圧が見直されて言論暢達政策が採用され、思想・言論統制の緩和によって戦意昂揚を目指したことが指摘されている。娯楽統制についてもこの枠組みで語られ、従来強化一方だった統制がサイパン陥落・同内閣の成立を契機として一転して緩和されたと整理され、その画期性が指摘されている。 しかし、この統制緩和は小磯内閣が娯楽に対して講じた措置のひとつに過ぎないし、画期といっても、この統制緩和に限らなければ、娯楽への積極的な措置は小磯内閣発足以前からすでに講じられていた。つまり先行研究は、統制緩和の画期性を重視するあまり、小磯内閣の娯楽政策の全容を明らかにしておらず、しかも従前の政策との連続性も見過ごしているきらいがある。 したがって本稿は、小磯内閣期の娯楽政策をできるだけ詳しく分析することで右の二点を明らかにし、同政策を歴史的に位置づける試みを行う。具体的には、当事者たちの問題認識や政策決定過程や政策の実効性を検討材料とする。 本稿が明らかにするのは以下の事柄である。第一に、娯楽統制史上、小磯内閣期の統制緩和は個別の措置としてはたしかに画期的であったが、娯楽に対する積極的な姿勢や問題認識に関してはむしろ前内閣との連続性が目立っていたこと。第二に、政策の実効性といった観点からは、個別具体的な措置については一定の成果が見られ、戦争末期にあっても興行の機会は確保され盛況も珍しくなかったこと。第三に、それにもかかわらず、政策全体の評価としては、絶望化する戦況下で観客や興行者たちが娯楽を供給・享受して戦意昂揚に結びつけるだけの精神的余裕を失っていたため、失敗に終わったと結論せざるを得ないことである。
本稿は、太平洋戦争末期の娯楽政策について考察する。具体的にはサイパンが陥落した一九四四年七月に発足した小磯国昭内閣期以降終戦までの政策に注目する。小磯内閣期の思想・文化統制については、先行研究により、東條内閣期の言論弾圧が見直されて言論暢達政策が採用され、思想・言論統制の緩和によって戦意昂揚を目指したことが指摘されている。娯楽統制についてもこの枠組みで語られ、従来強化一方だった統制がサイパン陥落・同内閣の成立を契機として一転して緩和されたと整理され、その画期性が指摘されている。しかし、この統制緩和は小磯内閣が娯楽に対して講じた措置のひとつに過ぎないし、画期といっても、この統制緩和に限らなければ、娯楽への積極的な措置は小磯内閣発足以前からすでに講じられていた。つまり先行研究は、統制緩和の画期性を重視するあまり、小磯内閣の娯楽政策の全容を明らかにしておらず、しかも従前の政策との連続性も見過ごしているきらいがある。したがって本稿は、小磯内閣期の娯楽政策をできるだけ詳しく分析することで右の二点を明らかにし、同政策を歴史的に位置づける試みを行う。具体的には、当事者たちの問題認識や政策決定過程や政策の実効性を検討材料とする。本稿が明らかにするのは以下の事柄である。第一に、娯楽統制史上、小磯内閣期の統制緩和は個別の措置としてはたしかに画期的であったが、娯楽に対する積極的な姿勢や問題認識に関してはむしろ前内閣との連続性が目立っていたこと。第二に、政策の実効性といった観点からは、個別具体的な措置については一定の成果が見られ、戦争末期にあっても興行の機会は確保され盛況も珍しくなかったこと。第三に、それにもかかわらず、政策全体の評価としては、絶望化する戦況下で観客や興行者たちが娯楽を供給・享受して戦意昂揚に結びつけるだけの精神的余裕を失っていたため、失敗に終わったと結論せざるを得ないことである。
関連記事
-

-
新語Skiplagging 「24時間ルール」と「運送と独占の法理」
BBCの新しい言葉skiplagging
-
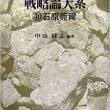
-
「世界最終戦論」石原莞爾
石原莞爾の『世界最終戦論』が含まれている『戦略論体系⑩石原莞爾』を港区図書館で借りて読んだ。同書の
-

-
運輸省(航空局監理部長)VS東亜国内航空(田中勇)のエピソード等
https://www.youtube.com/watch?v=flZz_Li7om8
-
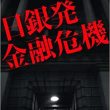
-
英国通貨がユーロでない理由 志賀櫻著「日銀発金融危機」
ポンド危機と英国通貨がユーロでない理由 サッチャー政権
-
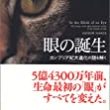
-
『眼の誕生』アンドリュー・パーカー 感覚器官の進化はおそらく脳よりも前だった。脳は処理すべき情報をもたらす感覚器より前には存在する必要がなかった
眼の発達に関して新しい役割を獲得する前には、異なった機能を持っていたはず しエダア
-
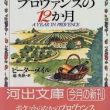
-
『プロヴァンスの村の終焉』上・下 ジャン=ピエール・ルゴフ著 2017年10月15日
市長時代にピーターメイルの「プロヴァンスの12か月」読み、観光地づくりの参考にしたいと孫を連れて南仏
-

-
太平洋戦争で日本が使用した総費用がQuoraにでていた
太平洋戦争で、日本が使った総費用はいくらでしょうか?Matsuoka Daichi, 九州大学で経
-

-
「起業という幻想」白水社 スコット・A・シェーン 職を転々として起業に身をやつす米国人の姿は、産学官が一体になって起業を喧伝する日本社会に一石投じることは間違いない。
マイクロソフトのビル・ゲイツ、アップルを立ち上げたス
-

-
筒井清忠『戦前のポピュリズム』中公新書
p.108 田中内閣の倒壊とは、天皇・宮中・貴族院と新聞世論が合体した力が政党内閣を倒した。しかし、