『金融資本市場のフロンティア 東京大学で学ぶFinTech、金融規制、資本市場』に学ぶべきMaaS
公開日:
:
最終更新日:2021/08/05
出版・講義資料
本書を読んで、アンバンドリングとリバンドリングという言葉に出会った。金融機能が、テクノロジーが導入されることで分解されることをアンバンドリング(unbundling)、再び再編成されることをrebundlingと表現し、銀行法や証券法等の規制がそれを阻害し、国際競争に敗北するのではないかという問題意識を霞が関がもっていることが理解できた。
私は、今世紀初頭、金沢学院大学大学院で物流の講義を始めた時に、「運送機能の分化」という表現を用いた。規制のない国際海運で起きていることを表現し、航空機から陸上運送にまでその現象が起きていることを説明したつもりである。そのことが、金融の世界でも始まっているのであるが、人流の世界では物流ほどではないものの、少しずつ始まっている。モノの移動には国境の障壁が低く、次いで金融である。金融は典型的な規制の対象である。しかし、ゴールドは国会善意存在し、貨幣はすべてゴールドに源を発しているから、規制がその機能を邪魔すれば、規制が悪者になることは容易に想像できる。
その点、人流は規制が立ちはだかっている。人命という安全確保が、国家の規制の必要性の説明になっているが、国家が複数存在する国際移動では、世界共通(アメリカ主導かもしれないが)の安全性確保が共通になり、経済規制はほぼ消滅している。従ってアンバンドリングとリバウンドリングが起きている。
起きていないのは、国内人流の世界で、特にバスタクシーの世界である。それでもITの影響を受け、ライドシェが国際的に普及してきた。国際的な観光地間競争に生き残るためには、2次交通が貧弱では、自然淘汰されるという意識を持たなければならない。自動運転技術が進展すれば、人命の安全性確保という建前は薄れてゆき、空いている車空間を最大限活用するというブロックチェーンの発想によるライドシェが当たり前になるであろう。
残念ながら日本では、法律論議に詳しくない環境学の専門家等が、権限保持マインドが強い運輸局から頼りにされるのか、にわか知識で論議しているが、私から見るとミイラ取りがミイラになっている。基本知識のある若手官僚は、ポストが頻繁に変わり、しかも、道路運送法を巡っては完全に政治優位であるから、制度改革に関するアイデアは全く出てこない。官僚が規制緩和を行ったにもかかわらず、政治家が業者と組合の声に押されて、議員立法で再規制してしまったからだ。これにはメディアの不勉強も影響している。これは、自動車、鉄道、道路といった国土交通省の組織の立て方にも問題があるのであろう。昔の地域交通局のような横断的なものでないと、若手官僚からは規制緩和のマインドが出てこないのであろう。近道は道路運送法の権限の地方自治体への移管であり、道路局と自動車局の統合であろう。地方運輸局は地方建設局と一体化した行政を行えば、マインドも変化するはずである。
私は東京都のシルバーパスを愛用しているが、都営の鉄道と都バス、民間バスは年2万円で乗り放題であるから、交通機関の障壁を全く感じない。東京メトロやJRが入っていないので、その分不便ではあるが、都営もネットワークがそこそこあるのであまり困らない。昔の交通学者が、欧州大都市の共通運賃制を研究していたが、MaaSと本質は一緒であり、進歩がみられない。というより、国定改革を実施した日本のほうが進んでいるのである。
金融に比べれば単純な世界である旅客交通では、はやり言葉のようにMaaSが論議されているが、旅客交通ビジネスは細かいところまで規制を受けている。金融が垣根を超えて規制の論議されているが、旅客交通に関しては、バスとタクシー、運転代行、レンタカーの垣根を超えるような規制論議を、MaaSでは誰もしていない。研究者の怠慢というより、業界から引き立ててもらっている研究者には、できない発想なのである。
しかし、国鉄改革時、組合から見て見方だと思っていた加藤寛氏等の学者が、分割民営化に宗旨替えしていたような経緯もあるから、研究者もそこまで権威筋になれれば変化は期待できる。
Amazonの書評は次の通り。
2018年後期の東京大学の公共政策大学院、法科大学院、法学政治研究科の大学院生向けの講義を再編して収録したもの。「金融とITの政策学」の続編である。
フィンテックや金融規制に関するものが6章、金融資本市場に関するものが5章で構成される。実務家による説明はいずれも興味深いが、最も面白いのはコーポレートガバナンス改革と独立社外取締役の役割という章。日本のガバナンスは低収益低成長で遅れている、独立社外取締役は役に立つことも立たないこともあるなどとデータも交えて説明している。ガバナンス向上のためには、株主総会改革よりもベンチャー育成による新陳代謝が重要とは考えもしなかった。実務経験に基づく意見で説得力もある。次に面白いのが、M&Aに関する章。税制がいかにM&Aの発展を阻害していることがよくわかる。フィンテックのところは特段目新しいこともないが、期待していなかった後半部分が異様に面白かった。
金融庁では少なくともそのようなマインドがあり、国際競争に取り残されないため、真剣に議論し、大学で講義まで行っている。
関連記事
-

-
『戦後経済史』野口悠紀雄著 説得力あり
ドッジをあやつった大蔵省 シャープ勧告も大蔵省があやつっている。選挙がある民主主義では難しいこと
-
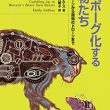
-
『サイボーグ化する動物たち 生命の操作は人類に何をもたらすか』作者:エミリー・アンテス 翻訳:西田美緒子 白揚社
DNAの塩基配列が読破されても、その配列の持つ意味が分からなければ解読したことにはならない。本書の冒
-

-
『AI言論』西垣通 神の支配と人間の自由
人間を超越する知性 宇宙的英知を持つ機械など人間に作れるか 人間は20万年くらい前に生物進
-

-
『平成経済衰退の本質』金子勝 情報、金、モノ、ヒト、自然 について、グローバリゼーションのスピードが違うことを指摘 情報と人流のずれが、過剰観光
いつも感じることであるが、自分も含め観光学研究の同業者は、研究原理を持ち合わせていないということ
-
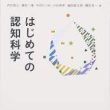
-
『はじめての認知科学』新曜社 人工知能研究(人の知性を人工的に作ろうという研究)と認知科学研究(人の心の成り立ちを探る研究)は双子
人工知能研究(人の知性を人工的に作ろうという研究)と認知科学研究(人の心の成り立ちを探る研究)は
-

-
『コンゴ共和国 マルミミゾウとホタルの行き交う森から 』西原智昭 現代書館
西原智昭氏の著書を読んだ。氏の経歴のHP http://www.arsvi.com/w/nt10.h
-

-
世界人流観光施策風土記 ネットで見つけたチベット論議
立場によってチベットの評価が大きく違うのは仕方がないので、いろいろ読み漁ってみた。 〇 200
-

-
鬼畜米英が始まったのは、1944年からの現象 岩波ブックレット「日本人の歴史認識と東京裁判」吉田裕著
靖国神社情報交換会に参加した。歴史認識は重要な観光資源であるとする私の考えに共鳴されたメンバーの
-

-
言語とは音や文字ではなく観念であるという説明
観光資源を考えると、言語とは何かに行き着くこととなる。 愛聴視して「ゆる言語学ラジオ」で例のエ


