安易なフードツーリズム、食育、和食神話への批判 コメに無期ヒ素が含まれているのはものすごく都合が悪い。大手メーカーが「ただの水です」といって水素水を売っている
公開日:
:
最終更新日:2023/05/28
出版・講義資料, 路銀、為替、金融、財政、税制
公研2016年6月号に「食の安全とリスクを考える」畝山智香子(国立医療品食品研究所安全情報部第三室長)と松永和紀(科学ジャーナリスト)の対談が掲載されている。
以下そのメモである。
日本の農産物は安全だ、農業の基準が厳しいという思い込みがあるが、いざ食材を輸出して相手国の基準が日本より厳しいことに気が付くことが多く、ダメと言われるレベルにまでなってしまっている。
海外ではコメに含まれる無機ヒ素が問題になっている。発がん性があるだろうという前提で進んでいる。自然に存在するから天然物の食品の場合ゼロにはできない。一番多く含まれているのはヒジキとコメ。
ヒジキは外国では禁止。問題はコメ。「放射能は一ベクレルも許さない」と言っている人が、なぜコメは完全スルーなのか。玄米の場合日本のコメは2割くらいEUの基準値を超えてしまう。
和食に戻りましょうと言ってきた人に、コメに無期ヒ素が含まれているのはものすごく都合が悪いのです。
長生きできるようになればがんの人が増えるのは当然で、むしろ年齢調整すると減少している。
健康食品の宣伝をメディアが行うが、ほとんど詐欺に近い。特定保健用食品(トクホ)の時代からかなり嘘ばかり。
大手メーカーが「ただの水です」といって水素水を売っているが、これは機能性すらなく、イメージだけ。
痩せるとうたわれてものはほとんど下剤
台湾でアメシバの被害が出ているのに、日本の大手出版社が宣伝している
ウコンが肝臓にいいと言っているのは日本だけ
生肉で食中毒が大量に出ている。なぜメディアがあんなに宣伝するのかわからない。ギラン・バレー症候群になって一生治らない人が出たらどうするのでしょう。
昔はささみを生で食べられたが、今は温水処理の段階で全部がカンピロバクターに汚染されてしまうから危険。
依然として洋食より和食だとか、加工品は食べないようにしましょうという内容を「食育」という名で続けている現状がある。年寄りの単なる思い込みである。
玄米はカドミニウムとヒ素が多いので子供に食べさせるのはやめるべき。
たんぱく質、炭水化物、脂質のバランスを言うのは日本独自で、根拠なし。日本人のナトリウム摂取量が多いのは、ご飯のおかずにいいように味を濃くするから。野菜料理そのもので十分な味と考えればもっと塩分を減らせるから、和食は最大の欠点。
添加物の鉄のほうがヒ素が入っていないので安全だが、日本人は添加物は悪いと思い込んでいる。
関連記事
-

-
デジタル化と人流・観光(1)
通信の秘密が大日本帝国憲法及び日本国憲法に規定されていることもあり、長らく電気通信事業は逓信省、運
-
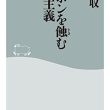
-
『ニッポンを蝕む全体主義』適菜収
本書は、安倍元総理殺害の前に出版されているから、その分、財界の下請け、属国化をおねだりした日本、
-
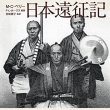
-
角川文庫『ペリー提督日本遠征記』(Narrative of the Expedition of an American Squadron to the China Seas and Japan)
https://youtu.be/Orb9x7NCz_k https:
-

-
quora 中世、近世のヨーロッパで、10代の女性がどのような生活を送っていたのか教えてくれませんか?貴族階級/庶民とそれぞれ、何をしていたのでしょうか?
何で10代の女性限定なのかよくわかりませんが、知っている範囲で。 中世の庶民は、ほぼ
-

-
MaaSに欠けている発想「災害時のロジステックスを考える」対談 西成活裕・有馬朱美 公研2019.6
公研で珍しく物流を取り上げている。p.42では「自動車メーカーは自社の車がどこを走っているかという
-
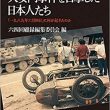
-
『天安門事件を目撃した日本人たち』
天安門事件に関する「藪の中」の一部。日本人だけの見方。中国人や米国人等が作成した同じような書籍があ
-

-
動画で考える人流観光学 観光資源、質量の正体は一体何なのか -質量の起源-
https://youtu.be/TTQJGcu-x3A https://
-

-
「キャピタリズム マネーは踊る」マイケル・ムーア
https://youtu.be/aguUZ7PGd2A https://youtu.be/a
-

-
戦陣訓 世間が曲解して使用し、それが覆せないほど行き渡ってしまった例
世間が曲解して使用し、それが覆せないほど行き渡ってしまった例である。「もはや戦後ではない」は私の


