観光とツーリズム~日本大百科全書(ニッポニカ)の解説に関する若干の疑問~
公開日:
:
最終更新日:2016/11/25
人流 観光 ツーリズム ツーリスト, 観光学評論等
日本大百科全書には観光に関する記述があるが(https://kotobank.jp/word/%E8%A6%B3%E5%85%89-469729)
以下特に気になる点を取り上げる。この解説でも「井上萬壽藏(ますぞう)著『観光と観光事業』1967」を引用しているが、井上氏の解説には原典が示されていないことから、正確であるのか疑問が残っている状況である。
〇 「日本で観光の語が現代的な意味で使用されるようになったのは、英語のツーリズムtourismの訳語としてあてられるようになった明治なかば以降である。」
◆ 字句「ツーリズム」が明治半ばに日本の訳語になったか否かの点は、辞書及び新聞記事検索結果では証明できない(むしろ否定的)ことをすでに本ブログでも明らかにしているところであり、帝京平成大学紀要27巻にも掲載しているところである。残された手段として、英文の原典と日本の訳本を突き合わせて照合しなければならないが、そのような作業は今のところなされた研究はない。
〇 「とくに一般化したのは大正に入ってからで、とりわけ1923~1924年(大正12~13)ごろ、アメリカ移住団の祖国訪問に際して新聞紙上で「母国観光団」として華々しく報道されたためだといわれる。」
◆ 朝日新聞記事データベース聞蔵Ⅱの検索結果では、「母国観光団」の記事は朝鮮からの母国観光団の記事が1911年に掲載されて以来1925年までに38件掲載されているが、1923年から24年の掲載件数は1924年6月18日の記事1件である。しかも当該記事は、母国観光団のブローカーが船賃を三倍にして横浜から米国に移民団を送り大儲けしたという、全く観光とは無縁の内容である。ちなみに1935年までに検索期間を拡大してもヒット数は49件であり、同期間の「観光」のヒット件数345件と比較しても格段多いということでもない。
朝日新聞だけが当時の日本語の報道であるわけではないが、たぶん読売新聞記事検索ヨミダスでも同じ結果になるであろう。
〇「日常的な語として広く使用されるようになったのは昭和初期以降であり、世界的な観光黄金時代を背景にして鉄道省に国際観光局が設置(1930)されたのを契機に民間機関も設立され、国内観光の気運が高まりをみせ始めたころからである。」
◆ 「国内観光の機運が高まり」の記述も不正確であることは帝京平成大学紀要27巻に記述しているが、人流観光研究所HPに『概念「「楽しみ」のための旅」と字句「観光」の遭遇』として掲載してある(http://www.jinryu.jp/category/study)
関連記事
-

-
脳科学と人工知能 シンポジウムと公研
本日2018年10月13日日本学術会議講堂で開催された標記シンポジウムを傍聴した。傍聴後帰宅したら
-

-
2026年4月20日 LITTLE TOKYOでの過ごし方 GEMINI回答
1. ビバリーヒルズからリトル東京への移動 公共交通機関を利用する場合、**メトロ・バス(Line
-

-
概念「「楽しみ」のための旅」と字句「観光」の遭遇 Encounter of the concept “Travel for pleasure” and the Japanese word “KANKO(観光)”(日本観光研究学会 2016年度秋期大会論文掲載予定原稿)
「「楽しみ」のための旅」概念を表現する字句が、いつごろから発生し、どのように変化していったかを、「「
-
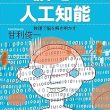
-
甘利俊一 AI時代の到来 その仕組みと新しい文明 学士会会報974 2025年Ⅴ
4億年前、情報処理に特化した脳神経系の器官が生まれた 物理学の法則は今の宇宙に貫徹。生命の法則
-

-
動画で考える 自動運転
https://www.technologyreview.jp/s/327918/whats-nex
-

-
若者の課外旅行離れは本当か?観光学術学会論文の評価に疑問を呈す
「若者の海外旅行離れ」を読み解く:観光行動論からのアプローチ』という法律文化社から出版された書籍が
-

-
『旅程と費用概算』、『ツーリスト案内叢書』にみる字句「遊覧」「観光」
都立図書館で閲覧可能な「旅程と費用概算」及び「ツーリスト案内叢書」により、当時の字句「遊覧」「観光」
-
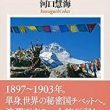
-
河口慧海著『チベット旅行記』の記述 「ダージリン賛美が紹介されている」
旅行先としてのチベットは、やはり学校で習った河口慧海の話が頭にあって行ってみたいとおもったのであるか


