『観光の事典』朝倉書店
公開日:
:
最終更新日:2023/05/28
人流 観光 ツーリズム ツーリスト, 出版・講義資料
「観光の事典」に「観光政策と行政組織」等8項目の解説文を出筆させてもらっている。原稿を提出してから4年近く経過しての出版であった。編集者の苦労が察せられる。朝倉書店の同書の担当者が、以前に私の学位論文『観光政策学』を出版したイプシロン企画出版・社長の義理の息子さんであった。私の原稿が一番早かったので、記憶されていたようである。
同書では1-1「観光の定義」から始まっている。その出筆者が、「研究では定義して使われることが求められる」とする点は当然である。しかし、「旅は「物見遊山」的な行動ともとられてきた」との記述は、近年進展している「近世旅行史」の研究成果とは見解が違うようであり、今後は、歴史研究者の参加を検討することが望ましいであろう。また「観光は大正期以降、旅、旅行、ツーリズムと同じような意味で用いられるようになった」とする記述は参考とする資料の明示が必要である。また観光の「公的定義」に審議会答申(諮問に対する答申であり拘束力はない)を引用するのはミスリードである。公的の概念が公的機関とするのであれば、行政機関になり、行政機関はそれぞれ諮問する役割が設置法で限定されているから一般論にはならない。研究者には権威はあるかもしれないが、権威に弱いのも問題である。
結局、カタカナ字句「ツーリズム」と字句「tourism」が同義ではありえず、字句「観光」とも完全には同義ではないから、それぞれ字句「観光、ツーリズム、tourism」の意味する概念を明確にしないといけないという、当たり前のことになる。
また、1-2「観光の語源」において「Tourismの訳語として一般的に「観光」が使用されるようにったのは大正期であったと筆者は推測する」と記述がある。これは私が「観光の事典」の「観光政策と行政組織」に記述した解説と平仄を併せるために「推測」と記述されたのであろうが、研究者であれば推測の根拠を示す必要がある。当時の鉄道省の資料には、それらしき記述が今のところ見当たらない。
昭和5年に初めて行政用語(政策用語でもある)として使用され国際観光局の英文名は(Board of Tourist Industry)であり、tourismではなかった。ましてや字句ツーリズムではないから、行政用語として字句ツーリストは存在しても字句ツーリズムは確立していなかったと考えることが妥当である。「観光の事典」に限らず、現在日本の多くの教科書は、大正時代に、tourismの訳語として字句「観光」があてられたと解説する。それは、戦後1967年に国際観光年記念事業協力会が発行した『観光と観光事業』に記述されているからだと思われるが、これらの観光の教科書では出典等は明らかにされていない。私が調べた当時の辞書を根拠にする限りにおいてはこのような解説には根拠がないことになる。ましてや、概念「観光」(字句には「物見」等が使用)の発生は、英国よりも日本の方が先でないかとする近世歴史学の研究もあるくらいであり、1827年に出版されたわが国で最初の英和辞典では『諳厄利亜大成』でも、観光関連字句として、travelle、trip、journey、passengerは紹介されているいるが、tour、touristは出てこず、ましてやtourismは出てきていない。
関連記事
-

-
中国人観光客の動向調査に役立つHP
百度検索 https://hotelbank.jp/baidu-2017/ 中国出境游研
-

-
Analysis and Future Considerations on Increasing Chinese Travelers and International Travel & Human Logistics Market ⑧
Ⅶ Alaska and Hawaii ~ High latitude tourist site
-
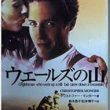
-
観光資源創作と『ウェールズの山』
観光政策が注目されている。そのことはありがたいのであるが、マスコミ、コンサルが寄ってたかって財政資金
-

-
公研2019年2月号 記事二題 貧富の格差、言葉の発生
●「貧富の格差と世界の行方」津上俊哉 〇トーマスピケティ「21世紀の資本」
-

-
ふるまいよしこ氏の尖閣報道と観光
ふるまいよしこさんの記事は長年読ませていただいている。 大手メディアの配信する記事より、信頼できる
-

-
全米50州走破計画をAIに聞く
アメリカのAMTRAKを安く利用する方法を教えてください。 アメリカの鉄道「Amtrak」を安
-
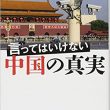
-
『言ってはいけない中国の真実』橘玲2018年 新潮文庫
コロナ禍で海外旅行に行けないので、ブログにヴァーチャルを書いている。その一つである中国旅行記を
-

-
ピアーズ・ブレンドン『トマス・クック物語』石井昭夫訳
p.117 観光tourismとは、よく知っているものの発見 旅行travelとはよく知られていな
-

-
『物語 ナイジェリアの歴史』島田周平著 中公新書
アマゾン書評 歴史家トインビー曰く、アフリカはサハラ砂漠南縁を境に、北のアラブ主義
-

-
『昭和史』岩波新書青本 恐慌の影響で、朝鮮人(日本国籍がある)の満州移住が増加したが、中国側は日本の手先と見て敵視 奉天の柳条溝で満州事変 この頃からメディアも変わる
26年と30年を比較すると中国(満蒙含む)の輸出入貿易額に占める対日貿易額の占める割合は低下した

