明治維新の評価 『経済改革としての明治維新』武田知弘著
公開日:
:
最終更新日:2023/05/30
出版・講義資料, 歴史認識, 路銀、為替、金融、財政、税制
明治時代の日本は世界史的に見て非常に稀有な存在である。19世紀後半、日本だけが欧米列強に対抗しうる軍事力を整え、世界の強国にのしあがったのである。しかし、「その資金はどこから出たのか?」--その答えについて、これまで明確に語られることはなかった。世界史の常識ではありえないような改革の数々、経済の活性化と急成長。そこからは、われわれ日本人がいままで持ってきた歴史観とは違う「明治の日本」、そして日本経済再生のヒントが見えてくるはずである。(「はじめに」より)
【目次】
第一章 「大日本帝国」の資金調達
第二章 「規制緩和」としての明治維新
第三章 渋沢栄一と特命チーム「民部省改正掛」
第四章 空前絶後の「超高度経済成長」
第五章 新政府を悩ませた「悪の金融工学」
第六章 松方正義が完成させた金融システム
明治維新の成功を、「経済発展」という見地から説き明かす異色の一冊。新刊だと思っていたが、巻末に、2013年に刊行された『史上最大の経済改革〝明治維新”』を改訂したものである旨の断りが書かれていた。先月刊行された『大日本帝国をつくった男』と重なる記述も見られるものの、明治維新の立役者らの功績が、挫折や苦悩、失敗や対立などの負の側面も交えて活きいきと描かれており、終始興味深く読んだ。
『大日本帝国をつくった男』を読んだ際にも感じたが、明治維新とは、本書に登場する、政府や役所の中枢にいた人物だけでなく、日本中のあらゆる人々が心を一つにし、『国のために、何としてもこの急激な近代化を成功させなければならない。』という思いを胸に懐いていたからこそ成功できた、まさに国を挙げての国家的事業であった。日本人とは、危機や困難に直面すると、『何が何でもこの難局を突破するぞ。』という底力がどこからともなく湧いて来て、関係者全員が力を合わせ、最終的には、まるで何事でもなかったかのように易々と難局を乗り越えてしまう国民である。日本人のこのような特質は、歴史上、何度か見られたが、明治維新においてほどこの特質が顕著に見られた例は後にも先にもない。本書第一章によると、明治政府が財源を確保できたのは、武士が自ら特権を抛棄し、商人が「藩債棒引き政策」に応じたからだと言う。一体日本以外のどこの国の人間が、国のために自らを犠牲にすることをかくも進んで肯(がえ)んじるであろうか。ここには、交渉の場で、「自らの利益の最大化」よりも「関係者全体の利益の最大化」を追求しようとする日本人の特質が端的に示されている。このような特質を持つ国民だったからこそ、明治維新は成功したのであり、裏を返せば、日本以外の国の人間にはこのような特質が欠けているからこそ、どこの国でもこのような急激な近代化は悉く失敗に終わったのである。明治維新には、日本人が自らの実像を知る上で、学ぶべき点が非常に多くある。
また、これも、『大日本帝国をつくった男』を読みながらも思ったことであるが、このような、関係者が一丸となって取り組む大事業においては、ここぞという局面において、あたかも狙いでも定めたかのように、余人を以て代え難いなくてはならない人材が自ずと現われ、また、そのような人物が手腕を発揮するようなお膳立てが整うものである。殊に、第六章を読み、一般にはさほど名前を知られず、あまり高く評価されていない松方正義の偉大な功労に、深く感じ入る他なかった。ただ、誤解がないように付け加えておくと、彼が断行した金融引き締め政策は、「正貨の蓄積」という特殊な目的を達成するためのものであり、今日、財務省とその提灯持ちが、仕事をしないことが仕事の天下り役人を養う財源を確保するために喧伝している、「増税しないとハイパーインフレが起きる!」とか、「財政健全化のためには緊縮財政が不可欠!」などの言説は、全てまやかしでしかない。
関連記事
-

-
電力、情報、金融の融合
「ブロックチェーンとエネルギーの将来」阿部力也 公研2019No673 電気の値段は下がって
-

-
MaaSに欠けている発想「災害時のロジステックスを考える」対談 西成活裕・有馬朱美 公研2019.6
公研で珍しく物流を取り上げている。p.42では「自動車メーカーは自社の車がどこを走っているかという
-

-
観光資源と伝統 『大阪的』井上章一著
今年も期末試験問題の一つに伝統は新しいという事例を提示せよという問題を出す予定。井上章一氏の大阪
-

-
『2050年のメディア』下山進
日本の新聞がこの10年で1000万部の部数を失っていることを知り、2018年4月より、慶應義塾大学
-

-
2002年『言語の脳科学』酒井邦嘉著 東大教養学部の講義(認知脳科学概論)をもとにした本 生成文法( generative grammar)
メモ p.135「最近の言語学の入門書は、最後の一章に脳科学との関連性が解説されている」私の観光教
-

-
シャマニズム ~モンゴル、韓国の宗教事情~プラス『易経』
シャーマン的呪術は筮竹による数字と占いのテキストを使った方法にかわった。このことにより特殊能力者でな
-

-
『金語楼の子宝騒動』(「あきれた娘たち」縮尺版)少子高齢化を想像できなかった時代の映画
1949年新東宝映画 私の生まれた年である。嫁入り道具に風呂敷で避妊薬を包むシーンがある。優生保護
-

-
保護中: 『市場と権力』佐々木実を読んで
日銀が量的緩和策で銀行に大量にカネを流し込んだものの、銀行から企業への融資はそれほど増えなかった。
-
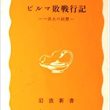
-
動画で考える人流観光学 『ビルマ敗戦行記』(岩波新書)2022年8月27日
明日2022年8月28日から9月12日までインド・パキスタン旅行を計画。ムンバイ、アウランガバード
-
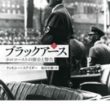
-
「ブラックアース~ホロコーストの歴史と警告」ティモシー・スナイダー著池田年穂訳 を読んで
ホロコーストについても、観光学で歴史や伝統は後から作られると説明してきたが、この本を読んでさらにその

