国際観光局ができた1930年代の状勢 『戦前日本の「グローバリズム」』
公開日:
:
最終更新日:2021/08/05
出版・講義資料
大東亜共栄圏の虚構を指摘
「バダヴィアに派遣された小林一三商相」国内世論の啓発に努める小林は、「日本の財界人、実業人の蘭印に対する認識不足ある以下無理解」を批判する。ジャワ島だけでも鉄道の総延長は日本と大差なかった。「列車の立派さは、その快速といい、乗り心地と言い、設備の行き届いている点など、わが東海道線の列車でも遠く及ばない」。アスファルト舗装の道路網も素晴らしかった。それなのに「日本の財界人が蘭印というものを、以前として未開野蛮な土人の国であると思っているようなことでは、到底日本の経済南進はおろか東亜広域経済の確保などというものは望まるべくもない・・」「小林は言う「どうせ南洋土人相手に売る品物だ、安かろう悪かろうということになって、在住邦人商業者の信用を失墜せしめ、それが結局日本の貿易に悪影響を及ぼす、そういう実例をいくらも見聞する」
戦前のインバウンドブーム(?)が1930年代に起きた理由が本書で理解できる。満州事変、日中戦争、日米開戦の共通項は満州利権であるが、多くの日本人には利権でも生命線でもなかったことが理解できる。ではなぜ、多大の犠牲を払って守ることになってしまったのか。移民というのは寒い地方から暖かい地方に行くもので、満州は逆だから誰も行きたがらないだろう。関東軍も五族協和を標榜し、日本人を優遇すれば悪貨が良貨を駆逐することにつながり、徹底した邦人保護をする気がなく、そのことが分かっているから、移民に二の足を踏むことになる。関西財界には満蒙放棄論がるくらいである。在満日本人は、内地人からの差別に不満。アメリカ資本に期待して、鮎川を活用したと解説する。現在のインバウンドブームにも、ネトウヨが同時進行で存在することも妙に符合するから、既視感がある。
1937年盧溝橋事件への対応 あきれ果てた非常時総理と芝公園で暴支膺懲国民大会を開催した国民、
Amazonの書評から「1930年代というと、国際連盟を脱退した後、日本は国際的な孤立化まっしぐら、というイメージを持つ人が多いが、本書では逆に1930年代にこそ花開いていた経済・外交の存在を明らかにする意図を持って記述する。満州事変について、「満蒙特殊権益の保護」が目的として理解されることが多い。
しかし、松岡洋右などは日中連携による満蒙開発を計画しており、満州事変はその計画を台無しにするものだった。満蒙は外国資本なくしては発展できないような「見捨てられた荒野」であり、そのため「王道楽土」はアメリカに著しい依存をする。」「従来、国際連盟脱退は「日本の国際的な孤児化」を招いたとされる。しかし、実際には脱退後も英仏協調路線がとられ、海軍軍縮予備交渉も英米と行われている。連盟脱退はむしろ事態を鎮静化させ協調を回復させるための策であり、実際そのように進んでいった。日本は最終的に独伊と同盟を結ぶので、独伊とは友好的に思われがちだが全く違う。この二国は人種偏見をむき出しにする国であり、反独伊・親英米の流れはかなり長く続いている。また、イタリアのエチオピア侵攻の際にはエチオピアを支持し、イタリアと強く対立する。1930年代には、英米仏もまた挙国一致体制をとっており、日本が範とするべき国は皆挙国一致であった。そのため、日本でも親英米のデモクラシー擁護者から見ても英米仏と独伊の境界線はあいまいになっていく時代であった。こうした背景が、日本の国家主義体制の基礎になっていく。世界恐慌で各国がブロック経済による封鎖をかけてくる。そのような中、日本は一国ずつ粘り強く交渉することで、交易の道筋を見出そうとする。そうして交易をおこなう相手は地球の裏側にまで及ぶ、極めて広範な地域になる。日本の擁護する「経済圏」は、ブロック経済とは真逆の、幅広い自由貿易による活性化であり、そのために発生していたのは経済摩擦であった。」30年代のイメージをひっくり返してくれる好著である。
書評2「これまでは戦前の海外政策の背景には列強への敵意や不信感があったと思っていたが、実際は全く逆で国際協調が主目的であったのは驚きであった。後世から見ればファシズムと戦争への突き進んだかに見える1930年代の政治情勢には国際協調や地域主義が決して小さな勢力ではなかったことを本書で初めて知った。そして文字通りの意味のグローバリズムが実現した時代であったことも。後世から見れば様々な要素が軍部の独走へとつながっていくかのように見えるが、決して唯一の選択肢ではなかった。勝ち目のない戦争へと突入していく以外にも選択肢はあり得たことを具体的に知り得ることができたのが本書である。戦前の孤立主義の代表的に語られるエピソードである国連脱退も松岡洋右は実は反対していたこと、国際協調派の外交官こそが脱退の推進派であったこと、脱退こそが経済制裁を回避しつつも国際協調を進めるための方策であったことなど新鮮な感で読むことができた。」内田外相を悪く評価する歴史書もあるが、熱河作戦が控えていた時点では、外務省本省の判断が正しかったのであろう。「ブロック経済圏についても、もちろん当時の列強の経済政策への対抗政策という側面が強くあったことは承知の上だが、独自に自由貿易経済を推進していたことも驚きであった。エジプトや中南米との貿易の推進はかなり意外である。そういえば戦前のイスラム研究の水準は相当なものだったと聞く。列強諸国への対抗ということも含むが、日本が非欧米の列強として中小諸国の希望の星であったことが実感できる。つまりは言葉通りの意味でのグローバリズムを目指したのが戦前の日本であったのかもしれない。現代のグローバリズムは欧米の価値観が全面に出ているが、戦前の日本は非欧米諸国との連帯に生き残りをかけていたと言えよう。欧米との連携を決して軽視していたわけではないが、正面きっても勝てない欧米への対抗策がグローバリズムであったのだろう。ある意味、非同盟諸国の発送を先取りしていたのかもしれない。また「東亜」の創出など現代の国際政治に通ずるような方向性も強く持っている。
書評3「著者の井上寿一氏(学習院大学教授)は、本書で「歴史の逆説の力学」(はじめに)を読み解き、「今日と共通する日本の国際化の問題」などに係る「教訓」(同前)の導出を試みている。 特に、1929年に始まった「世界恐慌」への対応に関し、英国は1932年、帝国特恵関税制度によって英連邦諸国間で「スターリングブロック」(ブロック経済化)を形成するなど、「持てる国」英国等による「世界経済のブロック化」が推展した。それに抗して、「持たざる国」日本はあくまで「国際協調主義」に基づく「通商自由の原則」を掲げていた歴史的事実は実に重たい。実際、「自由主義を掲げる日本の経済外交は、二国間通商交渉によって、経済摩擦の調整を図った」(p.177)のであるが、現代日本外交と比べ特筆に値する。 こうした日本の通商外交は、今日においても認容できよう。ただ、「持てる国(英仏等)」と「持たざる国(日独伊)」との「植民地(資源)争奪戦=世界再分割」といった平板なマルクス主義的解釈を排した展開には共感できるものの、その後の“真逆の結果=太平洋戦争”への“流れ”が足早となってしまい、惜しい感じもする。それは、日本の国内体制における“全体主義化”の問題も同様で、本書の副題である「1930年代の教訓」は掴み取れたが、「逆説の力学」を十分に説明し切れたか、というと、やや「竜頭蛇尾」に終わってしまった感がある。何れにしても、従来の「定説」を克服しようとする著者のトライアルは評価できよう。」
書評4「
1930年代というと、国際連盟を脱退した後、日本は国際的な孤立化まっしぐら、というイメージを持つ人が多いだろう。実際、歴史教科書でそのように習ってきたという人も多いはずである。これに対し、本書では逆に1930年代にこそ花開いていた経済・外交の存在を明らかにしてくれる。満州事変について、「満蒙特殊権益の保護」が目的として理解されることが多い。しかし、松岡洋右などは日中連携による満蒙開発を計画しており、満州事変はその計画を台無しにするものだった。満蒙は外国資本なくしては発展できないような「見捨てられた荒野」であり、そのため「王道楽土」はアメリカに著しい依存をする。従来、国際連盟脱退は「日本の国際的な孤児化」を招いたとされる。しかし、実際には脱退後も英仏協調路線がとられ、海軍軍縮予備交渉も英米と行われている。連盟脱退はむしろ事態を鎮静化させ協調を回復させるための策であり、実際そのように進んでいった。日本は最終的に独伊と同盟を結ぶので、独伊とは友好的に思われがちだが全く違う。この二国は人種偏見をむき出しにする国であり、反独伊・親英米の流れはかなり長く続いている。また、イタリアのエチオピア侵攻の際にはエチオピアを支持し、イタリアと強く対立する。1930年代には、英米仏もまた挙国一致体制をとっており、日本が範とするべき国は皆挙国一致であった。そのため、日本でも親英米のデモクラシー擁護者から見ても英米仏と独伊の境界線はあいまいになっていく時代であった。こうした背景が、日本の国家主義体制の基礎になっていく。世界恐慌で各国がブロック経済による封鎖をかけてくる。
そのような中、日本は一国ずつ粘り強く交渉することで、交易の道筋を見出そうとする。そうして交易をおこなう相手は地球の裏側にまで及ぶ、極めて広範な地域になる。日本の擁護する「経済圏」は、ブロック経済とは真逆の、幅広い自由貿易による活性化であり、そのために発生していたのは経済摩擦であった。」
関連記事
-

-
『シベリア出兵』広岩近広
知られざるシベリア出兵の謎1918年、ロシア革命への干渉戦争として行われたシベリア出兵。実際に起
-

-
『脳の誕生』大隅典子 Amazon書評
http:// www.pnas.org/content/supp1/2004/05/13/040
-

-
『新・韓国現代史』 文京洙著 岩波書店 を読んで、日韓観光を考える。
東アジアの伝統的秩序は、中国中心の華夷理念のもとに、東アジアの近隣諸国が朝貢・冊封の関係において秩序
-
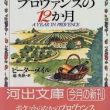
-
『プロヴァンスの村の終焉』上・下 ジャン=ピエール・ルゴフ著 2017年10月15日
市長時代にピーターメイルの「プロヴァンスの12か月」読み、観光地づくりの参考にしたいと孫を連れて南仏
-
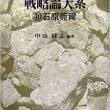
-
「世界最終戦論」石原莞爾
石原莞爾の『世界最終戦論』が含まれている『戦略論体系⑩石原莞爾』を港区図書館で借りて読んだ。同書の
-

-
『一人暮らしの戦後史』 岩波新書 を読んで
港図書館で『一人暮らしの戦後史』を借りて読んでみた。最近の本かと思いきや1975年発行であった。
-

-
日経新聞2019年5月18日見出し「池袋暴走の87歳、ミス否定 「ブレーキ踏んだ」説明」へのTanaka Yukoh氏のNewspicksのコメントが秀逸ですが、イイネは少ないです。紹介します。
大変痛ましく残念な事件ですが。ただ、こういうのは御遺族もおられる事ですから、どうぞ冷静に。
-
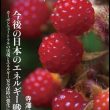
-
ウクライナ戦争の戦況集収から考える「情報」の本質 2022年7月 公研 嫌露、嫌米、アンチ公権力等の先入観が情報収集機会を減少
2022年7月の「公研」で、クライナ戦争の戦況集収から考える「情報」
-

-
英国のドライな対外投資姿勢 ~田中宇の国際ニュース解説より~
私の愛読しているメール配信記事に田中甲氏の田中宇の国際ニュース解説 無料版 2015年3月22日 h

