何故日米開戦が行われたか。秋丸機関の報告書への解説 『経済学者たちの日米開戦』
公開日:
:
最終更新日:2021/08/05
出版・講義資料
書名は出版社がつけたものであろう。傑作ではある。書名にひかれて読むことになったが、およそ意思決定には影響しなかった経済学者たちでもある。著者は、日米停戦のシナリオも作っておけばよかったのだと政策提言しているが、そんな本音が語れるぐらいなら、海軍もバカなことはしなかったであろう。
昭和16年の段階では、日米間の経済格差がとんでもなく大きく、経済的な資料に立脚する限り、日米戦争は、特にそれが2年以上の中長期戦になる限りは、完全に日本が負けることは、ごく普通の常識として一般の知識層どころか庶民にも知られていた。従って、秋丸機関の報告書も目新しいものはなく、陸軍も問題にしていなかったが、神話が出来上がったのは、戦後見つからなかったからである。そして、新史料の発見、それを通じた、神話である通説、異説への違和感について考え抜いた労作。国民の戦争熱を誰も抑えることが出来なかった(為政者も保身に傾き、天皇にもできない)ということ。戦争は国際情勢など関係なく国内問題が原因。日米の経済力を最もよく知っていた鈴木企画院総裁も戦後、国内の様々な矛盾を戦争に求めたと明言している。
ではなぜ自身の数十倍の工業生産力と豊富な資源をもつ米国に戦線布告したのか,長年の疑問に答える本である。人間が合理的な判断をしない理由を二つの理論を使って説明する。
一つは行動経済学におけるプロスペクト理論である。米国の石油禁輸で二,三年後には戦わずして屈服するという選択より,開戦すれば高い確率で致命的な敗北をするが,非常に低い確率で勝つかもしれないという選択の方を主観的に重みづけしてしまったということ。宝くじを多くの人が買うのと同じ,とこの本に書いてある。尤も,その低い勝つ確率は,ドイツがソ連とイギリスを屈服させることを前提としていたから,冷静にドイツの戦いを分析していれば,1941年10月,11月には,ちょっと待てよという判断はできたはずなのだが。しかし,これも見たくないものは見なかった,主観のバイアスが強かったということ。
二つ目は,社会心理学による説明で,集団意思決定では個人が意思決定を行うより結論が極端になることが多い,なぜなら集団の規範と一致する方向で極端な立場を表明することが集団の中での存在感を高める,という説明。当時の参謀本部では強気強気が尊ばれ,慎重意見を言えば前線へとばされたと別の本に書いてあった。政府も世の中のそういう雰囲気に流されたのだ。東條英機に,宰相の器量はない。
この二つ目は,開戦前の日本が取り得たもう一つの道として大杉一雄の本にも書いてあって,自分としては大変に心ひかれたスペインのフランコ政権のごとき「静観」を,日本が取り得なかったことも説明する。フランコは,自身の独裁政権樹立のときに戦ってくれたヒトラーからやいのの催促を受けても,第二次世界大戦へ参戦しなかった。スペインのこのやり方は,独裁者だからこそできた。専制的権力者が誰もいない日本では,こういう賢い選択ができない。独裁者ヒトラーも最後まで避けていたアメリカとの戦争を,奇襲先制攻撃という最も愚かな方法で始めてしまった。集団意思決定が最悪の結果を招いた。独裁は悪いことばかりではない。
関連記事
-

-
「脳コンピューター・インターフェイスの実用化には何が必要か」要点
https://www.technologyreview.jp/s/62158/for-brain-
-

-
人間ってなんなの?:チンパンジーの4年戦争【 進化論 / 科学 / 人 類 】タンザニア
グドール 道具を使うチンパンジーを発見 ジェーン・グドール(Dame Jane Morris Go
-
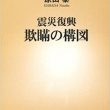
-
GOTOトラベルの政策評価のための参考書 『震災復興 欺瞞の構造』2012年 原田泰 新潮文庫
いずれ、コロナ対策としてのGOTOトラベル等の観光政策の評価が必要になると思い、災害対策等の先例を
-

-
『デモクラシーの帝国』 藤原帰一2002岩波新書 国際刑事裁判所 米国の不参加
国際刑事裁判所の設立を定めたローマ規程は、設立条約に合意していない諸国にも適用されるところから、アメ
-

-
QUORAに見る観光資源 マヤ語とは何ですか?
マヤ語とは何ですか? マヤ語の研究を高校生にして大きく押し進め、現在もマヤ文化と考
-

-
言語とは音や文字ではなく観念であるという説明
観光資源を考えると、言語とは何かに行き着くこととなる。 愛聴視して「ゆる言語学ラジオ」で例のエ
-
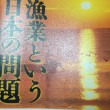
-
『漁業という日本の問題』勝川俊雄 日本人は思ったほど魚を食べてない。伝統の和食イメージも変化
マスコミによってつくられた常識は、一度は疑ってかかる必要があるということを感じていますが、「日本人は
-

-
Transatlantic Sins お爺さんは奴隷商人だった ナイジェリア人小説家の話
https://www.bbc.co.uk/programmes/w3cswg9n BBCの
-

-
『諳厄利亜大成』に見る、観光関連字句
諳厄利亜大成はわが国初の英語辞典 1827年のものであり、tour、tourism、hotelは現
