『鉄道が変えた社寺参詣』初詣は鉄道とともに生まれ育った 平山昇著 交通新聞社
初詣が新しいことは大学の講義でも取り上げておいた。アマゾンの書評が参考になるので載せておく。なお、私が関西勤務をした昭和50年代初めは、例えばフィールドリサーチに行った先で、南海バスと熊野神社の関係者が完全に共通の話題として集客の話をしていることに、むしろ驚き、有難味が失せた記憶がある。
なお新聞記事は朝日の聞蔵や読売のヨミダスなど簡単に検索ができる時代であり、多くの研究論文が生まれているようで面白い。ただ、観光の語源でも調べて分かったように、字句と概念は一致しないので、やはり読み込みが必要な部分がある。
私鉄の経営というと阪急の宝塚の成功ばかりが取り上げられ小林一三が神格化された感があるが、それが一面的な誤解に過ぎないことを教えてくれる一冊。実際、関西では近鉄が生駒聖天参詣を当初の経営の柱に据え、他にも南海電鉄高野線が高野山参詣のために整備されたことは周知の事実だが、住宅開発と観劇興行というサラリーマンの生活になじみ深い要素が目立たなかったために経営分析の要素から見落とされてきた。
初期の鉄道の経営環境には沿線には住宅地は無く、乗客を運搬する需要は他にあったのは当然のことだった。明治初期の人口集積地は大阪や東京の区部であり、運搬先は郊外に求めるのは当たり前のことだった。もともと江戸時代には伊勢参りや富士登山、地方でも金毘羅参りや出雲参りが講を組んで事業として行われていたわけで、ここにビジネスチャンスを見つけるの自然なことと言える。
その自然な流れを資料を参照し提示して論文としてまとめたのが本書です。惜しむらくは紙数が限られているため事実関係の掘り下げが浅いのと、定数的な分析がほとんど示されていないのが残念。西宮神社の新旧恵比寿参りの推移をグラフ化するだけでも理解の助けになる。しかしそんなことは瑕瑾といるべきだろう。
徒歩か馬車だけだった時代に、鉄道の出現はどれほど大きな変化だったか想像が付かない。年に1度の正月に恵方詣に出掛ける程度だった都市住民は鉄道で遠出するようになる。川崎大師に成田山、関西圏なら伊勢神宮。今に変わらぬ年始の光景が出現する。しかも新聞広告の力もあって運行が2社競合になると人気が集まる不思議。一連の動きは寺社、参詣客、鉄道会社と三方良しの社会の進化だったように思える。そして生活から旧暦が消失する後付けを示した西宮戎の記録も興味津々。心地良い読後感とともに、文化の発展とは、という問いにもなっている。
鉄道ファンであると共に、いわゆる「伝統文化」に懐疑的な私としては、非常に興味深い本だった。
日本の鉄道開業の年に行われた「太陽暦」への切り替えは、農漁村の生活に密着していた年中行事に混乱をもたらした。
と同時に、鉄道が、やや遠方の寺社への参詣手段として活用されるようになって、都市で生活する人々に、半ばレジャーとしての初詣という新しい風習を定着させることになった。
そういうプロセスを、貴重な新聞や鉄道関係の資料を用いて明らかにしてくれている。
実際、古典落語にも「初天神」というタイトルや正月風景を描いたものはあっても、「初詣」というタイトルはない。
この本で特に面白いのは、政府が「旧暦併記」を取りやめる前後の、西宮戎神社と阪神電車などとのやりとりである。そもそも、「旧暦併記」とその廃止ということは、この本を読んで初めて気が付いたことだった。「旧暦」「新暦」「月遅れ」、現在の日本の伝統行事には、この三種類が混在していること、その所以なども考えることができる。
この本を手に取った時、真っ先に思いついたのが鹽竈神社です。この神社は東北で最大の規模を誇り、そのアクセスとして主に仙石線が使用されます。「まさかこの神社を取り上げられることはないだろうなぁ〜」と思ったのですが、そのまさかで、この本でガッツリと取り上げられていました。
「元朝参り」という、1月1日午前0時になってからお参りをするという風習が宮城県内にあり、そのために電車の運行をするべく、仙石線の前身である宮城電気鉄道と、国鉄、さらには地元のバス会社をも巻き込む、まさに三つどもえのバトルロワイヤルが演じられていたそうです。新暦の1月1日のみならず、旧正月でも行われていたそうですが、これに関しては私はニュースや新聞で聞いたことも見たこともありません。
ちなみに、この元朝参りのために仙石線では終夜運転を長らく行っていたのですが、残念ながら2016年は運転を取りやめることになりました。2017年も行わないようです。
「社寺参詣」という”伝統的風習”と捉えられがちなものが、「鉄道」という”近代文明”によってどれだけ影響されてきたのかをまとめた一冊。明治~昭和初期の関東・関西を主な対象として話がまとめられている。学術的な鉄道研究として、最近は新聞記事・広告や社寺史料を丹念に研究するのがトレンドらしく。この著書もそういう書籍の一冊。こういう学術畑からの一般書は、情報量にまみれてしまい全体像を掴みにくい本が多いのですが、この本はその豊富な情報量の割には話の流れがわかりやすく読みやすい。古い鉄道会社名が鉄道ファン以外には理解しにくい点を除けば、一般者も普通に手に取れる一冊だと思う。詳細は読んでいただいた方が早いので省略しますが、
・東西の私鉄が、閑散期である冬の集客に寺社参詣を見込んでいたこと
・その集客惹句は必ずしも宗教的伝統に忠実とは言いがたく、使いやすい惹句は東西の鉄道会社間でもインスパイヤされたこと
・社寺の側も鉄道会社による参詣者増加効果に期待していたものの、伝統との兼ね合いで意見が食い違うこともあったこと
などが特に興味深かった。個人的に気になったのは、「旧暦・新暦」の兼ね合いを例示するために出された宮城県塩竈神社参詣(元朝詣で)輸送に関する記述。宮城が元旦終夜運転には全国的に見て早めに手を出してるのも意外なら、この終夜運転が新暦元旦だけでなく、旧暦元旦にも行われたことも驚き。旧暦元旦の臨時便は昭和に入っても運行されていたとの由。
仙台七夕が旧暦を意識した日程になっているように、仙台では割と旧暦ががんばったっぽい、とは感じていましたが、正月までそうだったとは知らず。仙台の祭の変遷は個人的に調べてみてもいいか、と感じさせるものがありました。「社寺と鉄道」の関係に注目されている一冊ですが、引用されている鉄道広告からは各鉄道会社の社風や様々な試みも読み取れ、実に楽しい一冊。歴史鉄必読の良著です。
関連記事
-

-
『休校は感染を抑えたか』朝日新聞記事
https://www.asahi.com/articles/ASP6J51TNP6CULEI0
-

-
動画で考える人流観光学 観光資源、質量の正体は一体何なのか -質量の起源-
https://youtu.be/TTQJGcu-x3A https://
-
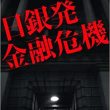
-
英国通貨がユーロでない理由 志賀櫻著「日銀発金融危機」
ポンド危機と英国通貨がユーロでない理由 サッチャー政権
-

-
2019年11月9日日本学術会議シンポジウム「スポーツと脳科学」聴講
2019年11月9日日本学術会議シンポジウム「スポーツと脳科学」を聴講してきた。観光学も脳科学の
-

-
『結婚のない国を歩く』モソ人の母系社会 金龍哲著
https://honz.jp/articles/-/4147 書によれば、「民族」という単
-

-
『ざっくりとわかる宇宙論』竹内薫
物理学的に宇宙を考察すればするほど、この宇宙がいかに特殊で奇妙なものかが明らかになる。マルチバー
-
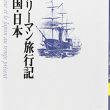
-
『シュリューマン旅行記』 清国・日本 日本人の宗教観
『シュリューマン旅行記 清国・日本』石井和子訳 シュリューマンは1865年世界漫遊の旅に出か
-
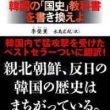
-
書評『大韓民国の物語』李榮薫
韓国の歴史において民族という集団意識が生じるのは二十世紀に入った日本支配下の植民地代のことです。
-

-
世界の運営を米国でなく中露に任せる 2023年6月7日 田中 宇
https://tanakanews.com/230607armenia.htm 5月25日、
-

-
「起業という幻想」白水社 スコット・A・シェーン 職を転々として起業に身をやつす米国人の姿は、産学官が一体になって起業を喧伝する日本社会に一石投じることは間違いない。
マイクロソフトのビル・ゲイツ、アップルを立ち上げたス

