『雇用破壊』森永卓郎著 角川新書 2016年 その他
公開日:
:
最終更新日:2023/05/31
路銀、為替、金融、財政、税制
森永卓郎氏は直接面識はないは、海外留学後日本専売公社から当時のいわゆる天上りで霞が関に出向し、その後エコノミストに転向した才人である。運輸省にも大手の銀行等から一流大学出身者が出向してきていた。私が勤務していた官房企画部門などは、出向者の方が主力で、プロパーは課長と課長補佐ぐらいというところもあったくらいである。許認可部門が主流の運輸省では、具体的な権限を持たない官房企画部門は学士の墓場と悪口を言われていた。しかし経済企画庁出向経験のある先輩に、当時言われたことは、むしろこちらの方が霞が関全体では主流だということであった。確かに、大来佐武郎、堺屋太一をはじめ、近年では竹中平蔵氏等が存在する。特に竹中平蔵氏は日本開発銀行から大蔵省に出向し、今日の基盤を築き上げた。運輸省でも国鉄から民営鉄道部都市交通課長に出向して、交通評論家になられた角本良平氏がいた。国鉄は運輸省の本家だから例としては当たらないかもしれないが。
森永氏は自著の中で、2012年時点で2億円の金融資産を蓄えたと記述しておられる。定職の私立大学教授のもと一年を300万円で暮らす方法を実践しておられたようだから、それくらいは貯蓄できたであろう。賢明な生き方である。専売公社を勤め上げ、関連会社に天下りしていても、退職金だけではそれほどの貯蓄はできなかったであろう。著書の中で、本業の経済評論はアンチ権力的なコメントが政権、番組作成者に疎んじられ出番が減少したものの、バラエティー番組出演は減少しなかったと記述している。依頼があった原稿はすべて断らないでこなしていたようだ。趣味の収集物展示ように、博物館を東京近郊に2億円弱で設立されてもいる。
本書の内容は、以下、amazonによる。 正規労働者が4割に! 年収300万円すら危うい 格差拡大が加速。 庶民は奴隷になる。雇用破壊のなか、超格差社会が加速する 我々の選択肢は、1資本の奴隷、2ハゲタカ、3貧しくともアーティスト この3つの選択肢から生き方を選ぶことになる。カギとなるのは、機械にはできない創造的な仕事だ!
●主な内容
序章 認識されないまま進む超格差社会への道
第1章 お金持ちを目指しても幸せにはなれない
第2章 雇用を破壊する三本の毒矢
第3章 第四の産業革命がもたらすもの
第4章 格差拡大にどう向き合えばよいのか
書評では、
本書でも言及しているが(p.12)、2000年以降の勤労者の実質所得の推移は、民主党政権時代は横ばいだったものの、第一次・第二次安倍政権下で見事な程、実質所得が低下している。また、本書でも言及しているように貧困率は世界でも最悪レベルである。安倍政権が喧伝してきたアベノミクス(実際には浜矩子氏が呼ぶように「どアホノミクス」が相応しい)は、1%層(超富裕層)には高株価等の利益をもたらしたものの、99%層(庶民層)は窮乏化しただけであったことが誰の眼にも明らかになりつつある。それでも安倍政権の支持率が高いとは、摩訶不思議である。メディア支配による政権批判封じが効果を挙げているとしか考えられない。メディアの責任は実に重大である。
著者は、安倍政権が掲げる成長戦略のうち、(1)派遣労働法改正による派遣労働の固定化、(2)高度プロフェッショナル制度の導入による残業代ゼロ体制、(3)解雇規制緩和による労働市場の流動化、の三つを「雇用を破壊する三本の毒矢」と断罪している。マルクスが喝破したように、資本は利益の源泉として一層の人件費圧縮を合法的に実施し、ほとんどの労働者はますます奴隷化の危険に晒されるのだ。
著者はこのような時代における庶民層の選択肢として、(1)資本の奴隷に甘んじる、(2)ハゲタカ(富裕層)への仲間入りを目指す、(3)貧しくともアーティスト(自分の趣味)に生きる、の三つを挙げている。著者は普通の家庭に育った人間が富裕層に喰いこもうとすればハゲタカになる覚悟が必要で、決して幸せにはなれないと説く。そして自らの経験を開陳しながら、このような時代に自分を見失わずに、趣味を持って楽しく生きることを勧めている。
昨今の殺伐とした社会状況(障害者を狙った無差別殺人、隣国人へのヘイト発言や行動など)を見ると、本書が指摘するような「庶民の奴隷化」の進行が、鬱憤を晴らすための弱者への攻撃として噴出しているように思えてならない。また、庶民が「超富裕層」の仲間入りをしたいなどと思い込むと、会社の中で自分を殺して上司のご機嫌取りをするか、不正や悪事に手を染めるかなどをして人間性を失うことになる、という本書の指摘にも同意する。本書は、超格差社会の進行の中で、庶民がささやかでも幸せに生きるためのヒントを提供している。
アベノミクスとは何なのかを、アベノミクスが発表された時点で正しく見抜かれています。
第一の矢と第二の矢の金融緩和と財政出動は、他国も行なっており日本の競争力確保のためにも良い。しかし第三の矢の成長戦略が、弱者を切り捨てる格差拡大政策だと述べています。
これは2017年現在で見てもその通りで、株高政策は土地や株を持たない庶民にはほとんど関係がありません。
(トリクルダウンなど「その果実で!」と連呼していたのも馬鹿にしてるなあと思ってましたし、現在ではそんなことを一言も言わなくなりました。3本の矢の話もしませんね。矢はどこに飛んでいったんでしょうか。)
「アベノミクス戦略特区」で都市部集中になるという主張も、地方創生が虚しく響く今の一極集中の状態を、まさに言い当てています。
また、教育資金贈与の非課税や年少扶養控除の復活など、国民のために見せかけて金持ちしか得をしないことをやっていることも書かれています。
書いてある中で大きく様子が違うことといえば、TPPが頓挫したことですが、これはトランプ大統領の当選によりま
デフレの真実を明かし、金持ち理論から日本経済を読み解く一冊。
端折って言えば、日銀然り既得権益を守ろうとする連中がデフレを緩和せず、税の負担も資産の少ない庶民に当てられている、ということだ。
何か扇情的な題名ではあるが、法人税の20%台減税然り、消費税増税の逆進性然り、確かに資産家に有利な政策がてんこ盛りな世の中である。
今はインフレ・ターゲットが掲げられて(いるはず)、日銀副総裁にも岩田規久男氏が勤めている中、金融緩和は遅々として進んでいない印象だ。
そういった観点から直截的に表現されると、上記のことも多少首肯できる。
分かりやすい内容で「なぜデフレは庶民に不利なのか」という観点から読んでいけば、今の経済状況を見直せる良いきっかけになせるかもしれない。
2012年上梓の本書で、2014年・2015年には震災恐慌が訪れるとあるが、まだそういった兆しは見えない…森永氏の思い描くウハウハな金融市場は見えてこないし、どちらかというと日経平均もジワジワ上昇し続けている。
森永氏の3億円の資産が働いてくれる日は、もう少し先なのかもしれない。
───我々にとって一番恐ろしいことは、庶民が「デフレの仕掛け」に気づくことだ。選挙の大半の票を持つ庶民が「徹底的な金融緩和を行ってデフレから脱却しろ」と言い出したら、もうどうにも止められない。だから、庶民には二つのことを言い続けなければならない。一つは「インフレは恐ろしい」ということと、「金融緩和なんてしてもデフレ脱却には効果がない」ということだ。(p.80)
関連記事
-

-
地方都市コンベンション関連団体によるシンフォニーでの発表会参加 2016年3月3日
ネット世界で知り合った元読売新聞の社員の方のお誘いを受けて、久しぶりにシンフォニー2時間の旅に参加す
-

-
パブリックコメント「道路運送法における登録又は許可を要しない運送の態様について」の一部改正に関する意見公募について
道路運送法の有償性に関する事務連絡の改正が検討されており、パブリックコメントが募集されたので、応募し
-

-
◎『バブル』永野健二著
GHQの直接金融主体の経済改革からすると、証券市場と証券会社の育成が不可欠であるにもかかわ
-

-
「宿泊税とオーバーツーリズム」論議への批判
私の博士論文では、観光税制を詳しく取り上げたが、当時は誰も関心がなかった。いま議論されている宿泊税
-

-
英国のドライな対外投資姿勢 ~田中宇の国際ニュース解説より~
私の愛読しているメール配信記事に田中甲氏の田中宇の国際ニュース解説 無料版 2015年3月22日 h
-

-
保護中: 『from 911/USAレポート』第827回 「アベノミクスの功罪と出口シナリオ」冷泉彰彦 これだけ識字率と基礎算術と社会性の訓練を受けた分厚い人口を抱えた大国が、利幅が薄く労働集約型の観光業を主要産業とするという、どう考えても悲劇的な産業構造に追い詰められた、これは7年半にわたって改革に消極であったことのツケにしても、随分と妙な方向になったと思います
結果的に、これだけ識字率と基礎算術と社会性の訓練を受けた分厚い人口を抱えた大国が、利幅が薄く労働
-
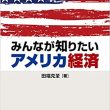
-
書評『みんなが知りたいアメリカ経済』田端克至著
高崎経済大学出身教授による経済学講義用の教科書。経済、金融に素人の私にはわかりやすく、しかも大学教
-

-
太平洋戦争で日本が使用した総費用がQuoraにでていた
太平洋戦争で、日本が使った総費用はいくらでしょうか?Matsuoka Daichi, 九州大学で経
-

-
明治維新の評価 『経済改革としての明治維新』武田知弘著
明治時代の日本は世界史的に見て非常に稀有な存在である。19世紀後半、日本だけが欧米列強に対抗し
-

-
2013.8.19 そして預金は切り捨てられた 戦後日本の債務調整の悲惨な現実 ――日本総合研究所調査部主任研究員 河村小百合
ここで紹介されている「 昭和21年10月19日には、「戦時補償特別措置法」が公布され、いわば政府に
