2 中国人海外旅行者数の増大、中国国内旅行市場の拡大が及ぼす東アジア圏への影響
公開日:
:
最終更新日:2023/05/20
人口、地域、, 路銀、為替、金融、財政、税制
○ 海運の世界で発生したことは必ず航空の世界でも発生する。神戸港は横浜港とともにコンテナ取扱個数において世界のベストテンに入る港であったが、阪神淡路大震災を経てその順位を急激に下げて行った。港湾関係者はその原因を物流コストの増大に求め、政府は物流施策大綱を閣議決定した(拙著『経済構造改革と物流』参照)が、日本全体の合計コンテナ取扱個数よりも香港港の取扱個数が多い原因は、港のコストが高いのではなく、港の背景にある中国からの膨大な雑貨の力にあるということに気付かされた。現実に香港のポートチャージの方が高かったのである。今やアジアのコンテナは中国の港を中心に流通している状態である。コンテナの世界で起きたことは航空の世界でも時間を経て発生する。中国経済の成長、中国人の個人消費の増大とともに、中国の航空旅客市場は爆発的に増大するはずであるからである。
○ 航空市場を展望するには日米航空協定見直しの歴史から学ぶことがよい。戦後の国際航空体制はシカゴ条約により2国間政府交渉に基づく航空協定(条約)が中心であった。敗戦から立ち直っていない日本では海外に飛行機を飛ばす力などなく、米国企業が中心となった日本を経由する航空路線が前提となっていた。その後日本が国力を回復するに従い、日米航空不平等条約の解消が長年の懸案事項となった。航空市場の増大に伴い二国間協定による体制は効率が悪く、アメリカはオープンスカイ政策を展開するように変化していった。そこには、巨大な国内航空市場を背景とできる有利な立場のアメリカ航空企業の思惑もあった。かつて七つの海を支配した英国が海運自由の原則を標榜したのと同じ論理がそこにはあったのである。今後の我が国をめぐる国際航空市場は確実にアジア、しかも中国市場を中心に展開すると考えた方がよいであろう。巨大な国内航空市場を抱える中国航空企業の思惑は、日本の国際国際航空市場をも動かすであろう。
○ 中国人海外旅行者数の増大
アメリカと同様に、中国が経済力をつければつけるほど、中国と周辺国の関係は朝貢ー冊封類似の「中央ー周辺」メカニズムに戻ってゆくことは間違いがない。日本にとって政治的には日米関係が当分の間基軸であることには変わりはないであろうが、人流においては日中関係は変化せざるを得ない。それを認識するかしたくないかでその政治姿勢にも影響はあるであろうが、日本の歴史は、朝貢ー冊封体制を中心に、中国との関係をどう取るかで動いてきたことは、昔も今も変わりはないのである。
中国人海外旅行者数の増大は海外旅行市場に大きな影響を与えている。日本において中国人の爆買が話題になっているように、BBC等においても海外における中国人アウトバウンド数の増大を報道している。2014年の中国人海外旅行者数が世界最大の一億人となり、世界の国境を超える旅行者数11億人の1割を占めるようになった。中国人の世界に占める人口比が二割であることから推測しても、これからも増大すると予測され、中国国家旅游局は2020年に5億人になると予測している。もし中国がその送客力に自覚すれば、大英帝国がインド大陸ムスリムのメッカ巡礼者の数を操作することにより、オスマン帝国に影響を及ぼしたと同様の戦略を講じることができるからである。観光市場の小さな地域であればある程、その影響も大きくなる。現在でも日本の地方公共団体は、地方空港の国際線を維持するため、中国航空企業詣で行っているのである。
○ 巨大国内市場のもつ意味
中国の国内人流市場は端的に人口比率だけで考えてもわが国の10倍であり、今後の経済成長を勘案すれば、世界最大級の市場となる。国際人流市場においてはカボタージュ規制がルールである。国際市場はオープンスカイ化してきているが、中国国内市場では中国国籍の航空機しか運航できない。しかしながら、航空会社経営においては、巨大国内市場を背景に国際市場に乗り出せる企業が有利であることから、今後は中国大陸周辺国際市場において、中国企業の更なる展開が予想される。
陸続きのモンゴルや朝鮮半島(南北の融和が前提であるが)等においては、直接線路が接続する鉄道事業経営は、2地点間を接続する航空路線とは異なり、中国鉄道政策の影響を直接受けるものである。朝貢ー冊封時代の中国は、日本に対する影響以上に、朝鮮等に対して影響力を持っていた。朝鮮半島やモンゴル等においては中国の鉄道政策を無視して行うことは困難な状況になってゆくであろう。
○ 歴史認識の観光資源化(朝貢ー冊封体制の再評価等)
東アジアの国際観光を考える場合、政治的価値判断を離れた興味の対象として観光資源を見つめれば、観光活動は活発化することを認識しておきたい。中国や韓国が歴史認識でこだわる背景を理解しておけば、その背景を形成するものですら観光資源となるからである。
歴史研究の基本原則は「実事求是」という共通認識はあるものの、中国人研究者は中国史を多民族からなる中華民族史とし、その周縁に対外関係史を位置付けている。古代以来の世界秩序も、朝貢ー冊封、植民地、契約の三部類とし、中国歴代王朝は「冊封―朝貢」による「中央―周辺」メカニズムを中心として東アジアをおおよそ一つの秩序ある地域として組み立ててきたと考えている。これは王朝が周辺の国際関係を維持してゆくための策略であったからである。一方、日本は「九世紀末に日本の中央官庁と天皇の書斎に当時の中国国内のすべての文献の五割の漢文典籍が収蔵されていた。19世紀初期、日本は中国の典籍の七割から八割を持っていた」と認識されている。いわば日本から見て中国文明はギリシャローマ文明であった。そのうえで、中国の歴史研究者は、その骨格を唯物史観によるものとすると明言する。
日清戦争により冊封体制が解体する危機時に、朝鮮は主権を確立し独立を維持するため、専制皇帝を中心にすえた国づくりを迫られた。その結果万国公法の論理と中華的伝統に基づいた皇帝制が折衷した大韓国国制が制定された。1905年第二次日韓協約をめぐり1992年に発生し「旧条約合法・不法論」が繰り広げられているそのもとは、大韓国国制のかかえる、皇室の家産であった国家体制に存在するところもある。旧条約が合法に締結された,あるいは法的に不成立とする主張は,実際には国際法的判断ではなく,20世紀初頭時点での日韓間の条約締結という歴史的事実を認定する域を出るものではない。大韓民国憲法が「3・1運動で成立した大韓民国臨時政府の法統」を継承するとうたっていることを認識しておくことが重要である。
関連記事
-

-
英国のドライな対外投資姿勢 ~田中宇の国際ニュース解説より~
私の愛読しているメール配信記事に田中甲氏の田中宇の国際ニュース解説 無料版 2015年3月22日 h
-

-
国際観光収支の黒字に意味があるのか?
観光基本法が全面改正された法制上の大きいな理由は、中央集権規定の廃止であった。農業基本法等戦後成立し
-

-
地方都市コンベンション関連団体によるシンフォニーでの発表会参加 2016年3月3日
ネット世界で知り合った元読売新聞の社員の方のお誘いを受けて、久しぶりにシンフォニー2時間の旅に参加す
-

-
矢部 宏治氏の「なぜ日本はアメリカの「いいなり」なのか?知ってはいけないウラの掟」
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/52466 外務省がつ
-

-
7月21日 第二回観光ウェアラブル委員会を開催して
満倉靖恵慶応大学理工学部准教授と㈱ナビタイムジャパン野津直樹氏に講演を頂いた。 満倉先生は「脳
-
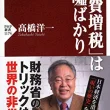
-
『戦後経済史は嘘ばかり』高橋洋一
城山三郎の著作「官僚たちの夏」に代表される高度経済成長期の通産省に代表される霞が関の役割の神
-

-
Quora Covid-19の死亡者はアメリカが27.9万人、日本が2210人 (12/06現在) です。日本では医療崩壊の危険が差し迫っているとの報道がありますが、アメリカに比べて医療体制が貧弱なのでしょうか?
12月16日現在、アメリカでの死亡者数は約30万4千人、そして日本での死亡者数は2600名足らずで
-

-
太平洋戦争で日本が使用した総費用がQuoraにでていた
太平洋戦争で、日本が使った総費用はいくらでしょうか?Matsuoka Daichi, 九州大学で経
-

-
『日本人のためのアフリカ入門』『アフリカを見る アフリカから見る』白戸圭一
アフリカ旅行にあたって、白戸圭一氏(毎日新聞OB)の「日本人のためのアメリカ入門」(2011年)「
-

-
21世紀を考える会「仮想通貨の現状」岩下直之京都大教授の話を聞く 2018年4月20日
Bitcoinの発掘の仕組み 256ビットの最初の30個は零が続かなければらないという約束。ハッシュ
- PREV
- 養老猛の教育論
- NEXT
- ウェアラブルデバイスを用いた観光調査の実証実験

