ウェアラブルデバイスを用いた観光調査の実証実験
公開日:
:
最終更新日:2016/11/25
観光学評論等
動画
https://youtu.be/Sq4M3nvX6Io
10月29日にg-コンテンツ流通推進協議会で行っているウェアラブルデバイスを用いた観光調査の実証実験を行った。観光調査ではわが国で初めての実証実験であろう。国土交通省時代に、自ら提唱して人流情報を位置情報デバイスを用いて収集する実験を行ったが、未だにパーソントリップ調査等では活用されていないので、提唱するだけで終わってしまわないように気をつけなければならない。
観光資源論が観光学の中心であるが、若手研究者の論文は、アンケート調査を基に分析しているものにとどまっており、アンケート調査自体の限界もあるが、アンケート自体が科学的な根拠に基づいているのかという点で疑義があるのであるから、観光学の発展には大いに疑問を感じていたところである。選択肢方式(大変良い、良い、普通、悪い、大変悪い)に基づくものしかなく、申告ベースであった。更には、富士山と桂離宮の観光資源としての評価をそれぞれアンケートで収集して比較しても、意味がないことがわかっているからである。
g-コンテンツ流通推進協議会において、人の感性や心拍数等をウェアラブルデバイスを用いて把握できることが紹介された。このウェアラブルデバイスを用いて、観光資源に対する観光客の感性の違いを把握できないかという提案がなされ、まずは実証事件を行ってみようと言うことで、今回の運びとなった。日本に留学してきている大学生(ナイジェリア人、中国人)と日本人の三人に被験者になっていただき、スカイツリー、浅草、秋葉原を観光してもらい、その感性データを収集したわけである。メンバーの一人であるJTB職員の野添幸太氏が撮影した動画のURLを記載しておくので参考にしてもらいたい。詳細は、g-コンテンツ流通推進協議会として11月中に発表。
DNAの塩基配列がすべて読みとられても、その配列の意味については一つ一つ実際に即して分析をしていかないとその意味はわからないのと同様に、感性データが収集されても、その反応があらわれる意味は、観光資源と観光客の関係や、周辺の事情等を把握しておかなければ解析できない。従ってウェアラブルデバイスを活用したからといって直ちに解析できるものではない。むしろ逆に、観光行動のデータマイニングにより、これからの若手観光学者の活躍しなければならない場面が大幅に増加したということになるのであろう。
結果としてあらわれる複雑な人の心の動きはウェアラブルデバイスを活用すればヒトの移動と脳の反応の関係に関してデータ取得の可能性が開かれることになった。これからは、観光資源に対する人の脳の反応が、その人の属性や周りの環境等に対応してどのように出現していのかを深く分析することにより、観光行動の科学的分析が可能となると確信している。さらに ヒトの移動、宿泊等を含んだ人流概念を発生させる契機もそこにあり、いずれは観光学は脳科学へ収斂すると思っている。スマートフォンの登場により、時々刻々発生するヒトの移動に対するニーズにリアルタイムの対応が可能となった。移動にとどまらず、物流でいえば保管場所にあたる住所、居所、宿所の管理を含めた人流概念としてとらえることが可能となった 。さらに、ビッグデータの活用により、先回りして人流ニーズに対応することも可能となってきている 。人流SCM (サプライチェーンマネジメント)の登場である。
また、今後は行政機関や企業において予算を準備し、ウェアラブルデバイスが経済的にも簡便に利用できる環境を整えてゆくことも重要な課題である。このまま活用されなければ民間企業で開発された折角のウェアラブルデバイスが、市場から姿を消す可能性もあるからである。
この実証実験が、科学的観光調査の第一歩となる記念すべきモノになることを確信する次第である。
関連記事
-

-
学士会報第20回関西茶話会「新興感染症の脅威と現代世界」光山正雄
感染症は今も世界の人々の死因第一位 歴史上の重大感染症 ①ペスト 14世紀 欧州で大流行 当時の
-

-
辛坊正記氏の日本の中小企業政策へのコメント
下請け泣かせにメス、政府が価格交渉消極企業を指導-150社採点 Bloomberg 2023/02
-

-
『科学の罠』長谷川英祐著「分類の迷宮」という罠 を読んで
観光資源論というジャンルが観光学にはあるが、自然観光資源と文化観光資源に分類する手法に、私は異議を唱
-

-
観光学が収斂してゆくと思われる脳科学の動向(メモ)
◎ 観光学が対象としなければならない「感情」、「意識」とは何か ①評価をする「意識」とは何か
-

-
『訓読と漢語の歴史』福島直恭著 観光とツーリズム
「歴史として記述」と「歴史を記述」するの違い なぜ昔の日本人は、中国語の文章や詩を翻訳する
-

-
『佐藤優さん、本当に神は存在するのですか?』メモ
竹内久美子×佐藤優 著 文芸春秋 本当に対談で語られたことなのか、発行済みの著作物をもとに編集部が
-
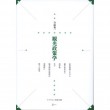
-
羽生敦子立教大学兼任講師の博士論文概要「19世紀フランスロマン主義作家の旅行記に見られる旅の主体の変遷」を読んで
一昨日の4月9日に立教観光学研究紀要が送られてきた。羽生敦子立教大学兼任講師の博士論文概要「19世紀
-

-
字句「美術」「芸術」「日本画」の誕生 観光資源の同じく新しい概念である。
日本語の「美術」は「芸術即ち、『後漢書』5巻孝安帝紀の永初4年(110年)2月の五経博士の劉珍及によ
-

-
脳波であらすじが変わる映画、英映画祭で公開へ
映画ではここまで来ているのに、観光研究者は失格である。 http://jbpress.isme
-

-
日本の観光ビジネスが二流どまりである理由
日本の観光ビジネスが二流どまりになるのは、人流に関する国際的システムを創造する姿勢がないからです。

