観光資源、観光行動の進化論
公開日:
:
最終更新日:2023/05/29
観光学評論等
「クラシック音楽に隠された「進化の法則」、東大京大の研究者が発見」tいうひょだいの興味深い記事を発見した。
jhttps://newspicks.com/news/3371305/body/?ref=index
私も感性アナライザー等を駆使してデータ集めを行い、解析を行って、観光資源あるいは観光資源を対象とする観光行動(おそらく人流分析になると思われるが)を研究すべきと思っていたので、興味深く読んだ。
「新奇性と典型性の間のバランスは、他の文化様式においても重要です。今回のモデルは、音楽データのみならず、他の文化的データの分析にも役立つはずです 」という結論は観光研究者がまなばなければならないことである
進化とは、個体の集団に適用されるアルゴリズム的なプロセスである。進化が起こるには、集団内のそれぞれの個体に、何らかの形で差異がある必要がある。たとえば、外見や行動の違いだ。さらに、これらの個体は、新しい世代の個体に特定の形質(特徴)を引き継がせる(継承させる)能力を持っている必要がある。そして、集団の存在している環境は、特定の形質を持つ個体を選択して生き永らえさせる一方で、別の形質を持つ個体を淘汰するものでなければならない。最後に、これらの段階を何度も繰り返す反復の過程が必要だ。
このプロセスにおける細部の違いは、進化の起こり方の軽微な違いにつながる。ある形質(たとえば、抗生物質耐性)が良い結果をもたらす場合、その形質は、まさに統計的なパターン通りに集団内に急速に広まり得る。近年では、大規模な遺伝情報データベースの登場に伴い、統計学者たちがこうしたパターンを研究し始めており、パターンを規定する進化の数学的法則を見い出しつつある。
作曲家76人による9996曲を調査
ここで生じる興味深い質問の1つは、同じアプローチを音楽にも使えるかということだ。
中村研究員と金子教授は、1500年から1900年の間に活動した76人の作曲家による9996曲の音楽を調べ、その答えを探し出すことにした。それぞれの曲をMIDI(楽器デジタルインターフェイス)形式にしたファイルを用いて、曲を構成する音の高低と間隔の順序立った一連の並びを調査した。
文化的現象を研究する上での1つの課題は、追跡が可能な、継承の基本単位を見つけることだ。生物学ではその単位は遺伝子であり、遺伝子が集団内に広まる様子は簡単に追跡できるようになった。
しかし、音楽において、同じような役割を持つ単位を定義するのはずっと難しい。そこで2人は、三全音と呼ばれる不協和(響きの悪い)音程の出現など、音楽における稀な事象を特定して継承の単位として使った。続いて、これらの単位がどれだけ頻繁に起こり、数世紀を経る中でどれほど広まったのかを調べた。音程が3全音離れた2つの音を同時に出す三全音は、一般に、響きの悪い不快な音程と考えられている。16世紀に作曲された曲には稀にしか登場しないが、時代を経るにつれて一般的になっていった。音楽学者はずっと、新しい曲が人気を集めるには、新奇性がありながら、既存の音楽の伝統とも結びついていなければならないという仮説を立ててきた。つまり、ある曲が人気を博するには、新しい、あるいは稀な音楽的事象が、典型的な事象と一緒に含まれていなければならないということだ。
こうした新しい曲が人気を集めると、稀な音楽的事象は広まっていく。三全音にもまさにこの通りのことが起こっていた。「1500年から1900年までの間に、三全音の現れる頻度(確率)の平均と標準偏差は増加の一途をたどりました」と、2人の研究者は述べている。
「統計的な進化則として定式化」
しかし、ここで重要な疑問が生じる。稀な音楽的事象の広まりが伝播の一般的なメカニズムによるものなのか、個々の作曲家の独特な行動による結果なのかということだ。それを調べるために、中村研究員と金子教授は、これら2つの状況を見分けられる進化の数学的モデルを作成した。そして、三全音の使用頻度が増加してきた様子が、伝播の原則となる「ベータ分布」と呼ばれる統計的法則に正確に従うことを発見した。
音楽の進化のしかたを理解する上で重要な影響を与える興味深い研究と言えるだろう。
中村研究員と金子教授は、この研究結果は、文化的進化が文化様式の伝播と選択の一般的なメカニズムを通じて起こることを示すものだと語る。
「音楽文化におけるいくつかの動向は、個々の作曲家の状況によって起こるというよりは、むしろ、統計的な進化則として定式化できると結論づけられます」。
同じアプローチは、他の文化的現象の進化を探り出すのにも使える可能性がある。「新奇性と典型性の間のバランスは、他の文化様式においても重要です。今回のモデルは、音楽データのみならず、他の文化的データの分析にも役立つはずです」さまざまな研究チームがすでに、言語、他の音楽のジャンル、さらには科学的な話題における進化の力学に注目している。今回明らかになった文化的進化の形式が、科学や工学にどのような影響を与えてきたのか、今後の研究に向けてのギャップがどこにあるかを知ることができれば興味深い。
(参照:arxiv.org/abs/1809.05832 : Statistical Evolutionary Laws in Music Styles:音楽の様式における統計的な進化則)
原文はこちら(英語)。
(執筆:エマージングテクノロジー フロム アーカイブ/米国版 寄稿者、写真:alexskopje/iStock)
This article is provided by MIT TECHNOLOGY REVIEW Japan. Copyright © 2018, MIT TECHNOLOGY REVIEW Japan. All rights reserved.
この記事は、株式会社KADOKAWAが、米Technology Review社との許諾契約に基づき、再許諾しました。一部の見出し、写真等は株式会社ニューズピックス等の著作物である場合があります。
関連記事
-

-
人流抑制に関する経済学者と感染症学者の意見の一致「新型コロナ対策への経済学の貢献」大竹文雄 公研2021年8月号No.696を読んで
公研2021年8月号No.696にコロナ関連の有識者委員等である、行動経済学者大竹文雄氏の「新型コ
-

-
『仕事の中の曖昧な不安』玄田有史著 2001年発行
書評ではなく、経歴に関心がいってしまった。学習院大学教授から東京大学社研准教授に就任とあることに目
-

-
グアム・沖縄の戦跡観光論:『グアムと日本人』山口誠 岩波新書2007年を読んで考えること
沖縄にしろ、グアム・サイパンにしろ、その地理的関係から軍事拠点としての重要性が現代社会においては認め
-

-
自動運転車とドローン
渋谷のスクランブル交差点を見ていると、信号が青の間の短い時間に、大勢の人が四方八方から道路を横断して
-

-
新語Skiplagging 「24時間ルール」と「運送と独占の法理」
BBCの新しい言葉skiplagging
-

-
Ctripの空予約騒動について 大山鳴動に近い騒ぎ方への反省
「宿泊サイト、予約しない部屋を販売」といった表題でテレビが取り上げ、関係業界内ではやや炎上気味であ
-
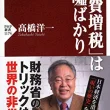
-
『戦後経済史は嘘ばかり』高橋洋一
城山三郎の著作「官僚たちの夏」に代表される高度経済成長期の通産省に代表される霞が関の役割の神
-

-
町田一平氏の私の論文に対する引用への、厳しい意見
町田一平氏がシェリングエコノミーに関して論文を出している https://m-repo.l
-

-
CNN、BBC等をみていて
誤解を恐れず表現すれば、今まで地方のテレビ番組、特にNHKを除く民放を見ていて、東京のニュースが地方
-

-
加太宏邦の「観光概念の再構成」法政大学 法政志林54巻4号2008年3月 を読んで
加太宏邦の「観光概念の再構成」法政大学 法政志林54巻4号2008年3月の存在をうかつにも最近まで知
