角本良平著『高速化時代の終わり』を読んで
公開日:
:
最終更新日:2023/05/05
観光学評論等
久しぶりに金沢出身の国鉄・運輸省OBの角本良平氏の『高速化時代の終わり』を読んでみた。本を整理していて偶然出てきたからである。1975年に書かれた本である。氏は、高名な交通評論家で、国鉄分割民営化を早くから主張していた研究者でもあるが、この時点ではまだ明確にはなっていない。
「高速化時代はひとまず終わった」「貨物はできるだけ「運ばない」工夫をしなければならない」「旅行回数は当然増加するはずのものである」と主張されている。やはり専門家の予測でも将来の技術開発を見通すことは難しいものであり、デルファイ法の限界を示している。夢の乗物の可能性を、アポロ計画で人類は月旅行に成功したが、それがいかに巨費をようするかが現実に明示されて夢はしぼんでしまったと記述されるが、宇宙観光の専門家は大気圏外への旅行はその気になれば商業化できたと考える人が多い。ロケット技術は相当古い技術なのである。それができなかったのはロケット専門家集団の独善性によるのではないかと考える。従って、イーロンマスク等があらためてチャレンジしているのであろう。
「これからは変化の少ない安定した社会が出現する」と記述される。変化が少ないのか多いのかは主観的な部分もあり、何とも言えないが、すぎさって見ればあまり変わり映えしないのかも知れない。固定電話が携帯に変わろうが本質的なことは変わっていないかも知れない。
「日本人の住み方は石の文化の国に比べて変化を受け入れるのに極めて柔軟であった」と感想を記述する。その例として「東京とパリを比べて両者とも路上駐車が増加し交通マヒの恐れがあった」「木の文化の日本は、車庫の義務付けをしたが、19世紀以来の5,6階建ての建物がぎっしり並んでいるパリでは困難」「交通計画もロンドン等をまねて都心まで勇敢に高速道路を開通させたが、先例のはずのロンドンはもっと慎重であった」「追い越してしまったのである」とされる。この点も、観光的には、あまりにも変化の激しい東京は、ロンドン、パリに比べて風格が劣るような感想が今日見られるところから、何とも評価がしにくい。私なら、京都よりもベニスに軍配を上げる。
「貨物輸送量が何故GDPほどには伸びなくなったのであろうか」と記述されるが、輸送量を重量と距離で考える先人の限界であろう。同書には、懐かしい言葉に「少量物品輸送」があらわれる。今では死語になってしまった。「やがて郵便局も国鉄駅もデパートの運送部門も労働不足でまいってしまうことは明らかである」と結論付けるが、小倉昌男さんがまだ宅急便を発足させていなかった時代でもある。ましてやAMAZONなど想像もできなかったのであろう。
それであっても、角本良平氏は尊敬できる先輩である。こよなく交通を愛し、多くの著作を世に出してきた。交通学者とよばれる研究者は大勢存在したが、多くは御用学者である。政府にいたことがないから、その分権威にあこがれる。従って国鉄改革時に日和見が多かったのである。その点では角本氏ははっきりしていた。その後、航空会社と運輸省が対立した時にも日和見の航空交通研究者がいた。三流学者しか交通には関心がないのであろうか、困ったものである。
関連記事
-

-
人流抑制に関する経済学者と感染症学者の意見の一致「新型コロナ対策への経済学の貢献」大竹文雄 公研2021年8月号No.696を読んで
公研2021年8月号No.696にコロナ関連の有識者委員等である、行動経済学者大竹文雄氏の「新型コ
-

-
脳科学と人工知能 シンポジウムと公研
本日2018年10月13日日本学術会議講堂で開催された標記シンポジウムを傍聴した。傍聴後帰宅したら
-

-
観光資源としての「隠れキリシタン」 五体投地、カーバ神殿、アーミッシュとの比較
「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」が世界遺産登録された。江戸時代の禁教期にひそかに信仰を続け
-

-
自動運転車とドローン
渋谷のスクランブル交差点を見ていると、信号が青の間の短い時間に、大勢の人が四方八方から道路を横断して
-

-
千相哲氏の「聞蔵Ⅱ」を活用した論文
「「観光」概念の変容と現代的解釈」という論文を偶然発見した。 http://repository.
-
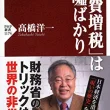
-
『戦後経済史は嘘ばかり』高橋洋一
城山三郎の著作「官僚たちの夏」に代表される高度経済成長期の通産省に代表される霞が関の役割の神
-

-
『仕事の中の曖昧な不安』玄田有史著 2001年発行
書評ではなく、経歴に関心がいってしまった。学習院大学教授から東京大学社研准教授に就任とあることに目
-

-
観光と人流ビッグデータとウェアラブルに関する意見交換会
2015年2月17日14時から一般社団法人日本情報経済社会推進協会/gコンテンツ流通推進協議会におい
-

-
観光行動学研究に必要なこと インタラクションの認識科学の理解
ミラーニューロンを考えると、進化の過程で人間が人間をみて心を想定するように進化したとおもっていたか
-

-
京都大学経営管理大学院講義録「芸術・観光」編を読んで
湯山重徳京大特任教授が編者の講義録、京都大学なので興味が引かれた。エンタテインメントビジネスマネジメ

