ジョン・アーリ『モビリィティーズ』吉原直樹・伊藤嘉高訳 作品社
コロナ禍で、自動車の負の側面をとらえ、会うことの重要性を唱えているが、いずれ改訂版を出さざるを得ないだろう。社会学の表面的な観察に基づいて記述するからである。負の側面でとらえられた自動車も、自動運転が標準装備されれば、改訂版が出されることであろう
「いわゆる運転の自由は、自動車という巨大かつ強力なものをコントロールする自由を伴う。つまり、1トンのものが高速で動き…自動車は、人を死に追いやる力を有しており、実際に予測不可能な規則性の下で人を死に追いやっている。」
「この運転する自由には驚くばかりの不平等が付きまとっている。毎日3000人が自動車事故で死んでおり、3万人が負傷している。衝突事故は2020年までに世界の疾病損傷ランキングの第3位になりその犠牲者のほとんどは実際には自動車を所有していない。ここで注目されるのは、衝突事故は偶然に起きているのではなく、自動車システムの特性であるという点である。」
そして、来るべきポスト自動車社会までも見通している。
それは
地球温暖化の進行、石油資源の枯渇、交通政策の変化、新たな燃料システム、カーシェアリングの普及、自動車の脱私物化、通信との融合などの動きから、おぼろげながらも、多元的で密度の濃い移動形態となるだろうとし、
「ちょうどインターネットと携帯電話が爆発的に普及したように、ポスト自動車への転換も予期せぬ形で現れるだろう」と予測している。
そしてまた、著者は「会うこと」の重要性を説いている。
「本章の議論に欠かせないのが、社会学における「会うこと」の地位を復権させることであり、とりわけ会うことで社会的ネットワークがどのように形成されるのかを見ることである。」
ここでは、対面で話すことの効果が説明され、現代の組織や集団の中では決定的に重要だと説く
関連記事
-

-
『物語 ナイジェリアの歴史』島田周平著 中公新書
アマゾン書評 歴史家トインビー曰く、アフリカはサハラ砂漠南縁を境に、北のアラブ主義
-

-
公研2019年2月号 記事二題 貧富の格差、言葉の発生
●「貧富の格差と世界の行方」津上俊哉 〇トーマスピケティ「21世紀の資本」
-

-
QUORA 李鴻章(リー・ホンチャン=President Lee)。
学校では教えてくれない大事なことや歴史的な事実は何ですか? 李鴻章(リー・ホンチャン=Pre
-

-
中国語の中の日本語(Chinese Borrowings from the Japanese Language) 陳 生保(Chen Sheng Bao) 上海外国語大学教授
中国語の中の日本語(Chinese Borrowings from the Japanese
-

-
ゲルニカ爆撃事件の評価(死者数の大幅減少)
歴史には真実がある。ただし人間にできることは、知りえた事実関係の解釈に過ぎない。もっともこれも人間
-

-
『旅行契約の実務』 鈴木尉久著2021年 民事法研究会発行
旅行業法の解釈について、弁護士でもある鈴木教授がどのような見解を持っておられるかと本書を図書館で
-

-
フェリックス・マーティン著「21世紀の貨幣論」をよんで
観光を理解する上では「脳」「満足」「価値」「マネー」が不可欠であるが、なかなか理解するには骨が折れる
-
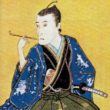
-
『眼の神殿 「美術」受容史ノート』北澤憲昭著 ブリュッケ2010年 読書メモ
標記図書の存在を知りさっそく図書館から借りてきて拾い読みした。 観光資源の文化資源、自然資源という
-

-
『ダークツーリズム拡張』井出明著 備忘録
p.52 70年前の戦争を日本側に立って解釈してくれる存在は国際社会では驚くほど少ない・・・日本に
- PREV
- コロナとハワイ
- NEXT
- 東日本震災時に問題視された略奪の限りを尽くしていた火事場泥棒
