Quoraなぜ、当時の大日本帝国は国際連盟を脱退してしまったのですか?なぜ、満州国について話し合ってる中で軍事演習をしてしまったのか、なぜ、当初の目的である権益のほとんどを認められているのに堂々退場したのか。
日本の国際連盟脱退は、満州事変に対するリットン調査団の報告書を受け入れられないと判断して席を蹴ったものです。
客観的に見てリットン調査団の報告書はよく出来た公正な物です。清朝末期の動乱から満州事変に至るまでの日本と中国と当該地域の歴史的な経緯をよく把握しており、事変自体に関してもよく調べており、流石だなと言う印象です。
満州事変に対する欧米列強の最大の関心事は、満州における権益云々ではなくて、第一次世界大戦の反省からケロッグ=ブリアン条約(パリ不戦条約)において戦争を違法化、先制攻撃による侵略はこれを許さないと決めたのに、堂々と侵略をキメてくれちゃった日本にどう対処しようかと言う点にありました。
満州事変は関東軍の暴走による侵略行為であり、柳条湖事件に対する反撃と言うのは大嘘であると判明した以上、日本の軍事力による満州制圧からの傀儡国家の樹立という流れをそのまま追認することは不戦条約の精神をぶち壊しにすることになり、欧州と世界の平和に大きなヒビを入れることになりますから到底受け入れられません。
そこで、侵略行為に関しては手厳しく批判、軍の撤収を求めつつ、満州進出は軍事じゃない別のアプローチでやってくれよな、権益は大体において認めるからさぁ、と言う現実的な提案をしてきました。
しかし、満州事変以前の幣原外交による中国への過度の融和姿勢による舐められと、中国における現地日本人居留民へのテロ行為の頻発などに対してキレ気味であった日本国民は、満州事変を見て「いいぞ!もっとやれ!」と超盛り上がっていました。
最初は天皇陛下の意向に従い関東軍の責任者の処罰を行おうとしていた政府も、あまりの盛り上がりに尻込みして黙認する流れになってしまっていました。この状況では、日本の侵略行為を指摘して軍事的に一旦撤収することを求める勧告は、国内の政治情勢的にもはや受け入れることが出来なかったのです。
また、事変を首謀した関東軍の幹部連中は、いずれ中国と組んで欧米に対抗すべきと言う思想を持ち、欧米が作り上げたルールをぶち壊しにすることは善であると考えていましたから、政府が必死で事態を収拾しようとするのをあざ笑うかのように、欧米の態度が硬化するような行動を繰り返していました。
以下太字の部分は認識不足
ちなみに、あそこまで拙速な脱退決断は、松岡洋右の性格も影響しているような気はしますね。英語力と押しの強さだけが取り柄で堪え性がなく、外交に関するまともな見識を持ち合わせない松岡を代表として送り込んでいたのは、今から見ればなにやら悪夢のように思えます。
内田外務大臣の訓令が間違い。松岡は脱退する意図はなかった。しかし、帰国して国民が圧倒的に指示していたので驚いている。
関連記事
-

-
『デモクラシーの帝国』 藤原帰一2002岩波新書 国際刑事裁判所 米国の不参加
国際刑事裁判所の設立を定めたローマ規程は、設立条約に合意していない諸国にも適用されるところから、アメ
-

-
電力、情報、金融の融合
「ブロックチェーンとエネルギーの将来」阿部力也 公研2019No673 電気の値段は下がって
-

-
塩野七生著『ルネサンスとは何であったのか』
後にキリスト教が一神教であることを明確にした段階で、他は邪教 犯した罪ごとに罰則を定める 一
-
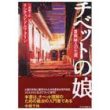
-
『チベットの娘』リンチェン・ドルマ・タリン著三浦順子訳
河口慧海のチベット旅行記だけではなく、やはりチベット人の書物も読まないとバランスが取れないと思い、標
-

-
『起業の天才 江副浩正 8兆円企業を作った男』大西康之
父親の縁で小運送協会が運営していた学生寮に大学1,2年と在籍していた。その時の一年先輩に理科二類
-

-
QUORA 李鴻章(リー・ホンチャン=President Lee)。
学校では教えてくれない大事なことや歴史的な事実は何ですか? 李鴻章(リー・ホンチャン=Pre
-

-
『動物の解放』ピーターシンガー著、戸田清訳
工場式畜産 と殺工場 https://www.nicovideo.jp/watch
-
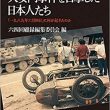
-
『天安門事件を目撃した日本人たち』
天安門事件に関する「藪の中」の一部。日本人だけの見方。中国人や米国人等が作成した同じような書籍があ
-

-
日本人が海外旅行ができず、韓国人が海外旅行ができる理由 『from 911/USAレポート』第747回 「働き方改革を考える」冷泉彰彦 を読んで、
勤労者一人当たり所得では、日本も韓国も同じレベル 時間当たりの所得では、日本は途上国並み これで

