書評『日本人になった祖先たち』篠田謙一 NHK出版 公研2020.1「人類学が迫る日本人の起源」
公開日:
:
最終更新日:2023/05/29
出版・講義資料
分子人類学的アプローチ
SPN(一塩基多型)というDNAの変異を検出する技術が21世紀当初に開発
SPNの違いの大部分は意味がないと考えられている。しかし、やがてSPNの違いが能力と結びつけて語られるようになることは避けられない。集団間に生物学的な違いがあるという根拠として用いられるようになると、何が起きるか
「個人」を自らがもつ遺伝子の組み合わせと考えると、一つ一つの遺伝子が数十万年の歴史をもっているにせよ、前後20世代としても1000年ほどの歴史しかない。そのくらいの年月で特定の遺伝子どおしの組み合わせは雲散霧消してしまう。つまり自らの持つ遺伝子の組み合わせを過去にさかのぼって追求できるのはせいぜい500年程度。個人という観点から由来をさかのぼることはそれほど意味のあることではない
アフリカ人以外の人々は皆、ネアンデルタール人の遺伝子を持っている。
私たちホモサピエンスがデニソワ人やネアンデルタール人の共通祖先から分岐したのがだいたい55万ー77万年ぐらい、その後ネアンデルタール人とデニソワ人が47万ー38万年ぐらい前に分岐している
現在では、形態としてのホモサピエンスの完成は概ね20万ー30万年前 一直線ではなく、我々以外の人類と交雑した
民族には数千年ぐらいの時間幅しかない
DNA分析により、集団の移動と文化的拡がりにズレが生じていることが分かった
文化的に共通性があると思い込んでいた民族や地域集団が。実は遺伝子で見ると複数の地域集団に分かれていたり、またその逆であったりということがかなりはっきりわかってきた。
この10年間で欧州人の成り立ちがわかってきた
これまでは、狩猟民族がすんでいたところにアナトリア(アジア大陸最西部の半島)から農耕民がやってきて、1万年前より新しい時代にその二つが混血するなり置換するなりして欧州人になったといわれてきた
今は、アナトリアから農耕をもって拡がった人たちが狩猟採集民族を飲み込んでいってプロト・ヨーロッパ人が出来上がったあと、4千ー5千年前に現在のウクライナあたりにいたヤムナヤという遊牧民族西ヨーロッパに一挙に入ってきて、以前からいたプロトヨーロッパ人を置換する形でできたのが、現代の欧州人だといわれている
ヤムナヤの遊牧民が使っていた言葉がまさに今のインド・ヨーロッパ語族の一番のベースになったといわれている。あれはアナトリアの農耕民族の言葉ではなかった
ヨーロッパを見ると、文化的な連続性と、集団の遺伝的な連続性がきちんと対応したものでなないということが分かってきた
日本列島に南から入ってきた人たちはほとんど子孫を残さなくてそこで終わり、今の沖縄の人たちは本州や九州流入した縄文人
縄文人と同じ遺伝子を持った人は現代にいない。世界中にいなく消えてしまった。
「和食」という言葉ができたのは明治30年代。それまでは京料理、江戸料理と呼ばれていた。それを考えると日本人という概念も明治以降に産まれ、それまでは薩摩人、長州人
入ってきた人がどれだけ子孫を残すかが大きな影響を残す
南米大陸に入ったのは主にスペイン人。500年経った今、南米の先住民のY染色体は8割くらいはヨーロッパ系、ミトコンドリアDNAは8,9割が先住民系という状況になっている。
現在2%超で入ってきた人たちが、今後、日本列島で沢山子供を残し、いわゆる在来の日本の人たちが子孫を残さなかった場合は、数百年で遺伝的に大きく変わる
実は1万年前、欧州人の肌はまだ褐色で、白くなるのは8千年より新しい時代であるということがDNA分析で分かっている
関連記事
-
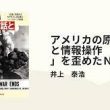
-
アメリカの原爆神話と情報操作 「広島」を歪めたNYタイムズ記者とハーヴァード学長 (朝日選書) とその書評
広島・長崎に投下された原爆について、いまなお多数のアメリカ国民が5つの神話・・・========
-

-
『一人暮らしの戦後史』 岩波新書 を読んで
港図書館で『一人暮らしの戦後史』を借りて読んでみた。最近の本かと思いきや1975年発行であった。
-

-
中国の観光アウトバウンド政策 公研No.675 pp45-46
倉田徹立教大学法学部教授 1997年にアジア通貨危機、2003年にSARS流行発生時、香港経
-

-
ジャパンナウ観光情報協会機関紙138号原稿『コロナ禍に一人負けの人流観光ビジネス』
コロナ禍でも、世界経済はそれほど落ち込んでいないようだ。PAYPALによると、世界のオンライン
-

-
鬼畜米英が始まったのは、1944年からの現象 岩波ブックレット「日本人の歴史認識と東京裁判」吉田裕著
靖国神社情報交換会に参加した。歴史認識は重要な観光資源であるとする私の考えに共鳴されたメンバーの
-

-
『平成経済衰退の本質』金子勝 情報、金、モノ、ヒト、自然 について、グローバリゼーションのスピードが違うことを指摘 情報と人流のずれが、過剰観光
いつも感じることであるが、自分も含め観光学研究の同業者は、研究原理を持ち合わせていないということ
-

-
ここまで進化したのか 『ロボットの動き』動画
https://youtu.be/fn3KWM1kuAw
-
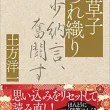
-
『枕草子つづれ織り 清少納言奮闘す』土方洋一 紙が貴重な時代は、日記ではなく公文書
団塊の世代が義務教育時代に学修したことの一部が、その後の研究により覆されている。シジュウカラが言
-
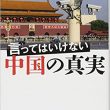
-
『言ってはいけない中国の真実』橘玲2018年 新潮文庫
コロナ禍で海外旅行に行けないので、ブログにヴァーチャルを書いている。その一つである中国旅行記を
-

-
『永続敗戦論 戦後日本の核心』、『日米戦争を起こしたのは誰か ルーズベルトの罪状・フーバー大統領回顧録を論ず』『英国が火をつけた「欧米の春」』の三題を読んで
「歴史認識」は観光案内をするガイドブックの役割を持つところから、最近研究を始めている。横浜市立大学論

