歴史認識と書評『暗闘 スターリン、トルーマンと日本降伏 』長谷川毅
日本降服までの3ヶ月間を焦点に、米ソ間の日本及び極東地域での主導権争いを克明に検証した本。
この本を読んで知見を得たこと、印象的だった箇所は次の4点。
1.米国首脳部では、ポツダム宣言の対日通告の前日に、広島と九州北部(結果的には長崎)への核爆弾投下が決定されていたこと。米国の核兵器行使は、日本のポツダム宣言「黙殺」に対する報復ではなく、ソ聯参戦前に日本を降服へ追い込む目的があったこと。
2.8月初旬当時の日本の最高指導者は、戦争を継続した場合、本土に核爆弾が投下され、今後も引き続き投下される可能性を認識していたが、そのことよりもソ聯が参戦し、日本本土への侵攻することへの懸念のほうが降服の意思決定の根拠となっていたとうかがわれること。
3.日本が降服の意思決定を行なう過程で、「国体の護持」を降服条件とすべきであるとの主張が継戦派から提起されたが、これに対し停戦・降服派は、「国体護持」=天皇の生命・身体の安全と自由を確保し立憲君主制を維持すること、と敢えて狭く定義することで、昭和天皇と皇族の同意を得、軍部の諒解を得た経緯があったこと。
4.ロバート・JC・ビュートー著、大井篤訳「終戦外史」(時事通信社、1958年刊)の存在を知ったこと(その後すぐに古書店で買いました)。
書評11945年は敗戦の年である。それは日本人にとって忘れることのできない年であるが降伏にいたる経緯をめぐってはいまだに幾多の大きな疑問が残されている。誰が、あるいは何が、戦争を終結に導いたのか。原爆か、ソ連の参戦か。その渦中にあって日本の指導者たちはどのように振舞ったのか。天皇の果たした役割はどのようなものであったか。世上には多くの著作があふれているが日、米、ソ三国にまたがる広大な舞台で時々刻々に変転しつつ展開するドラマを過不足なく捉えるのは至難である。ましてや政治的な、さらには人道上の責任に直面した個々人の利害得失をめぐって展開される弁護、弁解、虚偽、欺瞞の数々は今日に至るまで真相の究明を妨げている。
本書は敗戦後60年の間に刊行された日記、回想録、研究書、さらには日本、米国、ソ連で入手可能な公文書を広く渉猟した上に成ったもので類書の群を抜く水準に到達している。冒頭において、太平洋戦争は日本がポツダム宣言を受託した8月15日に終ったのではなくソ連の千島占領が終結する9月5日まで続いたと指摘する。このように、本書はこれまで無視されがちであった、ポツダム宣言以後に顕在化するソ連の領土的野心を見失っていない。
ヤルタ会談でソ連の参戦を求めたアメリカは原爆を手中にすることによってその誤りに気づくが時すでに遅かった。ポツダム宣言は「実際には、原爆を使用することを正当化するために発せられたものであった」。アメリカでは、原爆は本土上陸作戦を敢行すれば失われたであろう100万のアメリカ兵の生命を救ったと広く信じられているがそれが神話に過ぎないことも明らかにされる。
ポツダム宣言の受諾は原爆よりはむしろソ連の参戦によって頼みの綱を奪われた日本政府の決断であった。ソ連は和平派にとっては講和の仲介者であり、継戦派にとっては「決号」作戦の鍵を握るものであった。この窮地にあって日本の指導者は日々どのような奔走に明け暮れたのだろうか。本書を読んで、これまで立役者とされてきた政治家たちが思いのほかに優柔不断であったことを意外に感じる人は少なくないだろう。真の和平派は彼らを縁の下で支え続けた人々の中にいた。
書評2原爆投下、ソ連参戦と日本の降伏をめぐる、トルーマン、スターリンと日本の指導者の熾烈な駆け引きを克明に描いた本である。
日本では、終戦の経緯に触れた本は非常に多い。しかし本書を読むと、従来の多くの文献が、国内中心の天動説的な視点から書かれており、降伏をめぐる国際政治上の駆け引きに目を向けていなかったことに気づく。原爆投下とソ連の参戦はあたかも天から降ってきた災難であるかのように扱われ、なぜアメリカは原爆を投下したのか、ソ連の参戦と原爆投下にはどういう関係があるのか、といった疑問は、提起されないことも多かったのである。
アメリカでは、原爆投下の経緯や正当性について長い論争があるが、ベトナム戦争や冷戦をめぐる論争と同様、争点は「アメリカは正義の国か否か」というアメリカの自画像をめぐるものになっており、日本の降伏におけるソ連の役割には目が向いていなかった。
本書はソ連の極東政策の変遷に着目することで、原爆の投下、日本の降伏、そしてソ連の参戦を密接に結びついた過程として描き出すことに成功している。ワシントン・東京・モスクワの3箇所を結び、分刻みで展開されるドラマには、息のつまるような迫力がある。スターリンの動きが補助線となって、いままで見えなかった複雑な駆け引きやロジックが見えてくるのである。
優れた歴史書を読むと、大いに啓発されると同時に、なぜ今までこういう本がなかったのか、と不満に思うのが常である。どこの国でも、歴史叙述は国内的関心を反映しがちであり、本当の意味で国際的な立場から書くのは難しい。アメリカに帰化したロシア研究者、長谷川氏にしてはじめて書けた本ということなのだろうか。本書は吉野作造賞、司馬遼太郎賞のほか、アメリカでも2つの賞をさらっている。おそらくアメリカでも本書を読んで、自国の歴史叙述に不満をもった人が多かったのだろう。名著だと思う。
1945年2月、駐スウェーデン陸軍武官父・小野寺信が日本に送信した「ヤルタ密約電報」の行方に関係し、終戦後70年を迎えようという今、
その真相が、岡部 伸著の「消えたヤルタ密約緊急電」で解き明かされつつある。
最近ウクライナ問題が頭をもたげ、「北方領土問題」、「平和条約」も未締結のまま、ロシアと日本の関係はまた難しい局面を迎えようとしている。歴史は所詮、繰り返されるのだろうか。
関連記事
-

-
QUORAに見る歴史認識 世界で日本人だけできていないと思われることは何ですか?
世界で日本人だけできていないと思われることは何ですか? そもそも、日本が世界的に優れているも
-
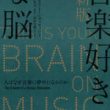
-
『音楽好きな脳』レヴィティン 『変化の旋律』エリザベス・タターン
キューバをはじめ駆け足でカリブ海の一部を回ってきて、音楽と観光について改めて認識を深めることができた
-

-
世界遺産を巡る日韓問題(軍艦島)
観光資源評価は頭の中の出来事である。ネルソン・マンデラが政治犯として収容されていたロベン島はその物語
-

-
QUORAにみる歴史認識 伊藤博文公は、当初朝鮮併合に関しては反対だったって話ですが、実際は如何でしょうか?
伊藤博文公は、当初朝鮮併合に関しては反対だったって話ですが、実際は如何でしょうか?
-

-
筒井清忠『戦前のポピュリズム』中公新書
p.108 田中内閣の倒壊とは、天皇・宮中・貴族院と新聞世論が合体した力が政党内閣を倒した。しかし、
-

-
QUORA 第二次世界大戦 · フォロー中の関連トピック 米国は、日本の真珠湾攻撃の計画を実際には知っていて、戦争参入の口実を作るために敢えて日本の攻撃を防がなかった、というのは真実ですか?
回答 · 第二次世界大戦 · フォロー中の関連トピック米国は、日本の
-
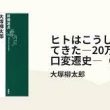
-
『ヒトはこうして増えてきた』大塚龍太郎 新潮社
p.85 定住と農耕 1万2千年前 500万人 祭祀に農耕が始まった西アジアの発掘調査で明らかにさ
-

-
Quora Ryotaro Kaga·2019年8月1日Sunway University在学中 (卒業予定年: 2024年)なぜこんなに沢山の日本人女性が未婚なのですか?
Ryotaro Kaga·2019年8月1日Sunway University在学中 (
-

-
動画で考える人流観光学 西洋人慰安婦に関する映画
She Ends Up In A Japanese Concentration Camp For
-

-
『コンゴ共和国 マルミミゾウとホタルの行き交う森から 』西原智昭 現代書館
西原智昭氏の著書を読んだ。氏の経歴のHP http://www.arsvi.com/w/nt10.h


