2019年11月9日日本学術会議シンポジウム「スポーツと脳科学」聴講
2019年11月9日日本学術会議シンポジウム「スポーツと脳科学」を聴講してきた。観光学も脳科学のシンポジウムを考える必要がある時代になっている。
AIは運動学習が苦手である。意識があったほうが役立つのではないか
潜在脳機能 イップス、マルアドプテーション
精神的な原因などによりスポーツの動作に支障をきたし、突然自分の思い通りのプレー(動き)や意識が出来なくなる症状のことである。本来はゴルフの分野で用いられ始めた言葉だが、現在ではスポーツ全般で使われるようになっている。
伊佐正 日本学術会議神経科学分科会委員長 京都大学教授
平成30年度創設の京都大学の新規WPI研究拠点・ヒト生物学高等研究拠点(ASHBi)の進化神経科学研究グループを兼ねている。特に霊長類で高度に進化した巧緻な運動、すなわち手指や眼球運動に関わる神経回路とその回路の部分損傷後の機能代償機構、さらには意思決定やモチベーション・注意・連合学習・意識などの認知機能のメカニズムについて多様な研究手法を融合して研究を進めている。特に、従来霊長類において困難だった光遺伝学や化学遺伝学などの先端的回路操作技術を霊長類において使用可能にする技術開発に注力している。
内藤栄一
国立研究開発法人情報通信研究機構
一流サッカー選手と「10:13 ブラインドサッカー選手の脳から考える 「神経系の適応と超適応
我々の研究室では、主にMRIなどのニューロイメージング手法や行動学的アプローチを用いて、人間の感覚・運動機能を理解して、これを改善・向上する研究を行っています。
我々の興味は、人間の身体認知から運動制御や運動学習に至るまでの幅広いトピックスを包括しています。例えば、身体像、身体意識や自己意識の脳内表現、他者理解、運動意図、運動イメージ、運動適応、運動技能、感覚運動連関などが主な研究テーマです。我々は、主にMRI、EEG、TMS、tDCSなどの装置を用いた研究を行っています。脳機能マッピングや脳情報復号化技術などを用いて、人間の感覚情報処理や運動制御・運動学習の脳内メカニズムを脳の機能と構造の両側面から理解し、行動計測による計算論モデルの構築を通して、脳のシステム的理解を図っています。これらの深い理解に基づき、適切な行動介入、神経修飾やニューロフィードバックなどの手法を用いて、人間の感覚・運動機能を効果的に改善・向上させる手法を開発しています。
子供から高齢者、感覚(視覚)障害者からトップアスリートに至るまでを広く研究の対象とし、発達に伴う機能分化、加齢に伴う機能劣化、障害者やスポーツの達人に見られる脳の特殊化や超適応機能などを可視化して、人間の一生を通じて起こる脳のネットワークレベルでの可塑性ルールの解明に挑んでいます。このような研究は、自己の脳の可塑的な適応力を最大限に活かして、子供から高齢者、身体障害者までが広く活躍できる社会を実現するための学術的基盤となります。
我々は、これらの基礎研究の知見がスポーツやリハビリテーショントレーニングなどの実生活現場に、継ぎ目なく移行できるような研究の枠組みを確立することを目指しています。これを実現するため、大阪大学をはじめとする様々な大学や企業との共同研究も積極的に行っています。
日本電信電話株式会社 コミュニケーション科学基礎研究所 柏野牧夫
http://sports-brain.ilab.ntt.co.jp/
桑田選手が自己認識していたカーブの投げ方と、実際にカーブを投げている投げ方は、正確な観察によれば違った。
パラリンピックブレイン -パラアスリートの脳にみる人間の脳の再編可能性
東京大学大学院総合文化研究科 中澤公孝
https://www.ueharazaidan.or.jp/houkokushu/Vol.32/pdf/report/012_report.pdf
関連記事
-

-
Quora ヨーロッパ人による境界がなかった場合には、今日のアフリカには幾つくらいの国があったと思いますか? 欧州にはバスク語しか残らなかった
https://youtu.be/i28l-t4H1GM ヨーロッパ人による境界がなかっ
-

-
ジョン・アーリ『モビリィティーズ』吉原直樹・伊藤嘉高訳 作品社
コロナ禍で、自動車の負の側面をとらえ、会うことの重要性を唱えているが、いずれ改訂版を出さざるを得な
-

-
Quora 微分方程式とはなんですか?への回答 素人の私にもわかりやすかった
微分方程式とは、未来を予言するという人類の夢である占い術の一つであり、その中でも最も信頼のおける占
-

-
『財務省の近現代史』倉山満著 馬場鍈一が作成した恒久的増税案は、所得税の大衆課税化を軸とする昭和15年の税制改正で正式に恒久化されます・・・・・通行税、遊興飲食税、入場税等が制定されたのもこの時であり、戦費調達が理由となっていた 「日本人が汗水流して生み出した富は、中国大陸に消えてゆきました」と表現
p.98 「中国大陸での戦争に最も強く反対したのは、陸軍参謀本部 p.104 馬場
-

-
書評『情動はこうしてつくられる』リサ・フェルドマン・バレット 紀伊国屋書店
参考になるアマゾンの書評の紹介 ➀ 本書のサブタイトルにある「構成主義(const
-

-
ハーディ・ラマヌジャンのタクシー数
特殊な数学的能力を保有する者が存在する。サヴァンと呼ばれる人たちだが、どうしてそのような能力が備わ
-

-
動画で考える人流観光学 観光情報論 錯覚
https://youtu.be/WnsXhHJ_HJE
-

-
言語とは音や文字ではなく観念であるという説明
観光資源を考えると、言語とは何かに行き着くこととなる。 愛聴視して「ゆる言語学ラジオ」で例のエ
-
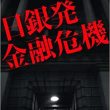
-
英国通貨がユーロでない理由 志賀櫻著「日銀発金融危機」
ポンド危機と英国通貨がユーロでない理由 サッチャー政権
-

-
『物語 ナイジェリアの歴史』島田周平著 中公新書
アマゾン書評 歴史家トインビー曰く、アフリカはサハラ砂漠南縁を境に、北のアラブ主義

