戦陣訓 世間が曲解して使用し、それが覆せないほど行き渡ってしまった例
公開日:
:
伝統・伝承(嘘も含めて), 出版・講義資料, 観光資源
世間が曲解して使用し、それが覆せないほど行き渡ってしまった例である。「もはや戦後ではない」は私のHPにも、教材として載せてあるが、新たに、下記サイトで発見した例が、戦陣訓の文章である。
東条英機で有名な『戦陣訓』は、「生きて虜囚の辱を受けず」は、戦後にマスコミが強調したもので、実際の兵士には、我々が意識するほど重要なものでは無かったのです。
『戦陣訓』は、長期にわたる支那事変での軍紀紊乱への対策として、陸軍教育総監部が軍人勅諭を補足するものとして作成をはじめたもので、陸軍大臣畑俊六が発案し、当時の教育総監部の教育総監:山田乙三、本部長:今村均、教育総監部第1課長鵜沢尚信、教育総監部第1課で道徳教育を担当していた浦辺彰、陸軍中尉白根孝之らを中心として作成され、作家の島崎藤村が昭和15年に「戦陣訓」を校閲しました。この起草作業が長引き、東条が陸軍大臣の時に完成し、大臣の訓示として発表されました。
陸軍で発表されたものですから、海軍は当然に無視されました。
陸軍でも、東条英機のシンパの部隊(野砲兵第22連隊)では、起床後の奉読が習慣になっていたようですが、それ以外の部隊では冷淡で、学徒出陣で出征し戦車隊の小隊長だった作家の司馬遼太郎の発言では「関東軍で教育を受け、現役兵のみの連隊(久留米の戦車第1連隊)に属してほんの一時期初年兵教育もさせられたが、戦陣訓が教材に使われている現場を見たことがない、幹部候補生試験などでも軍人勅諭の暗記はテストの対象になるが、戦陣訓はそういう材料になっていなかったように思える。」と書いている。
また、中国戦線において戦陣訓を受け取った伊藤桂一陸軍上等兵(のち戦記作家)によれば、一読したあと「腹が立ったので、これをこなごなに破り、足で踏みつけた。いうも愚かな督戦文書としか受けとれなかったからである。戦陣訓は、きわめて内容空疎、概念的で、しかも悪文である。自分は高みの見物をしていて、戦っている者をより以上戦わせてやろうとする意識だけが根幹にあり、それまで十年、あるいはそれ以上、辛酸と出血を重ねてきた兵隊への正しい評価も同情も片末もない。同情までは不要として、理解がない。それに同項目における大袈裟をきわめた表現は、少し心ある者だったら汗顔するほどである。筆者が戦場で「戦陣訓」を抛(ほお)つたのは、実に激しい羞恥に堪えなかったからである。このようなバカげた小冊子を、得々と兵員に配布する、そうした指導者の命令で戦っているのか、という救いのない暗澹たる心情を覚えたからである。」と述べています。
そもそもに、「生きて虜囚の辱を受けず」の意味は、日清戦争中に第一軍司令官であった山縣有朋が清国軍の捕虜の扱いの残虐さを問題にし、「捕虜となるくらいなら死ぬべきだ」という趣旨の訓令が発端であって、陸軍ではそういう風潮が自然にあったそうです。
関連記事
-

-
ニクァラグア手話 聴覚障害の子どもたちが手話を作り出すまで
https://youtu.be/qG2HjmG0JGk https://www.bbc
-

-
ピアーズ・ブレンドン『トマス・クック物語』石井昭夫訳
p.117 観光tourismとは、よく知っているものの発見 旅行travelとはよく知られていな
-
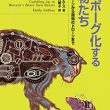
-
『サイボーグ化する動物たち 生命の操作は人類に何をもたらすか』作者:エミリー・アンテス 翻訳:西田美緒子 白揚社
DNAの塩基配列が読破されても、その配列の持つ意味が分からなければ解読したことにはならない。本書の冒
-

-
『ミルクと日本人』武田尚子著
「こんな強烈な匂いと味なのに、お茶に入れて飲むなんて!」牛乳を飲む英国人を見た日本人の言葉である。
-

-
動画で考える人流観光学 観光資源 歴史は後から作られる 伝統は新しい
山田五郎のオトナの教養講座 https://www.youtube.com/watch?v=T
-
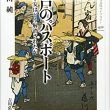
-
『江戸のパスポート』柴田純著 吉川弘文館
コロナで、宿泊業者が宿泊引き受け義務の緩和に関する政治的要望を行い、与党も法改正を行うことを検討
-
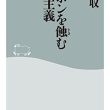
-
『ニッポンを蝕む全体主義』適菜収
本書は、安倍元総理殺害の前に出版されているから、その分、財界の下請け、属国化をおねだりした日本、
-

-
『銀座と資生堂』戸矢理衣奈
戸谷という珍しい苗字にひかれて本書を港図書館で借りた。現役時代、役所の先輩の息子さんが亡くなら
-

-
MaaSに欠けている発想「災害時のロジステックスを考える」対談 西成活裕・有馬朱美 公研2019.6
公研で珍しく物流を取り上げている。p.42では「自動車メーカーは自社の車がどこを走っているかという

