quora 中世、近世のヨーロッパで、10代の女性がどのような生活を送っていたのか教えてくれませんか?貴族階級/庶民とそれぞれ、何をしていたのでしょうか?
何で10代の女性限定なのかよくわかりませんが、知っている範囲で。
中世の庶民は、ほぼ農奴です。生まれた村を出ることができず、村の中の狭い人間関係の中で結婚し子供をつくり、労働の半分は領主の畑仕事、残りの半分で自分の畑を耕すもののそこから領主への税と教会への「10分の一税」を払うと、結局労働量の3~4割程度しか自分のものにならなかったはずです。移動の自由がなく情報がない中、また科学もマスコミもない中、どの村にもあった教会が唯一の情報機関であり、影響力がありました。日曜日にみんなで村の教会に集まって神父の説教を聞いたり、罪の許しを得るために教会を訪れて告白したりすることは、人々にとって大変重要なことだったでしょう。死後天国に行けるかどうかは、人々にとって大きな関心事でした。結果的に、神の意思に適った生活をしなければならないという圧は、現在と比べ物にならないほど大きかったことでしょう。
外的な条件として、12世紀以前のヨーロッパは外敵の侵入が相次いだり、封建諸侯同士の戦乱があったりと、大変困難な時代です。ヴァイキングが略奪のついでに娘をさらっていくのはよくあることであり、単純にレイプされるなどのケースも多々存在したことでしょう。イスラム地域では奴隷売買の習慣がありますが、奴隷の供給元にもなっていたようです。
ただ、中世温暖期と同じころに農法の進歩があり、生産力が増して人口が増え、経済的にも発展します。北欧へのキリスト教浸透とともにヴァイキングの侵入もおさまり、ヨーロッパは逆に十字軍やレコンキスタで広がる様相を見せ始めます。おそらく並行現象でしょうが、ジョングルール(大道芸人)が都市や村の広場で歌舞音曲や手品やジャグリングを披露した記録だの、宗教劇(村全体が参加して場所を移動しながら聖書の内容を劇で演じるもの、規模がだんだん盛大になって当の教会から禁止されるほどになったが、お祭りの機能を兼ねていたので中世を通じて行われ続けた)だの、「楽しそうな中世」のイメージのものが登場を始めます。13世紀にはモンゴル侵攻、14世紀にはペスト流行と人口減、数々の農民反乱など、なかなか困難な状況は続きますが、全体としてやや豊かになり、たまには楽しいことがあったのは想像可能です。人口減や農民反乱は領主からの税負担を緩める方向に作用し、そうした意味でも多少良かったことでしょう。
女性特有の労働として、糸紡ぎが行われていたはずです。繊維から糸を紡ぎ、紡いだ糸を織って布にし、それを縫い合わせて服や農作業用の袋をつくるなどというのは、時間がいくらでもかかる作業です。男性は農作業・力仕事を担当し、女性はこうした軽作業と食事で分担していただろうということと、10代の女性はすでに貴重な戦力でこうした労働の場面で大活躍だっただろうという事は、容易に想像できます。
中世ヨーロッパの習俗として、初夜権があります。王や領主や僧侶が花嫁の初夜の権利を持つというものですが、これは破瓜の出血への迷信的な恐れから、経験豊かな男性による「治療」「お祓い」のような目的で行われたものであるようで、そもそもは下劣な関心ではなかったようです。当時の結婚は早いでしょうから、そうした「治療」を受ける10代女性も数多くいたことも容易に想像できます。
中世の貴族階級と言っても、それほどはっきりとまだ我々のイメージする「貴族」になっていたわけでもないでしょう。強いて言えば騎士(領主を勤めている場合が多い)や諸侯・国王(中世の身分では騎士階級の一種)が貴族でしょうが、彼らは基本的に軍司令官であり、中世のお城は武骨な軍事拠点であり、居住性はないに等しく、我々が想像するような貴族文化は少なくとも前半にはありません。宮廷文化の繁栄には、国王が力をつけ、城が軍事拠点から諸侯の集合場所と機能を変える中世後半~近世を待たなければなりません。江戸時代の日本は、支配階級である武士と被支配階級である農民・職人・商人が質的にそれほど違わない生活をしていたと言われますが、恐らく同様です。生活は庶民よりだいぶマシだったでしょうし、お城に大道芸人や楽師が呼ばれて退屈を紛らしてくれることもあったでしょうが、現代的に見て贅沢と言える水準では絶対になかったことでしょう。国王や諸侯の娘は基本機能が政略結婚の道具であり、早くに嫁ぐケースも多かったはずです。全てを召使いに任せたわがまま生活…などと言う余地は、ほとんどなかったのではと思われます。むしろ、中世後半の豪商の娘(特にイタリア北部やフランドルの豊かな諸都市)なんかの方が、身分的には庶民ですがお姫様に近い生活をしていたのではと思います。
近世はルネサンスの頃からになるでしょうが、農村部の暮らしは基本的に中世と変わりません。ただ、いわゆる魔女狩りが盛んなのは、中世ではなく近世です。魔女狩りについての一番著名な著作は「魔女に与える鉄槌」で1486/87年、魔女狩り自体の最盛期は16~17世紀とされており、明らかに近世、それもカトリックの権威が揺らぎ、宗教改革から陰惨な宗教戦争に至る時期です。Wikipediaの「魔女狩り」の項によれば、「近世の魔女迫害の主たる原動力は教会や世俗権力ではなく民衆の側にあり、15世紀から18世紀までに全ヨーロッパで推定4万人から6万人が処刑されたと考えられている」そうです。昔おおげさに言われた数よりもはるかに少ないものの、魔女の嫌疑を受けた者はもっと多く、中には拷問を受けた者もいたでしょうし、処刑は焚刑が多く、残酷なものでした。魔女狩りの対象は実は男性も含まれており、国によっては裁判を受けた80%が男性だったりして、何だかよくわかりませんが、10代の女性が裁判にかけられ、焚刑になるケースもあったことでしょう。単純に30年戦争やユグノー戦争などの残虐な戦争も多く、大変だったろうと思います。
近世の貴族階級に関しては、ブルゴーニュ公国の宮廷やイタリア北部の都市の文化などが国際的に伝わり、華やかな宮廷文化が見られ始める頃です。カトリーヌ・ド・メディシスがフランスに嫁ぐのが16世紀の初めで、カトリーヌはイタリアの先進文化をフランスにもたらす役割を果たしたとも言われ、フィレンツェ料理を宮廷に持ち込み、中世ヨーロッパ共通の食文化からフランスの料理を離脱させ、フランス独特の料理を始めたと考える歴史家もいます。フォークやその他の食器類そして食事作法、ソースや地中海産の野菜、アイスクリーム、フロランタン、マカロン、シューといった菓子類、礼儀作法としての清潔、香水も、カトリーヌがフランスに伝えたとも言われています。
カトリーヌは学識のあるルネッサンス諸侯の権威は武力と同じぐらいに文字に依拠するものであるという人文主義者の思想を信じており、メディチ家の先祖たちやヨーロッパの主導的な芸術家たちを招聘した義父フランソワ1世の影響を受けていました。内乱と王権衰退の時代に、彼女は豪華な文化的装飾によって王室の威信を高めようとし、王室財政を支配できるようになると、彼女は芸術のパトロン活動を開始し、それは30年間続きました。この時代、彼女は芸術全分野にわたる独特の後期フランス・ルネッサンスを主宰したとされています。
こうした中にあって、当時の王族や貴族の10代の女性たちは、 その立場にふさわしい人文的教養やマナーを身につけるよう、教育を受けるようになったものと拝察できます。中世の最後あたりから、宮廷文化そのものは育ちつつありましたが、人文主義的教養がクローズアップされるのはルネサンス以後でしょうし、イタリア国外に全面的にそれが広がっていくのはカトリーヌ以後でしょうから、たぶんそうそう間違っていないと思います。その後の華やかな宮廷文化に連なる芸術的素養とマナーを身につけた深窓の令嬢は、この頃から王族の家庭、やがては貴族の家庭で育てられるようになったものと思います。
こんなところで勘弁してください。
関連記事
-

-
21世紀を考える会「仮想通貨の現状」岩下直之京都大教授の話を聞く 2018年4月20日
Bitcoinの発掘の仕組み 256ビットの最初の30個は零が続かなければらないという約束。ハッシュ
-

-
Quora 「汎化性能」
すべてのデータサイエンティストが知っておくべき、統計学の重要なトピックはなんでしょうか?
-
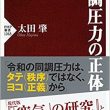
-
地域観光が個性を失う理由ー太田肇著『同調圧力の正体』を読んでわかったこと
本書で、社会学者G・ジンメルの言説を知った。「集団は小さければ小さいほど個性的になるが、その集団
-
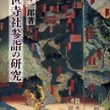
-
『近世社寺参詣の研究』原淳一郎
facebook投稿文章 「原淳一郎教授の博士論文「近世社寺参詣の研究」を港区図書館で借りて
-
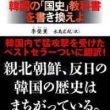
-
書評『大韓民国の物語』李榮薫
韓国の歴史において民族という集団意識が生じるのは二十世紀に入った日本支配下の植民地代のことです。
-
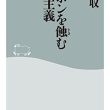
-
『ニッポンを蝕む全体主義』適菜収
本書は、安倍元総理殺害の前に出版されているから、その分、財界の下請け、属国化をおねだりした日本、
-

-
動画で考える人流観光学 マクスウェルの悪魔
【物理学150年の謎を日本人教授が解明】マクスウェルの悪魔が現れた!/東京大学 沙川貴大教授/教え子
-

-
伝統も歴史も後から作られる 『戦国と宗教』を読んで
横浜市立大学の観光振興論の講義ノート「観光資源論」を作成するため、大学図書館で岩波新書の「戦国と宗
-
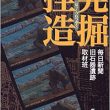
-
『発掘捏造』毎日新聞旧石器遺跡取材班
もう20年も前の事であるが、毎日新聞取材班の熱意により旧石器遺跡の捏造事件が発覚した。その結果、

