Quoraに見る歴史認識 終戦後に当時のソ連は、どうして北海道に侵攻しなかったのですか?
公開日:
:
最終更新日:2020/12/01
歴史認識
終戦後に当時のソ連は、どうして北海道に侵攻しなかったのですか?
回答を先に書けば、米国との間で、北海道侵攻は約束されていなかったからです。そして、別に攻め込まなくても北海道はソ連のものになるとスターリンが信じていたからです。
ここに示すのは1945年8月16日に米・国防総省が作成した連合国による日本分割占領案です。米軍は占領後に想定されるゲリラ抵抗(いつの時代のどの占領にもあります。近年ではイラクやアフガンでの事態が記憶に新しいところ)での損害を数万と見込んでいて、そのリスクを連合国で分担すべきだと考えていました。
スターリンは米国に送り込んでいたスパイ網を通じて、このプランを知っていたと思われます。そして、当日(8月16日)トルーマン大統領に北海道の占領を要求します。
一方、米国務省は早くからルース・ベネディクトなどの人類学者に依頼して日本人の民族性を基に占領政策の研究を行っていて、その結果、「米軍が想定するようなゲリラ抵抗は起きない」という内容の結論を得て、「米国単独占領で日本政府を存続させての間接統治をおこなうべきだ」と言う勧告書を作成して大統領に提出していました。
トルーマンは48時間の熟慮の末、国務省の勧告を受け入れスターリンの要求を拒否します。本当にスレスレの決断でした。日本人の知らない間に、北海道の命運は180度変わったのです。よく、ソ連が日本の敗戦を知って勝手に攻め込んできたと勘違いしている人がいますが、そうではありません。(そんな勝手なことをしたら米国が黙っていません)ソ連は連合軍の一員として、約束を守って参戦しています。
米国は、太平洋諸島などでの損害の大きさから、単独で日本本土への侵攻作戦を行った時の損害予測にたじろいでいました。そこで、ソ連に共同侵攻を持ちかけたのです(ヤルタ会談の極東密約)。スターリンは当初、日ソ中立条約を盾にこれを断りましたが、米国は国際法の専門家の意見も添えて、「国連憲章にもとづく大義により個別の条約違反は国際法に違反しない」との見解を添えて説得を続け、スターリンを口説き落としました。
しかし、スターリンは最小の犠牲で最大の効果を得るためにタイミングを見計らっていました。そして、事実上の終戦後になって、ようやく約束の軍事行動を起こします。米国側が鼻白んでいたのは隠しようがありません。冷戦がはじまっていたこともあり、米国は1956年に、ヤルタ協約はルーズベルト氏が個人的に行ったもので、米国政府はあずかり知らない、とまで言っています。
関連する事項を時系列でまとめると以下の通りです。
1945年
- 2月4日-2月11日、ヤルタ会談で樺太(サハリン)南部及びこれに隣接するすべての諸島、千島列島、満州権益と引き換えにソ連が対日参戦を約束。
- 8月8日、ソ連対日宣戦布告
- 8月9日、ソ連対日参戦
- 8月15日、日本ポツダム宣言を受諾
- 8月16日、スターリン、北海道の半分をソ連占領地とするよう、トルーマン大統領に要求
- 8月16日、米・国防総省の日本占領案「日本とその領土の最終占領(Ultimate Occupation of Japan and Japanese Territory)」(JWPC385/1)成立。それによれば、ソ連の占領地は北海道、東北地方
- 米国務省、独自の分析により「日本人の占領後のゲリラ抵抗は起きない」との結論を得て分割統治の回避を勧告。(ルース・ベネディクト「菊と刀」などの分析による)
- 8月18日、トルーマン大統領は国務省勧告を受け入れ、ソ連占領を拒否。
- 8月22日、日本政府を存続させての間接統治案を承認。
- 9月2日、日本、降伏文書に調印。日本占領開始。
ソ連が4月に日ソ中立条約破棄と同時に日本侵攻を開始していたら、北海道はソ連領になった可能性もあったように思います。
関連記事
-

-
山泰幸『江戸の思想闘争』
社会の発見 社会現象は自然現象と未分離であるとする朱子学に対し、伊藤仁斎は自然現象
-

-
『天皇と日本人』ケネス・ルオフ
P114 マイノリティグループへの関心 p.115 皇室と自衛隊 他の国の象徴君主制と大きく
-

-
保阪正康氏の講演録と西浦進氏の著作物等を読んで
日中韓の観光政策研究を進める上で、現在問題になっている「歴史認識」問題を調べざるを得ない。従って、戦
-

-
Quora 物語などによくあるように、中世ヨーロッパの貴族たちは国民から搾取してすごく贅沢な暮らしをしていたのですか?
中世に今日と同じ意味での「国民」はまだ存在しません。領主が農民を支配し、領主同士に主従関係
-

-
『シベリア出兵』広岩近広
知られざるシベリア出兵の謎1918年、ロシア革命への干渉戦争として行われたシベリア出兵。実際に起
-

-
Quora6に見る歴史認識 イギリスが中国にアヘンを売ったのは有名です。あるイギリス人の言い訳が、アヘンを売り始めた頃中国には麻薬の売買を禁止する法律が無かったから問題ない。これ真実ですか?それにしても犯罪者の理屈ですよね?
アヘン戦争に対する一般的なイメージ。それは以下の様なモノです。 「大英帝国が清国を麻
-
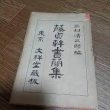
-
中国文明受入以前は、藤貞幹は日本に韓風文化があったとする。賀茂真淵は自然状態、本居宣長は日本文化があったとする。
中国文明受入以前は自然状態であったとする賀茂真淵、日本文化があったとする本居宣長に対して、藤貞幹
-

-
保護中: 7-1 先行研究1(高論文要約)
高論文 「観光の政治学」 戦前・戦後における日本人の「満州」観光 (満州引揚者)極楽⇒奈落 ホ
-
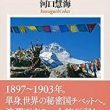
-
河口慧海著『チベット旅行記』の記述 「ダージリン賛美が紹介されている」
旅行先としてのチベットは、やはり学校で習った河口慧海の話が頭にあって行ってみたいとおもったのであるか
-

-
歴史は後からの例「殖産興業」
武田晴人『日本経済史』p.68に紹介されている小岩信竹「政策用語としての「殖産興業」について」『社

