天保の改革「人返しの法」 江戸の人口を減少させ地方の農村部の人口を確保することを目的に発令された法
公開日:
:
最終更新日:2023/05/27
人口、地域、
人返しの法(ひとがえしのほう)は、江戸時代の天保の改革において、江戸の人口を減少させ地方の農村部の人口を確保することを目的に発令された法。人返し令(人返令)とも称される。
前史
松平定信が寛政の改革において、この人返しの法と似た法令である旧里帰農令を発令した。こちらは離村して、江戸に流れてきた地方の農民たちに元の村々へ帰ることを勧め、そのための旅費・食費を幕府が交付する、というものだった。しかし、この法令には強制力がなく、また費用の交付も十分では無かったため、ほとんど効果がなかった。
天保12年(1841年)、大御所家斉が死去すると、忠邦は改革派の勢力をつくり、相次いで家斉の寵臣を粛清。遠山景元や鳥居耀蔵といった人材を登用し、天保の改革をスタートさせた。天保13年(1842年)8月、忠邦は町奉行に対し強制的な帰村を命じる政策について評議させたが、慣れ親しんだ江戸での生活から無理矢理引き剥がして帰村させるのは現実的では無いと回答して、強制帰村の政策に反対した。翌年の再評議においても意見の大筋は同様で、帰村を強制するよりもまずは人別改を強化した方が良いとの回答があった。これを受けて天保14年(1843年)、人返しの法が発令された。主な内容は、
- 新規に在方の農民が江戸の人別帳に入ることを禁止。
- 出稼ぎなどで短期間江戸に居住する場合は、村役人連印の願書に必ず領主の押印がある免許状を必要として、これが無い者には江戸で住居を貸す・奉公させることを禁止、そしてまた出稼ぎの者を江戸の人別帳に登録することも禁止とした。
この人別改の強化で江戸の人口増加を防ぐ狙いがあったが、その効果については疑問視されている。
関連記事
-

-
動画で考える人流観光学 日本のリゾート地
ストロー現象 https://youtu.be/1Sdan-uAOoA
-

-
文化人類学で読み解く北朝鮮社会 伊藤亜人 公研 2017年10月号No.650
韓国人がなぜ、国内海外を含めてあれほど旅行をするのか考えていたが、一つの答えが見つかったような気がす
-

-
幸田露伴『一国の首都』明治32年 都議会議員和田宗春氏の現代語訳と岩波文庫の原書で読む。港区図書館にある。
幸田露伴は私の世代の受験生ならだれでも知っている文学者。でも理系の人でもあり、首都論を展開してい
-

-
『日本経済の歴史』第2巻第1章労働と人口 移動の自由と技能の形成 を読んで メモ
面白いと思ったところを箇条書きする p.33 「幕府が鎖国政策によって欧米列強の干渉を回避した
-

-
『鉄道が変えた社寺参詣』初詣は鉄道とともに生まれ育った 平山昇著 交通新聞社
初詣が新しいことは大学の講義でも取り上げておいた。アマゾンの書評が参考になるので載せておく。なお、
-
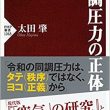
-
地域観光が個性を失う理由ー太田肇著『同調圧力の正体』を読んでわかったこと
本書で、社会学者G・ジンメルの言説を知った。「集団は小さければ小さいほど個性的になるが、その集団
-
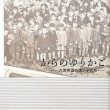
-
『からのゆりかご』マーガレット・ハンフリーズ 第2次世界大戦後英国の福祉施設から豪州に集団移住させられた子供たちの存在を記述。英国、豪州のもっと恥ずべき秘密
第2次世界大戦後英国の福祉施設から豪州に集団移住させられた子供たちの存在を記述。英国、豪州のもっ
-

-
中国の観光アウトバウンド政策 公研No.675 pp45-46
倉田徹立教大学法学部教授 1997年にアジア通貨危機、2003年にSARS流行発生時、香港経
-

-
観光学を考える 『脳科学の教科書 神経編・こころ編』岩波書店 理化学研究所脳科学総合研究センター編 をよんで
図書館でこの二冊を借りてきて一気に読む。岩波ジュニア選書だから、子供が読む本だけれど私にはちょうどい
